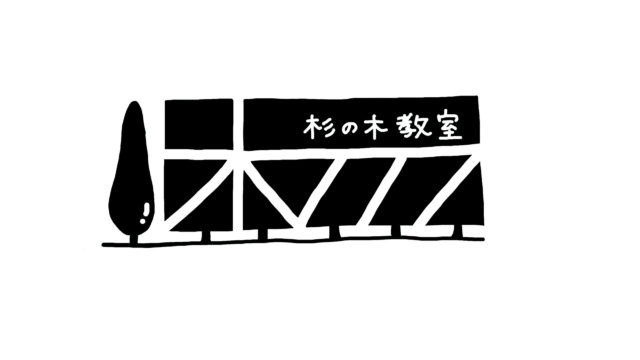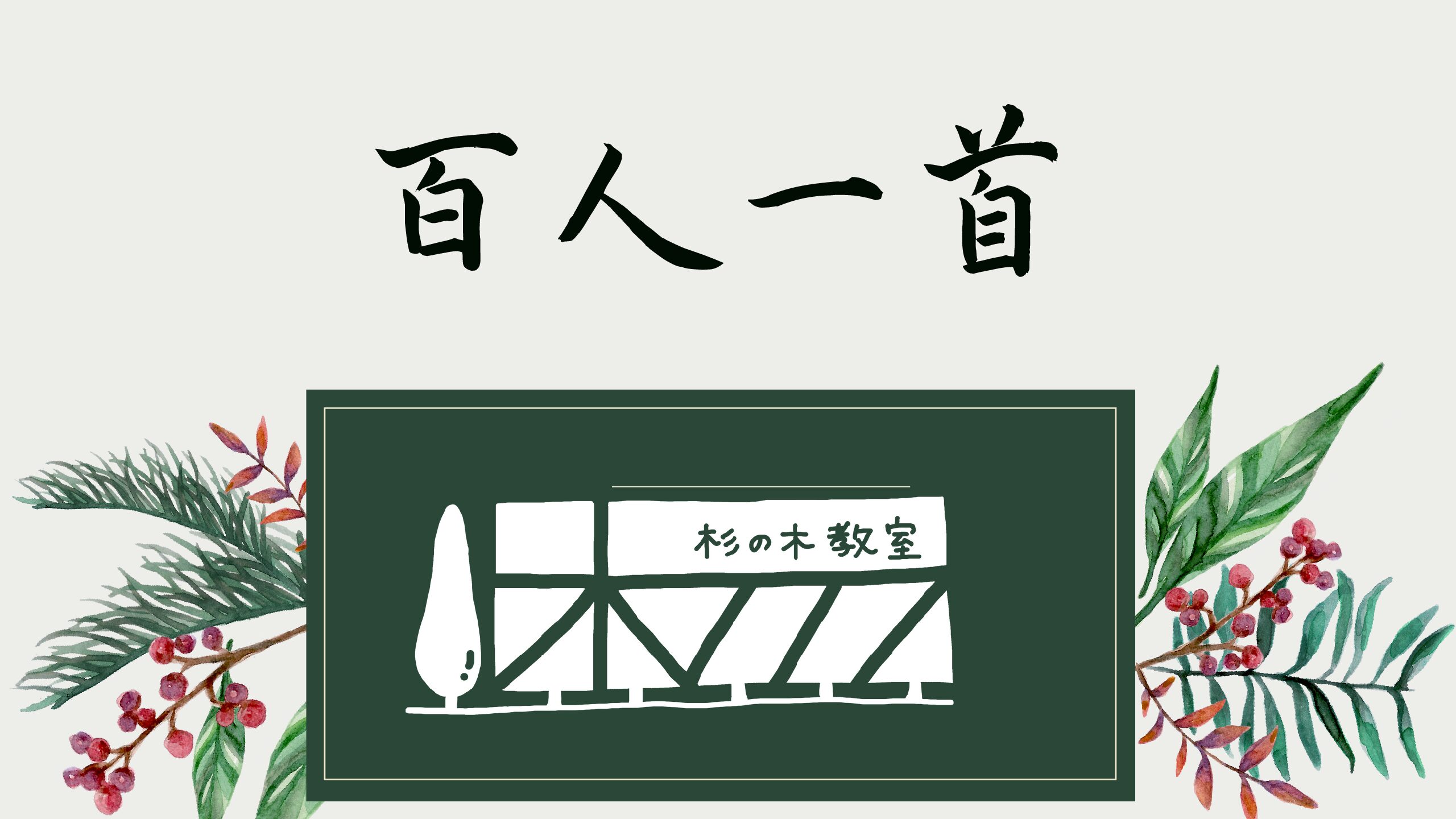百人一首
百人一首 花の色は移りにけりないたずらにわが身世にふるながめせし間に
*花・・・ここでは桜。古典で花といえば桜のこと。*花の色・・・「桜の花の色」と「女性の若さや美しさ」も表されている。*移りにけりな・・・「移る」は「色あせる、変わる」の意。「けり」は過去の助動詞。「な」は詠嘆の終助詞。よって2句切れになる。*いたずらに・・・無駄に、むなしく*世にふる・・・「世」は「世代」と「男女の仲」の掛詞。「ふる」も「経る(ふる)」の「時が経つ」と「降る」の掛詞。「ずっと降り続く雨」と「年を取っていく私」の2つの意味がある。*ながめ・・・「眺め」と「長雨」の掛詞。