哲学書を書こうとしている。その一つ目の骨子は「言葉」である。私の思索の始まりは、頭の中にあるものをとにかく書き出す「モーニングページ」という習慣から始まっている。「あれ」ではなく「これ」であるという分節は言葉以前からあるが、言葉をもって体系化しなければ世界は説明できない。二つ目は「関係性の存在論」である。言葉によって分節された全ては関係しあっているので、観察者もその関係から逃れることはできない。全てはそれぞれが互いに存在することを可能にしあっているのである。三つ目は、「根」と呼んでいるもので、われわれという存在の根本である。いわゆる天地創造のはじめを求めているのではなく、個人の始まりを求めているのである。このような三つの骨子を元にして、世界説明をする書物を書き上げようとしているのだ。
三つ目の「根」については、まだまだ思索中である。われわれは何人もある国家に生まれ、その影響を受けている。よって国家がわれわれの「根」の一部であることは間違いないと思う。そしてさらにその国家の歴史というものがわれわれを底から支え、また精神的には言葉が大きな役割を果たすと考えている。歴史的な言葉というと古文である。この古文を深く理解することが、「根」を深く理解することになると考えた。それで古文作文というものに興味を持って、毎日少しずつ書いてはいるが、よくわかっていない。できているのかどうか、それは何によって判断するのか。参考に出雲路修氏の『古文表現法講義』を買ってみたが、自分の文章があっているかは最終的にはわかっていない。だから「古文めいた」ものを作って楽しんでいる。しかし出雲路氏は、「国文学とは、辞世の一首を詠むための学問である」と言い、つまりは自分自身の中に思想・信仰を確立し、それをひとつの言葉で表すための学問であるそうで、重要なのは「ひとつの言葉」という簡素でありながらも深い意味を帯びた表現ということであろうか。わかったようなわからないような、もっと修行が必要そうな学問である。
そんなことで漠然と日本語に興味を持っていたところに、本屋で金谷武洋著「日本語と西欧語」を見つけた。主語の有無によって、その言語の視点が違うというもので、主語のない日本語は「虫の視点」で、主語がある西欧語は「神の視点」であるという。この本はまだ少ししか読んでいないが、私の哲学書作りにヒントを与えてくれている。言葉の分節力が重要と考えているだけに、この存在論ともつながる言語の分析に興味を持っている。
金谷氏によると、「日本語はある状況を、自動詞中心の『何かそこにある・自然にそうなる』という、存在や状態の変化の文として表現する。一方、英語は同じ状況を、『誰かが何かをする』という意味の、他動詞を挟んだSVO(主語―他動詞―目的語)構文で示す。つまり、人間の行為を積極的に表現する傾向が強い」という。例えば、日本語の「お金がある」ということを英語では「I have money」という。お金がそこにあるという存在や状況を示す日本語に対して、英語では「私は」お金を持っているという人間の行為を示している。その他「中国語がわかる」に対して「I understand Chinese.」、「時間が要る」に対して「I need time.」、「声が聞こえる」は「I hear a voice.」。
このように日本語には動作主としての主語はないが、英語には動作をする主語がある。このことが世界観の違いを生むというのだ。確かに英語の勉強しているときにつまずくのは、その語順と主語を何にするかということである。語順は徐々に慣れてゆくが、主語の方はうまく馴染まない。このこのような違いが世界観を変えるというのは、どういうことなのであろうか。
金谷氏は川端康成の『雪国』の英語訳と原文との比較をとおして説明している。この名著の冒頭は、原文では、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」であるが、E・サイデンステッカー氏の英語訳では、「The train came out of the long tunnel into the snow country.」となっている。この二つの文章の間には「視点の違い」があるという。原文の方は、主人公が汽車に乗っている情景を思い起こさせ、読者もそれを追体験するような表現だ。暗いトンネルを抜け、明るくなった外の景色は、雪に埋もれていた。そのように「時間の推移とともに」景色が変わっていく様子が思い浮かぶ。(図1)一方、英語訳の方は、汽車が走っている風景を思い起こさせ、それを上方から見下ろすような表現となっている。列車がトンネルから頭を出しており、トンネルの外には雪が積もっている。このように暗闇から雪景色というような「時間の推移」は感じられず、止まった景色が思い浮かぶのだ。(図2)


これら二つの文を比較すると、原文には主語がなく、時間とともに変化する主観的な体験の描写がある。確かに「自動詞中心の『何かそこにある・自然にそうなる』という、存在や状態の変化の文として表現」している。これに対して、英語訳は「The train」という主語があり、時間の経過はなく、上方から見下ろす客観的な描写となっている。「『誰かが何かをする』という意味の、他動詞を挟んだSVO(主語―他動詞―目的語)構文で示」している。金谷氏はここに世界観の違いを見ている。そしてそれぞれを「虫の視点」と「神の視点」と呼んでいる。「虫の視点」では、話者の視点は対象化、客体化されずに出来事の内部にとどまっており、まるで虫が草むらを這ってゆくように次々と出来事が起きて、時間が経過してゆく。一方「神の視点」では、自分を包んでいた自然から自己を引き離し、もはや自分自身も対象化して、出来事の外部の上空から客観的に眺めており、その出来事を一気に把握し、時間の経過がない。この脱近代的な違いを言語の主語の有無やその視点において捉えているところが、私には大変興味深く、そして思索を進めることとなった。
私が大切にしている「言葉」という分節の、関係を生み出す構造である具体的な文法面で、主語という存在を扱い、その有無によって、近代的な物自体の概念を捉えている。つまり主体は、それを超越した存在、すなわち神から見下ろされている。そのことによって主体は対象化され、相対化されてゆく。このことは自己の喪失として問題になっているが、それが言語の文法上の特性として捉えられていることは、その修正に関して、言語的なアプローチが日常のレベルで可能なことを指し示しており、希望がある。現代の英文法的な主語の必要性を排し、主語を必要としない言語の構造を持ち込むことによって、自己の喪失を防ぐことができるのではないだろうか。神の座を設け、そこに人間の理性を据えたことによる近代、またさらには現代の問題を解決する力となるのではないだろうか。
また、金谷氏によると、かつては英語にも主語がなく、「虫の視点」からの描写があったそうだ。このことは、われわれの「根」を考えるとき、「虫の視点」すなわち主観的な、そして時間的推移のある言語表現が根源的であると思われる。というのは、われわれの「根」は、その国家と深く結びついており、その歴史や言語を深く理解することは重要なことである。古い言語には主語がなく、視点が「虫の視点なのである。そしてその国家は、「私の」国家であり、その歴史は「私の」歴史であり、その言語は「私の」言語である必要がある。というのは、関係性の存在論でいうと、対象と「私」は関係で結ばれており、外側から眺めることはできない。具体的には、日本は世界中の196カ国のうちの一つの国ではなく、私が生きる国であり、日本語は、世界中の7000ある言語の一つではなく、私が思考する言語であって、この関係を無視した国家や言語の理解には、ホワイトヘッドのいう「抽象化したことを忘れて具体的なものを取り違える間違い」を起こしてしまう。その間違いを犯しながらの自らの国家や言語の理解は、文字通り過ちを犯し、根無草となってしまう。古代の英語には主語がなかったように、日本語の古文においても現代語よりも主語は少なく、敬語表現という話者から見た上下関係によって、主語を表現するという主観的な表現が多く用いられていることは、古代においては世界中で主語のない言語が多く、その認識また世界観は私たちの「根」であるといっていいのではないだろうか。それは抽象化された、または名付けられた経験ではなく、ナマの経験そのものなのである。
この「虫の視点」は現象学的な視点と似ている。谷徹氏の『これが現象学だ」』は、フッサールの根源的着想として直接経験が紹介され、そこにはこのような説明がされている。まず普通の経験は、「外部から物理的刺激が到来して、それを私が受け取る(見る)ことによって、知覚が成立するといったイメージ」であるとしている。(図1)次に直接経験は、エルンスト・マッハの絵を用いて説明している。(図2)「これは右目を閉じて左目だけで見た時の光景である。絵の右側に見えているのは、マッハの鼻であり、その上の方に伸びているのは眼孔である。・・・」つまりは、私たちの目で見ているそのままの絵なのである。現象学はこの図2の視点からの眺め、直接経験から始めると紹介しているのだ。


この二つの視点はまさに図1=「神の視点」と図2=「虫の視点」であり、私が思う「根」である「虫の視点」から始めるべきだとする主張は、現象学のそれと同じである。主語がないというのは主体の不在ではなく、主体の視点のみの存在である。そこから始めるべきなのだ。
そして谷氏はこう続ける。「図1は『客観的』だと思い込まれているが、しかし、じつは図2のような直接経験から出発して事後的に形成されるイメージである。」「あるいは、図2のような経験は、『主観的』だが、単に主観的だというのではなく、まだ「客観的」ではないという意味で『主観的』であり、これこそが『客観性』の前提なのである。」つまり「虫の視点」から始まって、それは「神の視点」へと発展してゆくということなのである。
現象学におけるこの主観と客観の問題については、まだ深く理解できていないので、これ以上は書くことはできない。私の意見では、現象学の客観=「神の視点」は、直接経験=主観=「虫の視点」の抽象化であり、ここからさらに抽象化を重ねてゆくと、具体的なものとのずれが生じてしまうと思っている。例えば、因果を遡ってゆき神が全てを創造したという言説などである。「人間の認識がやむところ、そこに人間の信仰が始まる」と言ったのはニーチェだが、創造主という信仰はあまりにも幻想的である。認識できないところまで来たら、その先は語らないのが誠実だと思う。
「根」については、まだまだ考えたい。「虫の視点」=直接経験がその中心であることは間違い無いと思うが、その周囲に広がる言語的世界がどのような構造になっているかは注目すべきところである。そしてこの構造は「関係性の存在論」であって、「根」と「関係性の存在論」は、同じものを違う角度から見た別名であるかもしれない。「神の視点」についても、これが全くの誤りであるということはできない。この視点なしには科学は発展しなかったであろうし、それは西欧だけのものでも無いと思う。とにかくまだまだスッキリと説明ができない、そして見通しもついていない、これからの未熟な哲学書である。がしかし虫のように這いながら、また神のように空を飛びながら、着実にその体系を構築していきたい。
令和6年9月21日
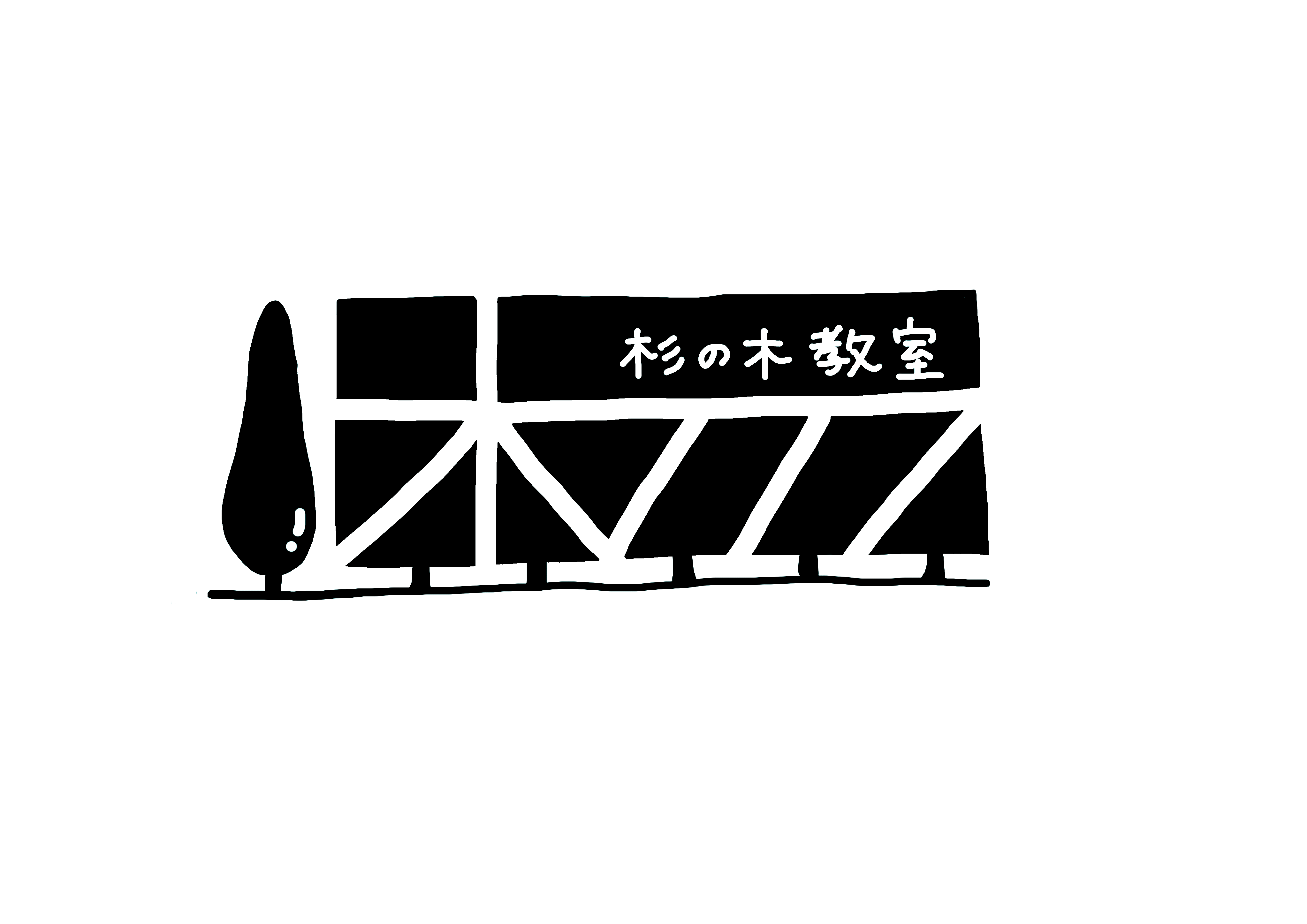
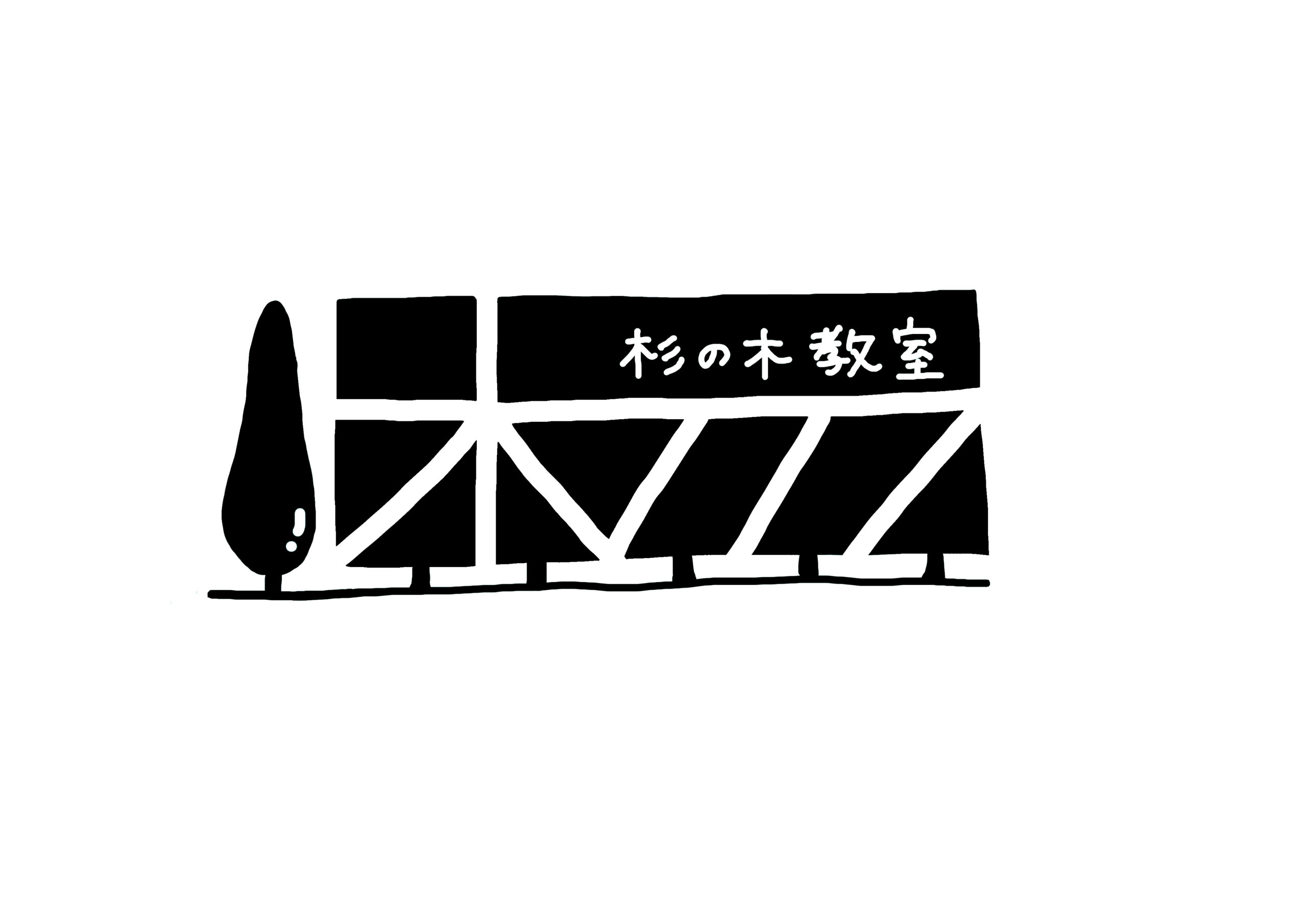
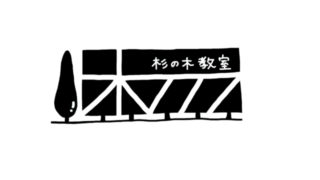

コメント