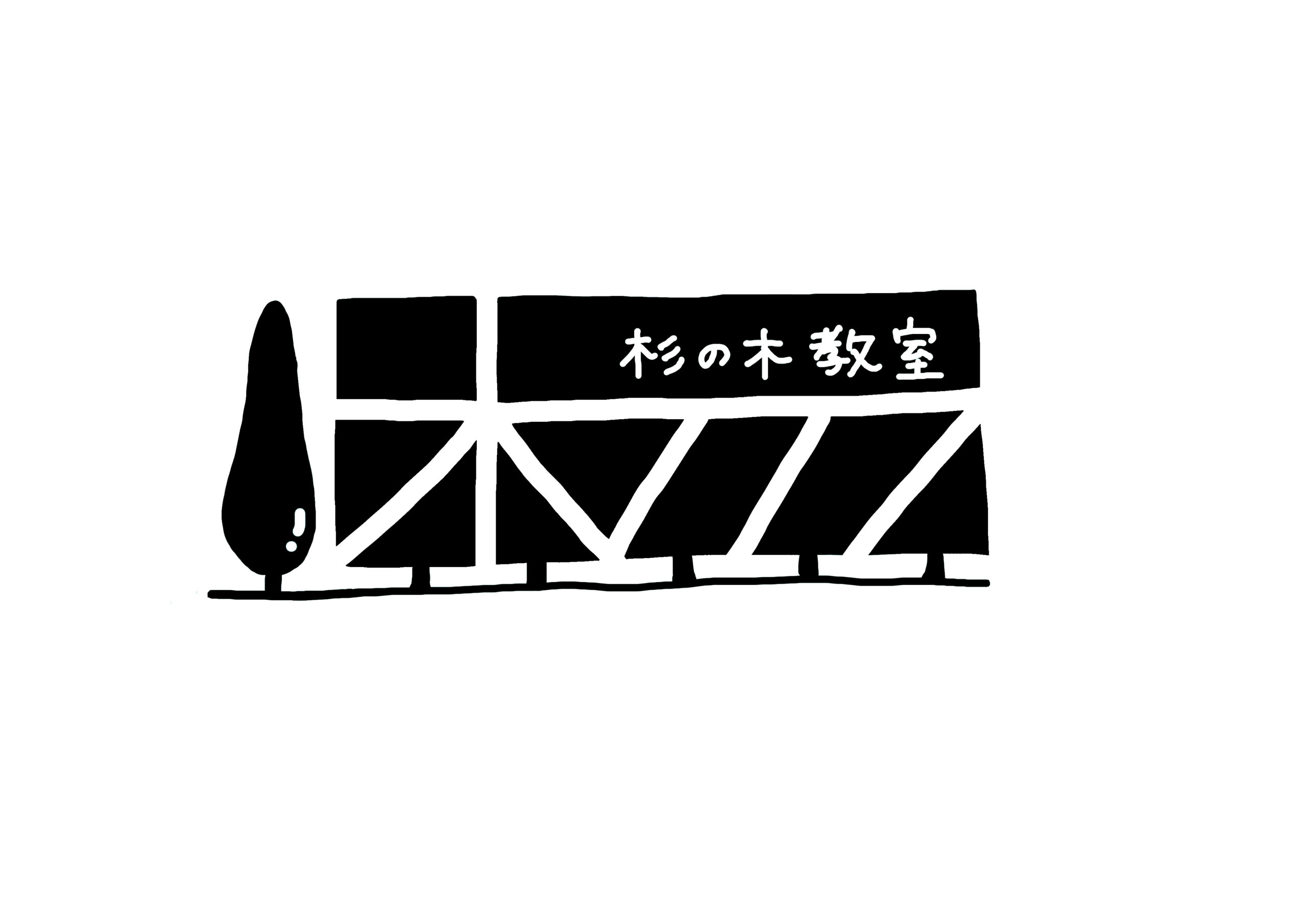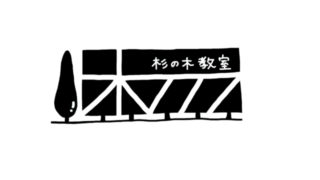関係性の存在論を語るのに、具体的な関係の研究が必要だと感じ、紆余曲折を経て中小企業診断士の試験を受けることにした。これは学問的な興味と合わせて実生活での要請もあった。資格を取ることで、神主として神社の経営に貢献できることと、副業などができたら個人的な収入も得ることができるのは、一石二鳥である。しかもその勉強が面白いと感じているのだから、この方向に進まずにはいられなかった。
試験は8月2、3日の2日間に分けてマークシート式の一次試験がある。7科目あるうち4科目が60分、3科目が90分の試験時間である。その後10月26日に二次試験の記述試験、年明けの1月25日に口述試験がある。これらに間に合うように計画的に勉強を進めなければならない。以前に家庭教師のバイトをしていたことがあるので、生徒には偉そうに指導していたわけであるが、いざ自分が受験するとなると少し戸惑った。一体何からすれば良いかわからなかったのである。
入門書は買っていた。『みんなが欲しかった!中小企業診断士 合格へのはじめの一歩』。この本は、7科目を少しずつ説明していて、どのようなことを勉強するのかを知るにはちょうど良かった。これを読んでさらに興味が湧いてきたので受験をすることに決めたのだった。読み終わったこの本を眺めながら、資格試験の受験勉強の計画を立てたのだ。
まずは入門書で大まかな内容がわかったので、今度はそれぞれを細かく勉強していく。それが終わったら問題集でさらに細かく進め、最後は過去問を解いていくということにしたのだ。ここで重要なのは、繰り返すことである。細かく勉強することは重要であるが、完全に理解するまで次に進まないようなやり方では、時間がいくらあっても足りないので、たとえ理解ができていなくても次に進み、全体を大きく理解してゆくことに注力をしていく。そして同じテキストや問題集を繰り返すことで徐々に細部の理解を深めていこうとしているのだ。
現在はテキストを2冊読み終わったところだ。7科目のテキストはそれぞれ300ページほどある。なかなか手強いが、前述の通り理解ができなくても次に進み、全体を徐々に把握していっている。『企業経営理論』は馴染みがある事柄が多かったので比較的順調にいったが、『財務・会計』は会計上の専門用語やそれらを使った計算式が複雑で、ただ読んでいくだけでもなかなかしんどい思いをしたのだった。
2冊目が終わったところで、少し復習をしようと体系図を書いた。科目の中の論点を紙1枚に書き出して、それぞれのキーワードを書き添えたり、線で結んで関係性を記したりしたのである。これは良い復習となった。論点と論点が結びつくことで、より深い経営についての知識となっていることがよくわかったのである。たとえば、『企業経営理論』では、企業活動の経営戦略を扱う。これは企業の内部と外部を分析して、より利益を上げることができるように活動を最適化していくものである。この時、内部の分析にあたっては同じ『企業経営理論』で扱う「組織論」や『財務・会計』で扱う「経営分析」が役に立つ。組織の構造やその人的資源の強みを有効活用したり、また過去のデータを元に無駄を省いたり弱みを補填することができる。外部の分析にあたっては、同じく『企業経営理論』で扱う「マーケティング手法」や『経済学・経済政策』で扱う「マクロ経済」の知識が役に立つ。市場を細分化してセグメントごとに適した商品の開発をしたり、大きく国内の景気の動向やさらには世界経済にも目を向けて、今後の企業の進むべき道を探るのである。
このように1つの知識が他と繋がり合うことで新たな意味を持ち始めるので、楽しくなるのだ。紙1枚に体系図を書き出して「全体から個、個から全体へ」と視点を移しながら勉強を進めてゆくことは、限られた時間内により多くの知識を効率よく取得することを可能にし、また様々な角度からの発見もあって理解を深めることができた。また自分が今理解できていないことが、他のどのような論点と結びつくのかを知ることで、その困難に立ち向かうモチベーションにもなっている。最初に計画した勉強法ではなかったが、今後適宜この「全体から個、個から全体へ」の視点移動を繰り返しながら、進めてゆきたい。
「全体から個、個から全体へ」ということでいうと、この資格の勉強という「個」が、私の人生という「全体」の中でどのような意味を持つかにまで想像が膨らんだ。これは初めに述べたように、学問的な興味と実生活での活用がキーワードとなる。私の生活を細かく分けてゆくと、仕事、哲学、家族、友人、音楽、などであろうか。中小企業診断士という資格は経営に関する専門的知識の集合であるので仕事に関わりがあることはもちろんであるが、さらには哲学という学問にも関係を持っている。「経済学・経済政策」では、マクロでの経済の動きを分析しているが、このことは関係性の存在論を考える上で良いモデルとなるだろう。また多くの人間にとって仕事は人生のほとんどの時間を費やすものであると思うが、その目的や意義を考えることは人生を哲学することにもつながる。
また現実の問題として仕事で成功することは、家族を養ってゆくためには欠かせない要素である。離婚をして子供たちと別居をしている私であるが、今再婚をしようとしている。相手にも子供がおり、その養育を担っていこうと思っている。お金が必要であることは言うまでもないが、彼らの幸せが何よりも、私の人生にとって重要なことである。あらゆる手段でそれを実現していかなければならない。この資格は経済的にもまた精神的にも私の力になってくれるのではないだろうか。
そのような「全体」の中でそれぞれの「個」が担う役割を考えていくと、また違った意味が生まれてくる。思いつきのようなこの資格受験は、いろんな問題を解決してくれるかもしれないのだ。
哲学書を書いている。去年たてたこの目標の期日は、今年の4月19日までに、その第一校を書き終えると言うものである。今その原稿がどう言うものであるかというと、書いては消し、消しては書いて、次の文言だけが残っている。「すべては空で、縁起することにより、現実存在する。そして諸行は無常である。」
「空」とは、「何もない」というような意味である。「縁起」とは「関わりあう」というような意味だ。つまりすべてはそれだけでは存在せず、関わりあうことで現実に存在する。そしてそれらは「無常」すなわち、止まることなく変化しているのだ。
こんな当たり前のことしか書いていない。しかしこの当たり前の命題は、疑い得ないものであると思う。私の哲学書の始まりとしてはいい始まりである。この第一校は全てと関係しながら発展してゆくだろう。
今、「全体から個、個から全体へ」という勉強法を行なっているが、これもまた「個」だけでは存在しないが、「全体」として関わりあうことで現実的となると言うような存在のあり方に沿っている。さらにそれらは静止しておらず変化するため、常に「全体から個、個から全体へ」と視点を移して見張っておかないと認識を誤ってしまう。この試験勉強はできるだけ成功させたいが、私の人生はなんとしても成功させなければならない。「全体から個、個から全体へ」と視点を移しながら、ふでのまにまに勉強を進める。
令和7年4月1日