久しぶりに訪れた島本町、私の育った町である。ここへは5歳の時に引っ越ししてきた。生まれたのは福知山であるが、なにぶん小さかったために何も覚えていない。かろうじて覚えているのは、自分の背丈ほどに雪が積もっていたことぐらいだ。背丈と言っても4歳ごろであるから、1メートルほどであっただろう。自分が埋まってしまうくらいの雪景色だったので、楽しくて仕方なかったというかすかな記憶だけがある。だからその後に育った島本町が私の故郷だと思っている。この町には雪は降らなかったが、積もりに積もった思い出がたくさんある。友達と遊んだり、初恋や失恋、音楽や哲学を学びはじめ、神主としての一歩を踏み出したのもこの町に住んでいた頃であった。
先日のライブに来てくれた幼馴染が、この島本で写真展をするというので、まだ朝晩は少しひんやりとするが穏やかで過ごしやすい気候の中、懐かしい駅に降りた。桜の花が咲いていた頃は、晴れの日が長く続いており乾燥して埃っぽかった。それと合わせて花粉もたくさん飛んでいたようで、いたるところがざらざらとしていて気持ち悪かったが、桜の花を勢いよく片付けて舞台の場面転換でもするように、強い雨と風がやってきて、一気に埃や花粉を洗い流し真新しい新緑の季節を運んできた。島本町にある水無瀬という阪急電車のこの駅は、私がまだここにいた頃、沿線で一番トイレが臭い駅として有名であったと思う。古くて使う人も少ない、そんな田舎の町にある駅であった。今でも都会でないことは確かではあるが、駅のトイレも綺麗になり、人も増えて、若葉のような瑞々しさを感じた。
5歳でこの町にやってきた私は、幼稚園の年長さんのクラスに入った。ゆり組で、担任は藤井先生という、見るからに優しそうな太った女性であった。私は何でもおもちゃにしていたそうで、例えばアイスクリームの蓋を手裏剣にしたり、割り箸に顔を描いてロボットにしたりしていたので、藤井先生からは「おもちゃちゃん」と呼ばれていたと当時の連絡帳に書いてあった。またその頃から音楽が好きであったようで、合奏会で大太鼓を叩いたことがとても嬉しかったようだ。ニコニコとしながら自分の体ほどある太鼓の前に立って、先生が叩くタイミングを教えてくれるのを「今か今か」と待っている「おもちゃちゃん」の写真が残っている。
ゆり組にはバンドでアルトサックスを吹いているクニカズがいた。彼とは40年以上の付き合いになる。仲が良かったかは覚えていないが、粘土で耳を叩かれて、耳がキーンとなったのを覚えている。おそらくそれが、耳がキーンとなる経験を初めてした時であった。幼いクニカズは痛がる私を見て楽しかったようで、彼が笑っていたのを覚えている。耳がキーンとなるという初めての出来事に感じた不安と、クニカズの無邪気な笑顔が、おかしいくらい対照的であった、苦くもあり、また微笑ましくもある思い出だ。
写真展をするのは、そのゆり組にいたキタムラだ。彼女とはその後中学校まで同じ学校に通い、遊ぶ仲間も同じだった。みんなで祭りに行って浴衣の女子にドキドキした思い出などがある。キタムラは女子の中では一番仲が良かった。もっと正確にいうと心を許していた。気を使うことなく過ごすことができた数少ない友達の一人だ。卒業してからは特に連絡を取るわけでもなかったが、ライブで偶然に会ったり、久しぶりに話しても久しぶりじゃないように自然で、縁があると感じていた。今回はライブの告知をSNSで見つけたようで、連絡をくれた。普段は東京に住んでいるようだが、ちょうどその頃に島本で写真展をするからライブを見に行けると喜んでくれた。ライブが終わった後に少し話をすることができた。懐かしかったが、昨日まで一緒に遊んでいたような落ち着いた気持ちになった。「同級生が集まると、キタムラの個性的な生き方の噂が出るらしいよ」と、イタズラっぽく言ったら、「あんたもやで」と言い返された。彼女は世界中を旅したり、能楽堂で働いたりと珍しい経歴を持っている。私たち2人は、仲間の中では変な二人なのかもしれない。
駅に着いてから写真展までに少し時間があったから、自転車を借りてこの懐かしい島本の町を散策することにした。最初に行ったのは水無瀬神宮。後鳥羽天皇を祀る古社だ。子供の頃は自転車で友達とよく立ち寄った。お参りなどはしてなかったと思うが、離宮の水という全国名水百選に選ばれた水を飲んで喜んでいた。また石川五右衛門の手形が門に残っていたのを覚えていた。今回も子供の頃と同じように自転車で立ち寄った。五右衛門の手形はよく見えなかったが、神社は昔のままで嬉しくなった。離宮の水を飲み、子供の頃には興味がなかった植物に目をやった。立派な枝垂れ桜があり、紅葉の新芽も美しかった。葉山椒が生えていたりして、子供の頃には感じられなかった楽しさを味わった。
お参りを済ませてから次は「青葉の家」に行った。私は島本にいる間に1度引っ越しをしていて、1件目が「青葉の家」だ。当時でも古い家で、水洗トイレではなかった。壁もクロスではなく土壁で、こするとキラキラとしたものが手のひらにいっぱいついた。隣との間は薄い壁一枚だけで、隣の坂本さんのお兄ちゃんを遊びに誘う時は、壁越しに呼ぶこともできた。その次に2件目の「桜井の家」にも行った。自転車で5分ぐらいの距離で、急な坂の上にあり見晴らしのいいところだった。注文住宅のいわゆるマイホームで、建設中に楽しみすぎて毎日のように見に来ていた。「青葉の家」も「桜井の家」も佇まいは変わらなく、文字通り家に帰った気分であった。
そこから細い路地を通りぬけ線路沿いに走ると、通っていた小学校に着いた。昔は「田んぼ」に囲まれていてカエルがゲロゲロ鳴いていたが、今は住宅地の整地がなされていた。たくさんの人が住んで、私と同じように、この島本で多くの思い出を作ってゆくのは嬉しいことだが、よく知っている景色がなくなってしまったのは残念であった。皮肉にも「田んぼ」があった頃には気がつかなかった「田んぼ」の美しさを整地された住宅地の中に見出したのであった。
線路沿いの小学校への通学路にはトンネルがあった。高架の下を大人が立ってギリギリ通れるぐらいの高さにくり抜いた、なんともこじんまりとしたトンネルで、少し地面より下がっていたからか、いつも濡れていた。このトンネルは「マンボウ」と呼ばれていた。なぜこのような名前なのかは分からないが、実際に見てみると「マンボウ」という少し怪しげで、とぼけた感じがよくあっている。私たちは自転車で恐る恐る身をかがめながら通ったが、その後を地元のおじさんが勢いよく自転車で通って行った。おじさんの勢いは怖がっている私たちを小馬鹿にするように、そしてまた怖がる必要はないと諭すように意気揚々として勇ましかった。
時計をみると、まだ開場までは時間があったので、一緒についてきてくれていた彼女が事前に調べていた陶器屋さんに行くことにした。水無瀬の駅前にあり、私は行ったことがなかったが、そこにそんな店があることは小さい頃から知っていた。間口の狭い小さなお店で、店先には「やあ、こんにちは」と書かれた暖簾がかかっており、徳利やお猪口、土鍋や急須、籠や藍染の鞄などもかかっていた。私の記憶では全く興味のないガラクタばかりが置いてある店であったが、ところがその店先に出ているものに早速釘付けになった。薄い緑の大きな土鍋の色が印象的で、手触りも良く、何度も蓋を開け閉めした。徳利はぎっしりと籠に並び、どれも同じものはなく、わいわい賑やかに喋ってるようだった。店内から小柄な70代ぐらいのおじいちゃんが出てきて、声が小さかったから分からないが、おそらく「いらっしゃいませ」と言って、迎えてくれた。店内は、10畳ほどの広さだろうか、天井の低い部屋にたくさんの陶器が並んでいた。並んでいたというよりも積んであるというように、棚から溢れていた。天井からも急須や花器、古い裸電球や山葡萄の蔓で編んだ鞄などがぶら下がっている。新幹線が近くの駅を通り過ぎると店が揺れ、重ねられたお皿がカタカタなった。雑然と並べられた陶器たちであったが、手に取ると少しひんやりとして、よく手に馴染み、色も穏やかで、細かい模様が丁寧に描かれていた。思いがけず私はそこの陶器に魅了された。どれも触れてみたくなり、また使ってみたくなるものばかりであった。ガラクタではなく、丁寧に作られた品の良い器たちが私を興奮させたのだ。お店の名前は「とらやま」、おそらく店主のお名前であろう。その名前とは裏腹に穏やかで優しく、それでいてどこかに一本筋が通っているような方であった。店主の人柄と器たちが良く似ているような気がした。優しい心とそれを支える確かな技術があった。1時間以上見入ってしまい、急須と皿とマグカップを買って帰った。
「とらやま」で買った荷物をぶら下げながら、カフェネネムに向かった。写真展が開催されるお店だ。民家の一部を改装して作ったお店で、木目調の落ち着いた色合いと、レトロなサーキュレーターが印象的であった。30代ぐらいの女性が切り盛りしているようで、キタムラはいなかったが写真展を見にきたと言うと愛想よく案内してくれた。店内に20点ほどの作品が行儀良く、またトイレの中など、ユニークな感じにも飾られていた。キタムラがイギリスやインドなどに訪れた時の写真だそうだ。それらの写真の中に、小学校の周りの「田んぼ」と「マンボウ」と「とらやま」が映っていた。さっき自転車に乗って見てきたばかりの景色、いや小さい時から見てきた景色だ。「田んぼ」の写真には青々とした稲が揺れていた。「マンボウ」には小学生が大きく手を広げている。「とらやま」は「やあ、こんにちは」と言っていた。さすが幼馴染である、見ているところが同じであった。二人とも変人だからであろうか、もしくは島本に他に見るところがないからだろうか。私の思い描いていたものとは少し違ったが、妙に一致した景色に私は心を踊らせた。「実際に目で見た景色」も美しかったが、キタムラが撮った「写真」にも、違った味わいがあり心を打った。がしかし、当たり前だが島本の景色そのものではなく、あくまでもそれを写した「写真」であった。
これは「パロール」と「エクリチュール」の関係だと思った。「実際に目で見た風景」が「パロール」、「写真」が「エクリチュール」だ。これらはフランス語であり、「パロール」が「話されたこと」、「エクリチュール」が「書かれたこと」の意味である。古くより「話されたこと」の方が優れているとされてきた。なぜならそれは発話者に尋ねることができ、直接対話をして、より真実に近づくことができるからだ。一方、「書かれたこと」は、対話することができずに解釈をするしかなく、真実からは遠いと考えられてきた。「実際に目で見た景色」が真実、自然そのものに近い、だから優れているという認識だ。しかし、フランス現代思想家のジャック・デリダは「パロール」が唯一の真実ではなく、「エクリチュール」には多くの正当な解釈があるとした。つまり「実際に目で見た景色」、これが唯一の真実ではなく、「写真」という「エクリチュール」=「書かれたもの」、ここでは「解釈されたもの」には、たくさんの正当なもの、優れたものがあるということだ。キタムラが撮った「写真」は島本の真実を解釈した正当なものの一つであり、私の中にあるものと良く似ていた。しかし、景色そのものではない。
このデリダの思想は、発話者が語る真実を「パロール」は純粋に現前させずに、常に遅れて、少し違っているという「差延」の思想になってゆく。我々が「実際に目で見た景色」は、真実と少しだけズレている。そして「写真」ももちろん真実とズレているが、こちらの方がズレが大きいので人々はそのズレを意識している。一方、「実際に目で見た景色」とのズレは、少しなので意識できていない。意識できていないという点で、劣っている。さまざまな「写真」を見ることは、真実とのズレの多くの種類を見ることになり、真実を推測しやすくなる。その意味で、「写真」=解釈=「エクリチュール」は優れているのだ。
キタムラが見せてくれた本当の島本とのズレは、私に私が持つズレを意識させてくれ、また本当の島本、本当の故郷、本当の子供時代を想像させてくれたのかもしれない。自転車に乗って走った雄大な島本の景色の中ではなく、一軒の小さなカフェネネムのフィルム写真の中に、私は昔の私、「おもちゃちゃん」を見つけたのかもしれない。
令和5年4月19日
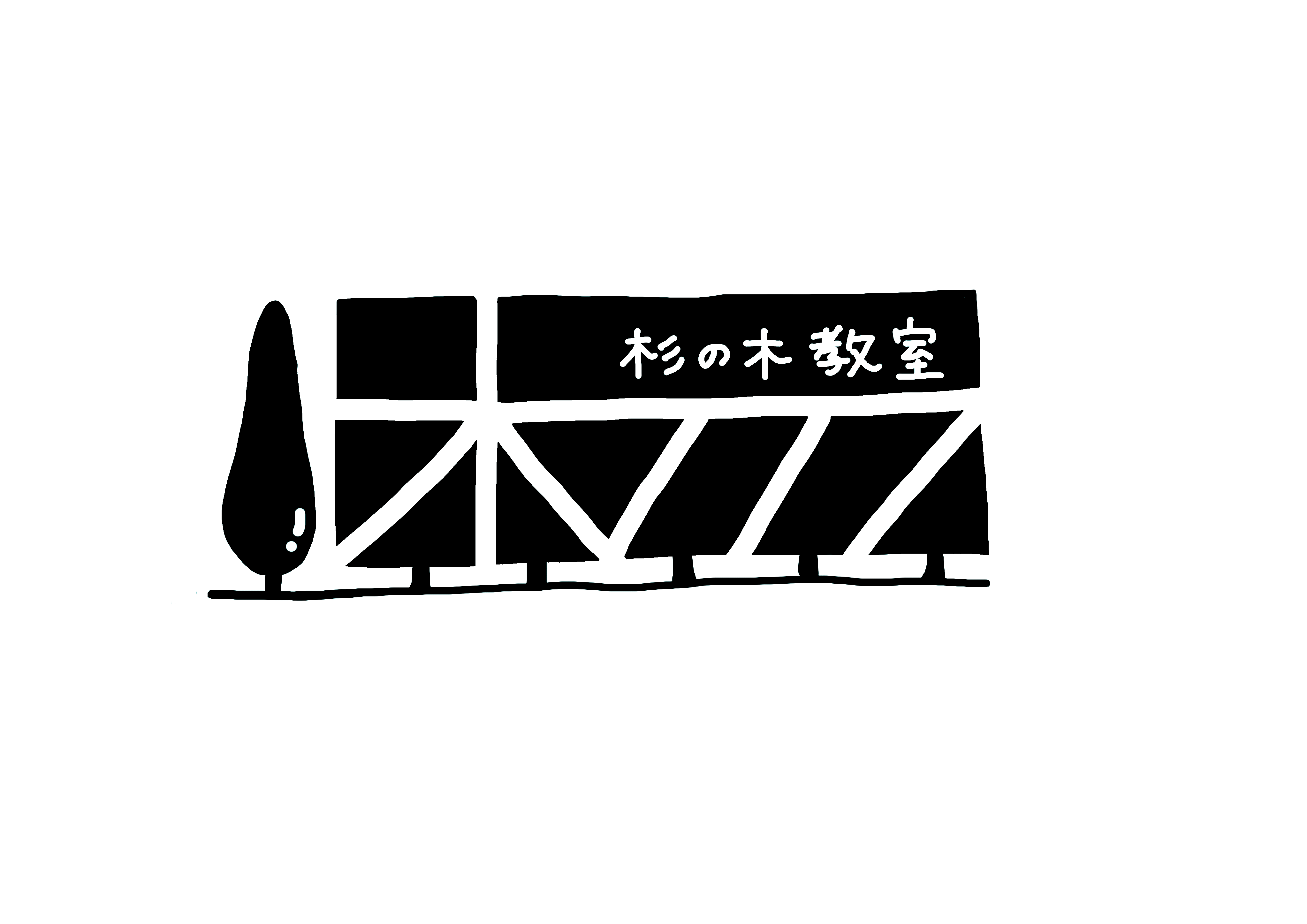
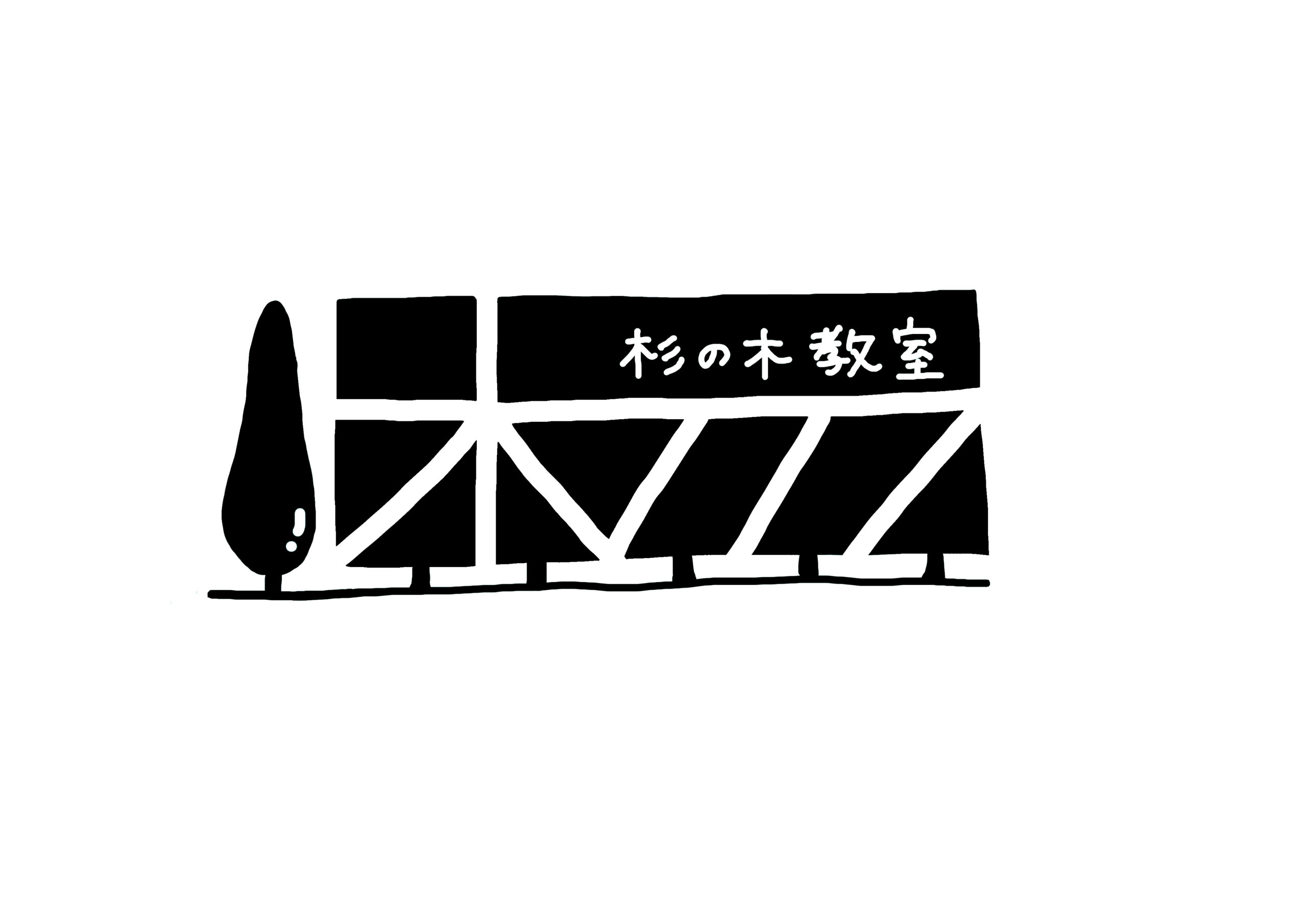

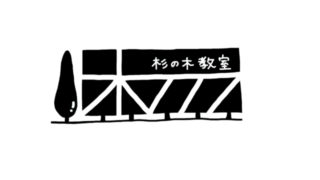
コメント