令和2年だから、ちょうどコロナ禍が始まった年だ。Kindleの端末を買って、本を読み始めた。酒を飲む代わりに本を読むことにしたのであった。以前から大酒を飲む方ではあったが、離婚がきっかけとなって毎晩浴びるように酒を飲んでいた。このままではダメだと思い、いろんなことを試していた。単純に我慢をしたり、夜に外を走ったり。一番良かったのが本であった。最初は本を読みながら酒を飲んでいたが、本の内容が全く入ってこないので、酒は本を読んだ後にするようになる。当然のことである、がしかし当時はそれがなかなかできなかった。毎晩酔い潰れるまで飲んでいたのであった。それが後になって読書の時間が長くなっていったのだった。毎晩酒ではなく言葉と乾杯をするようになったのだ。
読んだ本の中にモーニングページを紹介する本があった。創造性を高めるために毎朝起きた時に頭の中にあるものを書き記す。書き記すものがないときは「書くことがない」と書くほど、とにかく書き続けるというのがモーニングページだ。なんでもいいから言葉にすることによって、自分の中の云い知れぬ思いや行き場のない衝動に方向性をつけることができたのではないだろうか。このモーニングページを始めてからお酒を飲まなくてもよくなった。本を読む、つまり誰かの言葉よりも自分の言葉が私を変えたのであった。
酒を飲まなくなると読書量は増えた。1ヶ月に10冊ほど読むこともあった。3日に1冊のペースだから遅くはなかったと思う。そうするとモーニングページで書き出すことも増えて、翌年にはこの随筆を書くようにもなった。
本を読んでいると知識がどんどん増えていくので楽しいが、しばらくするとそれらの知識を忘れていることに気がついた。酒浸りの日々から脱出して知的な生活をしている、そんな自負があったが、せっかく得た知識をしばらくすると忘れてしまっていたのでは、また元の生活に戻ってしまうのではないかという焦りを感じた。だから忘れてしまわないように、知識を溜めて、それらを自由に取り出せるような仕組みに興味を持ち始めた。
そして出会ったのがZettelkasten(ツェッテルカステン)である。「Zettel」がメモ、「kasten」が箱を意味しており、ドイツの社会学者であるニクラス・ルーマンが編み出したとされている。例えば、いいアイデアが思いついたとする。そしたら、それをカードにメモをして箱に入れる、それがZettelkastenだ。ただそれだけである。しかしこれがとても魅力的なのであった。ノートでアイデアをまとめる際の問題点として、ノート上のアイデアや知識がばらばらに散らばってしまい、ノートを見直したときに他の関連する知識やアイデアを即座に参照することができないことが挙げられる。しかし、アイデアをカードに書き記すことによって、アイデア同士を物理的に近づけ、つなげることができる。これはあたかも脳細胞同士をつなげるような作業だ。具体的には、カードに番号をつけて、関連するカードの番号などもリンクとして書いておく。そうすると、細胞のようなアイデア1つ1つが集まって、生物のような体系を持った塊になるのだ。
このZettelkastenを作るようになってから1年7ヶ月がたとうとしている。できたアイデアのカードは390枚ほどだ。ルーマンは90,000枚以上のカードを作ったというからまだまだ少ないが、これからが楽しみである。
最近、永田希氏の「積読こそが完全な読書術である」という本を読んだ。これは現代の情報が溢れている社会を「情報の濁流」と表現をし、その濁流に飲まれないように自分だけの「ビオトープ」つまり生態系のような知識のネットワークを持つべきであるという本だ。そしてその方法として、本を読まずに積んでおく、「積読」を提唱するものである。もちろん本当に読まずに置いておくのではない。本と良い距離を保ちながら、読んだり、または積んだりしながら、自分のペースで知識のネットワークを発展させていくものである。ざっと目次だけでも読んでそこに何が書かれているのかを漠然と理解しながら、その他の本との関係を意識して、自分の蔵書全体で理解をしていくような方法とも言える。
私はたくさんの本を読むようになったが、その中には最後まで読むことができなかったものや、いつか読むであろうと思って買ったはいいが、その後全くページを開いていないものは1冊や2冊ではない。そのことになんとなく後ろめたさを感じていたので、この本の内容は私を安心させた。著者によれば、本は積んでおくだけでもいいのである。それだけでも自分の知識のネットワークの一部として働いているのだそうだ。
よく考えてみると、「積読」とZettelkastenは似ていると思った。両者ともにたくさんある知識や本の中から任意に取り出したものを自分のものとして管理し、それらをつなげたり、関係を考えながら知識のネットワークを作るのである。Zettelkastenはカードに書くので短い文章だが、本は文章の塊でとても長くて、そこには大きな違いがあるが、しかしそれをまとめて繋がりを意識するということにおいては共通する。本一冊がZettelkastenのカード一枚と考えたらいいのである。
また、どちらもたくさんの中から選び出すという点でも共通している。たくさんの知識の中から選び出してカードに書き留めておく。また「情報の濁流」つまりたくさんの本の中から自分の興味にあったものを選び出す。「自分で選び出してそれらを管理しておく」という行為に意味を見出しているのである。この行為は頭の中にあるものを全て書き出すモーニングページとも似ている。言葉にする前の頭の中は混沌としていてまさに感情や考えの「濁流」であると言ってもよい。そんな状態をなんとか言葉にして、方向をつける、扱いやすいものにする。そして自分の気持ちと現実とのバランスをとりながら創造的に生きてゆくことができるのかも知れない。
たくさん溜まったカードや本を眺めながら、それぞれのアイデアを思い出す。そうしていると今まで気づかなかったつながりや可能性を発見する。しかしこれを実行するにはしっかりとカードや本を管理しておかないといけない。たとえば本当に本を「積読」したまま何年も経ってしまってその存在を忘れていたのでは意味がない。また新しいカードを作ったり本を買うことに夢中になって、溜まったそれらを省みることがなければ、ネットワークは構築されない。
そこでもう一冊の永田希氏の「再読だけが創造的な読書術である」を手に取った。積んでおくだけで良いと言った著者が、一度構築したネットワークを日々変化する社会や自分に合わせて更新していくことを提唱している。現代社会という「情報の濁流」から本を選び自分だけの「ビオトープ」つまり生態系を構築するという「積読」を発展させて、「テラフォーミング」するために「再読」を提案している。「テラフォーミング」とは、たとえば火星などの地球外の惑星を入植可能とするために、テラ(地球)のように環境改変をすることを指すそうだ。要するにネットワークを構築したままでは少しずつ自分の感覚とずれてくるので、手入れをして自分の思い通りにするということだ。その方法として「再読」をあげている。
単純だが本質的だと感じたのでいくつかの本を再読してみた。三島由紀夫「潮騒」や、川端康成の「雪国」、外山滋比古の「思考の整理学」。忘れているところと覚えているところのコントラストが面白く、頭の中で繋がりができてくるのが心地よかった。例えば、外山滋比古の「異本論」とジャック・デリダの「差延」が結びついた。
「異本論」とは、同じ作品でも異なるテキストが存在することを前提として、そのテキスト間の差異を分析することで、作品の成立過程や作者の意図などを明らかにしようとするものだ。そして、ある古典作品が古典になった「過程」を排除し、その「源泉」だけを遡るいわば源泉至上主義を批判した。
「差延」とは、「語でも概念でもない」とされるデリダの造語で、同定や自己同一性が成り立つためには、必ずそれ自身との完全な一致からのズレや違い、逸脱など、常に既にそれに先立っている他者との関係が必要であることを示す方法だ。つまり、「私」を認識しそれを言葉にしたものは、今の「私」とは一致しない。なぜなら、まず言葉であるということ、さらには認識されたものは『「私」を認識した私』を含んではおらず、差異がある。そして「私」に影響を与えるものも変化しているからだ。全ての認識は差異や遅延を含んでいるのである。
この2つに共通するのは、差異や遅延を重視することと、テキストや記号には根源的な直接性や同一性がなく、他者や他のテキストとの関係によって意味が形成されるとすることや、音声や原本という概念に対して批判的であり、文字や痕跡という概念を重視することだ。この2つについては、また別のところで詳しく述べたいと思うが、Zettelkastenや「積読」との結びつきにも気づいたので、その点だけ述べておく。
「異本論」に、「文学作品は物体ではない。現象である」という言葉がある。これは原本だけがその作品の価値を決めるのではなく、書き写された写本や読者のさまざまな解釈、他の本との関係によって決まるという意味だ。印刷の技術がない頃には、書物は全て書き写されていた。そこには当然写し間違えや意図された改変などが加えられた「異本」が存在した。価値があるとされているのは、作者の意図がそのまま表現されている原本であるとされるのが一般であるが、よく考えてみると、それらの「異本」も作品に別の価値を与えている。また、読者の解釈もさまざまで、古典と言われるような書物には解釈本もたくさん出版されている。これもまた「異本」のようなもので、作品に別の価値を加える。さらには、のちに同じような内容で、その書物を凌駕する内容の書物が書かれた場合、元の書物の価値は激減するであろう。すなわち、書物は固定化された価値をもったものではなく、その価値や内容も時代や地域によって変化していくということだ。
「差延」においても、「指示される概念が、それ自身のうちに、つまり、ただ自己自身にのみに送り返されるような充足した現前性の中に現前することはけっしてありません」と述べられている。つまり概念は、別の概念へと送り返される、すなわち関係するからこそ意味を持つものであり、それ自体で孤立、自足、充実した概念は存在しないということだ。さらにこれらの関係は「天空から降ってきたもの」ではなく、「徹頭徹尾歴史的」に産出されたものであるとし、言葉のようにはじまりがあるのではなくどこまでも地続きな無際限な変容の過程があるだけだとしている。すなわち、概念は互いに関係し合いながら、いつまでも変化していくことが述べられている。
この2つを踏まえてZettelkastenや「積読」をみた時、これらも物体ではなく現象である。1枚1枚のカードや本が、それ自身において孤立、自足、充実することはない。選んだ知識のカードや本は集められた時点だけが価値のあるものではなく、その後に「再読」されるなど管理され関係を変えていくことによって、より価値のあるものとして変容していき、完成することはない。物体ではなく現象であるから常に動き変化するのである。まさに「ビオトープ」、生態系である。
このようにZettelkastenと「積読」や「再読」は似ているが、違った部分もある。特に「再読」においては、その内面化の作用が特筆するべきことであろう。Zettelkasten、「積読」は知識やアイデアの外部化や整理に役立つ。自分なりの感性で知識や本を集めていくことで、「情報の濁流」に流されない自分の考えというものを構築することができる。一方「再読」は知識やアイデアの内面化や深化に役立つ。それらを日々変化する社会や自分自身に合わせて更新してゆき、深く吸収していくことができる。この両者を組み合わせることで、より効果的な読書や学習ができることだろう。
酒を飲むことは今でも大好きだ。時々読書を我慢して酒を飲んでいる。なぜそんなに読書が好きになったのだろうか。はっきりとした理由はわからないが、書くことと関係があると思っている。和辻哲郎が「倫理学」の中で、「言い現されるべき1つのことがいくつかのことに分けられた時、そのことが『分かった』、すなわち理解せられたと言われるのである。」と述べている。自分の中にあるものは混沌としていて区別がつかない。それを言葉にすることによって分けられる、理解される。その感覚が読む時にも頭の中で起こる。自分の内側と外側でも言葉が物事を分節し、つまり1つのことをいくつかのことに分け、文章になることによって意味を生み出す、分離されたことを結合するのだ。また井筒俊彦は「意味の深みへ」で、「我々の内面外面に広がる全存在世界そのものがコトバの存在喚起力の産物」であるといっている。言葉には生きる力があるのかもしれない。我々の内側や外側にある世界を捉えて、理想に近づけるように構築してゆく。カードを並び替え「再読」をしながら、全存在世界をふでのまにまに飲みほそう。
令和5年7月5日
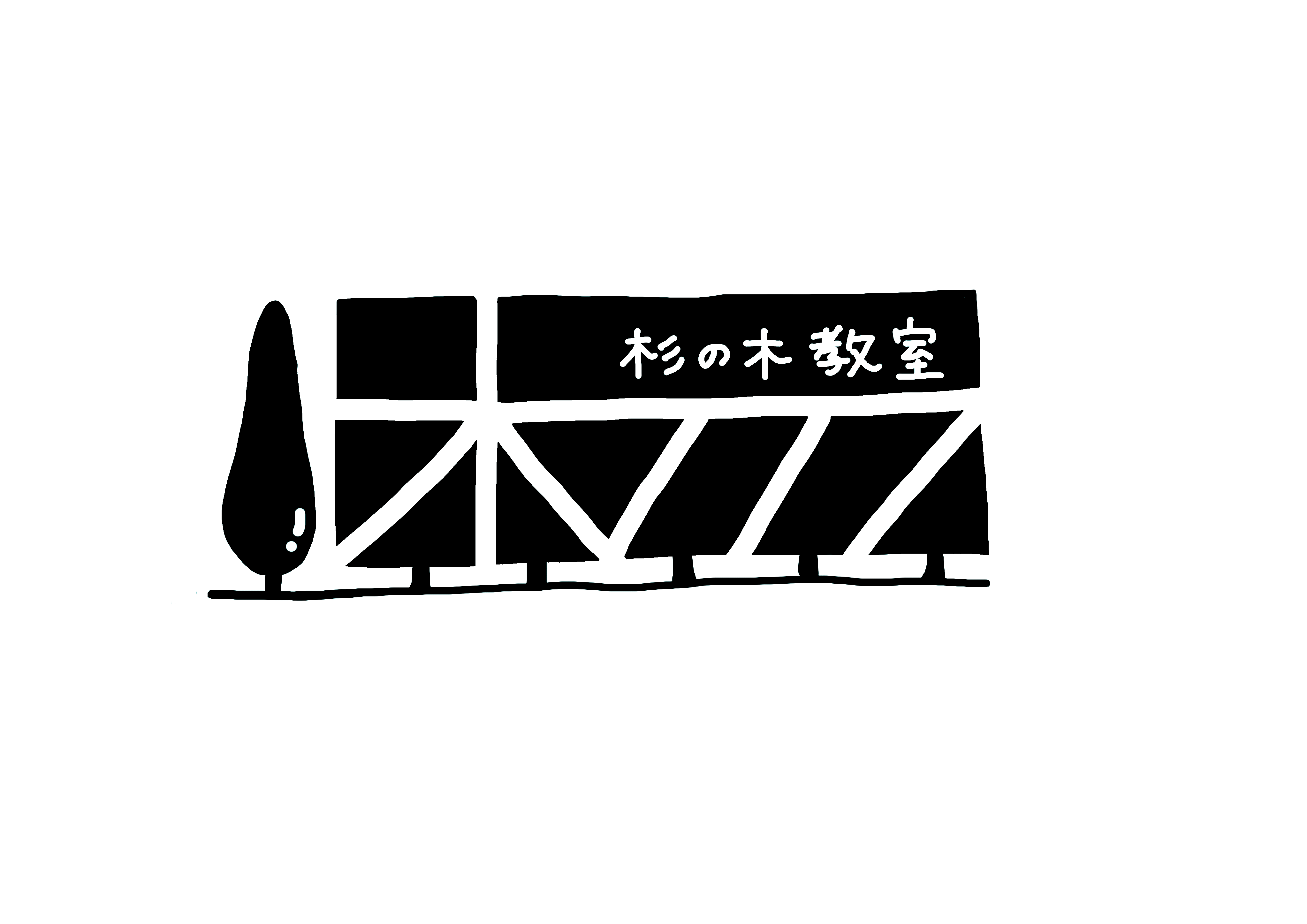
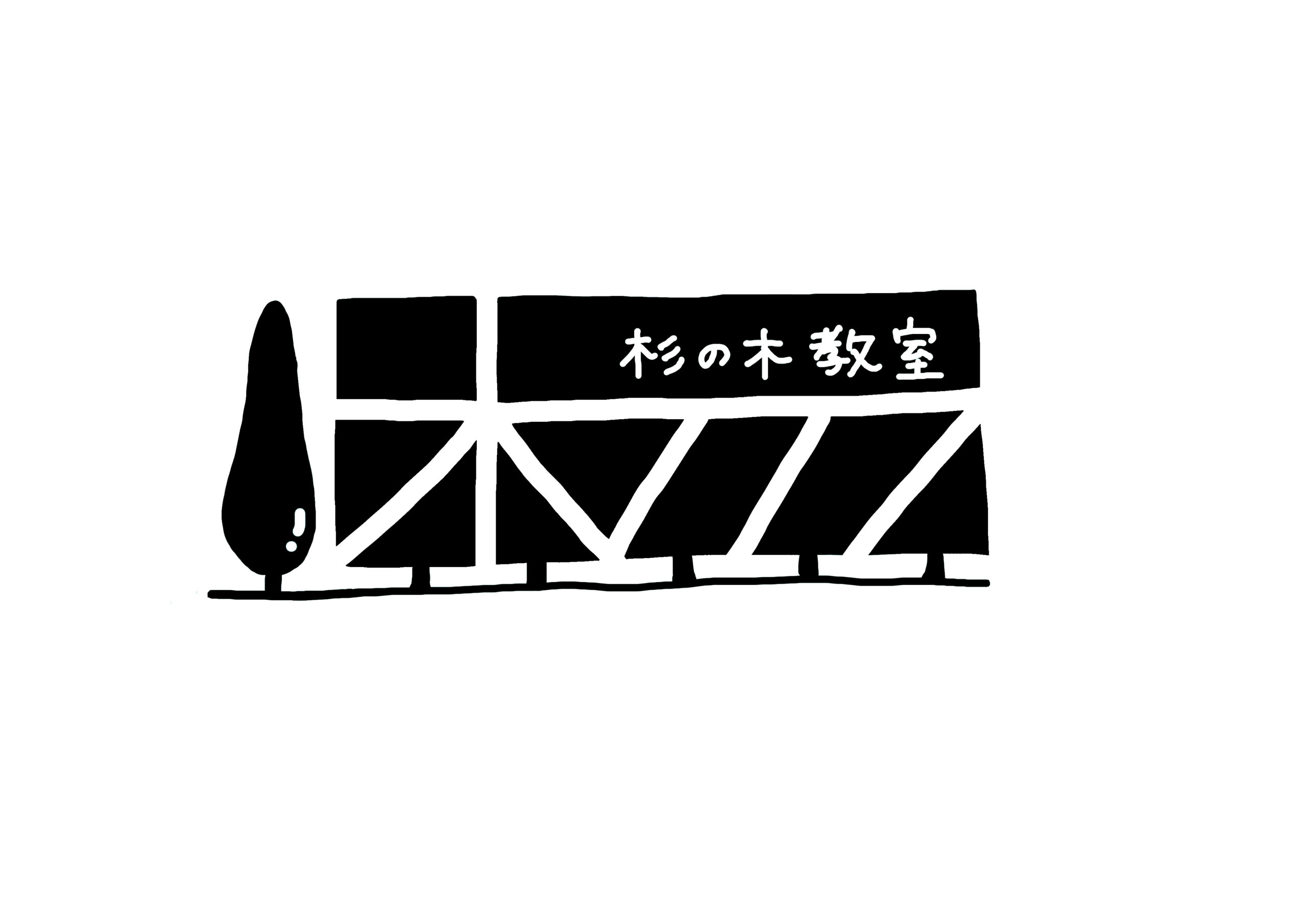
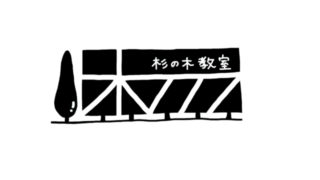

コメント