大学時代は哲学を専攻していた。ライプニッツのモナドロジー。存在論といったらいいのだろうか、この世で物はどんなふうに存在しているのかという哲学だ。一般には、人がいて、ものがある、それぞれが別々に存在している、という考えが普通だろう。
私が学んだモナドロジーは、普通とは違った世界観だ。人がいて、ものがある、それぞれがあるのは、それぞれがあるからである、というのだ。人がいるから、ものがあるし、ものがあるから人がいる。お互いがお互いの存在理由になっている。このような世界観だ。これを「共可能性」という。「共」に存在することを「可能」にしている関係という意味だ。
身近な例で言うと、10年来の夫婦。「夫は几帳面」で、「妻は大雑把」。結婚する前は、反対であった。「夫は大雑把」で、「妻は几帳面」。がしかし、夫婦生活を過ごす中で、性格が入れ替わってしまったのだ。お互いに影響しあって、性格が変わってしまった。つまり、夫は「几帳面だった妻」に影響されて几帳面になり、妻は「大雑把だった夫」に影響されて大雑把になった。よって、結婚後の2人の性格は、お互いがその原因となっている。「几帳面な夫」と「大雑把な妻」は、「共」にその存在を「可能」にしあっているのである。
学生時代は勉強などしなかったが、卒業して勉強をしなくてもよくなったら、急に勉強したくなってきた。その時に読んだもので、ナーガールジュナという仏教哲学の人がいる。ライプニッツの「共可能性」とよく似ている世界観を持っている。
ナーガールジュナは「空」と「縁起」という概念を以って存在論を説明している。「空」はよく聞く言葉で、なんとなく「空っぽ」なイメージだ。スポーツ選手などが「空」の境地に至って、ものすごく記録を伸ばした、みたいな話で出てきそうだ。雑念が消えて、集中力が増したような境地を指しているような気がする。
ナーガールジュナのいう「空」とは、確かに「空っぽ」というような意味だが、雑念がないというような意味はない。ある存在が「空」だというとき、それは存在しないという意味になる。彼曰く、全てのものは、それ自身では「空」だというのだ。つまり存在しないのだ。では、何も存在しないということかというと、そうではない。全てのものはそれ自身では「空」であるが、「縁起」しているので、存在しているそうだ。「縁起」とは何かというと、関係している、というような意味だ。お互いに関係しあっているから、それぞれは存在する。簡単に言えば、みんながいるから僕がいて、僕1人では存在できない、というような意味である。ライプニッツの「共可能性」と同じように関係し合うことで、それぞれが存在することができているという考えだ。
その後、結婚して子供を育てている間は、なかなか勉強をすることはできなかったが、離婚をして子供たちと離れて暮らすようになって、良くも悪くも私は1人の時間を持つようになり、本を読むことが増えた。でも、離婚した初めの頃は、やけになってお酒を飲むことも多かったのだが、、、
最近読んだ本の中に、これらとよく似ているものを見つけた。ホワイトヘッドという、イギリスの数学者であり、哲学者でもある男性だ。彼の場合は「抱握」という概念で世界観を表している。
私たちは、自分の位置を他の様々なものを知覚することによって、認識する。私の家は豆腐屋の右隣で、左隣には大きな欅の木がある。向かいは本屋さん。こんな感じであろうか。自分の家を認識するとき、他の家を基準に考える。もし周りに何もなければ、どのように自分の家の位置を説明すれば良いかわからない。その意味において、我々は周囲を認識することによって、また周囲に何かあることによって、存在していると言える。
そして自分の家もまた、他の家を説明する際に基準となる。豆腐屋さんは私の家の左隣であり、大きな欅は私の家の右にある。同じように本屋は私の家の向かいなのである。お互いに認識しあって、お互いに基準となり、お互いに存在させている。
さらにいうと、実際に認識しなくとも、まわりにあるものによって自分の在り方は決まっているといえる。人間は自らに働きかけているすべてのものを認識しているかと言えばそうではない。空気やその詳細な成分、引力やその他の物理的な力をすべて認識しているわけではないが、それらの存在や働きなしでは、今のような状態はあり得ない。このように認識の有無とは関係なく、自分以外の環境世界全ては、私の存在を助けていて、それらとの関係の仕方を「抱握」というのである。ホワイトヘッドによれば、この世界は、他の存在を把「握」し、「抱」え込むという、関わり合いの錯綜した世界なのである。
17世紀フランスの哲学者デカルトは、「我思う故に我あり」と言い、思考する自己を存在の始めとした。「我」が存在の基本であり、疑いようのない実在であるとしたのである。しかし、私があげた3つの世界観は、一気に全てのものが存在するようなものだ。1つが2つになり、やがて無限とも思える全体になるというものではなく、一気に全てが出来上がる。ブロックのように一つ一つに分けることはできず、全体は一つの生命体のような世界だ。そういった分けることが出来ない世界観、それらに影響を受けてきた。
新聞を読むことがマイブームであった頃から何ヶ月かがたった。ブームが絶頂を迎えていた頃には、新聞を5つも6つも買っていたものである。そしてそれらの違いを楽しんでいたのだ。世にいう陰謀論を読み聞きするようになって、新聞各社の違いを楽しんでいたが、隠蔽や暴露などという精神衛生上良くなさそうな言葉に嫌気がさして、最近では目を惹くあたりさわりのない記事を読んでいる。
そんな中で、世界の対立はグローバリズムとナショナリズムであると聞いたことがある。グローバリズムとは、地球全体を一つの共同体とみなして、世界の一体化、グローバリゼーションを進める思想である。私たちはコロナウイルスを経験し、いい意味でも悪い意味でも世界は繋がっていることを実感した。また、地球温暖化の問題は、世界が協力して取り組まなければならないものとして考えられ、SDGsなどの国際的な活動がある。「地球全体を一つの共同体とみなす」というのは、まさにこの世界を「一つの生命体」のように考えることと似ているような気がした。
一方、ナショナリズムとは、国家という統一、独立した共同体を形成する思想である。その元となるのは、一般的には自己の所属する民族である。自己の所属する民族を元として、独立した共同体を作り、良い意味でも悪い意味でも、その内部に目線が向けられているのである。こちらはグローバリズムに比べると分断された世界観のように感じる。
この2つの考えが世界を2分しているそうだ。外国からの移民を積極的に受け入れて、多様性を重んじ、経済的にも開かれた国があるかと思えば、自国の文化を守り、外国との交流や貿易を盛んに行わない国もある。グローバリズムの国は、自国の産業を守るための関税が高い国に、経済的な解放を求めたり、ナショナリズムの国は、伝統文化を守るために、外国人の永住権などを取得しにくくしていたりするそうだ。つまりは、「開かれた社会」か、「閉じた社会」かということであろう。
がしかしこの観点に立つと、結局のところ両者には差がないように思われる。というのは、ナショナリズムの歴史は浅く、国家が規模の大きなものになってからの、近代の思想だといえるからだ。
古くは、日本人という意識よりも、江戸っ子や、紀州人、などの、今でいう地方の人間であることが意識されていたと思われる。現在のように「日本人」ということが意識されるようになったのは、人々の認識する範囲が広くなったために、より大きな枠組みが必要となってきたことが契機となっているのではないだろうか。したがって、認識の範囲が広がれば、グローバリズムとナショナリズムは程度の差ということになるのではないだろうか。
例えば、昔はある地域を出ることは稀であったぐらいに、人々の行動範囲は狭かった。それゆえに、自らの所属する共同体の範囲も狭かったのである。これが、近代になり行動範囲が広く、さらには、国と国との国交というのも広がったので、地方ではなく、より大きな国家という共同体の枠組みが意識されるようになってきた。これを発展させて考えると、例えば宇宙に簡単にいくことができるようになり、他の惑星との交流や争いがあったとすると、その時今のグローバリズムはナショナリズムとなるだろう。つまり、現在は、自分が所属しているのは、あの「国」ではなく、この「国」だと思っているが、宇宙との交流の中では、自分が所属しているのは、あの「惑星」ではなく、この「惑星」だと思うことになるだろう。範囲が違うだけである。よって世界の対立は、いわゆる「開かれた」グローバリズムと「閉じた」ナショナリズムとの対立に見えるだけで、本当の対立は違うところにあるのではないかと感じた。
哲学の2大潮流として、イギリス経験論と大陸(フランス)合理主義がある。簡単に説明すると、イギリス経験論は、信用できるのは感覚であると考え、実験・観察から真理を導く哲学であり、大陸(フランス)合理主義は、信用できるのは理性であると考え、数学的論理によって真理を導く哲学である。
現在の対立の根本は、この2つのイデオロギーの対立と考えられないだろうか。言い換えると先人たちの知恵を活かし徐々に改良を加えていく経験論と、理想を掲げ論理によって改革を進める合理主義と言えるだろうか。一般には合理主義は過去のものである。カントによって「人間理性の限界」が示され、以降哲学は、「世界はいかに成り立っているのか」という問いよりも、「世界をどう生きるのか」という問いに変わったはずであった。合理主義は空理空論となったはずである。人間の経験は人それぞれではあるが、経験の受け取りかたには人類共通の一定の形式があり、その共通の形式に基づく範囲であるならば、普遍的な真理、学問を打ち立てることは可能である。しかし、それはあくまで人間にとっての真理である。とうてい人間には、本当の普遍の真理を得ることはできない、このように考えられてきたはずであった。しかし現在、私はこの認識が弱まっていると感じている。「科学による認識が万能である」との考えが、現実と認識との差異を大きくしているように思う。この「科学万能」の考えが、大陸(フランス)合理主義の傾向を強めているのではないだろうか。
科学による認識は、現実に比べると、どうしても抽象にならざるを得ない。自然を分析するためには、その複雑さから離れなければならないからだ。範囲を限定し、特定の視点から抽象化する必要がある。「1本の樹」や「1匹の昆虫」あるいは、「一つの細胞」といったかたちで、単純にしなければならない。いり乱れているから特定できないはずの部分を、無理やり切りとらなければならないのだ。よって科学はこの世界の部分であり、全体にはなり得ない。関係性の存在論の視点から見ると、科学は多くの関係を断ち切って、事物を捉えている。こういった科学が万能であることはないだろう。一時的にはうまくいったとしても、その未来にはまた別の関係が認識されて、その方法論を改めなければならなくなるのだ。現実と抽象の間の差異を意識しないこと。つまり抽象を具象だと間違えてしまうこと。このことにより、現実と認識との間に齟齬が生まれて、過ちを犯す。これが問題なのだと思う。
現在の風潮を正確にいうと「科学万能」という観念ではなく、自説の絶対的な価値を疑わない、そんな姿勢が強くなっているのかもしれない。これは、インターネットで自説と同じものを集めることが容易になったことに影響を受けているかもしれない。また、映像などの刺激の強い情報を個人が容易に作ることができるようになり、同類の情報が氾濫し、自説をより強く固定化しているのかもしれない。個人を尊重する開かれた情報社会のはずが、より刺激の強い情報源により、意見を皆とおんなじにされてしまうという全体主義になっているのは皮肉なことである。先人の知恵を活かして、改良を加えて、みんなで協力して時代を切り開いていくというのが、理想であると思っているのだが。
「開かれている」か「閉じられている」かの問題ではなく、現実と自分達の認識の間にズレがあることを改めて意識する必要がある。このズレを意識しているか、していないか、それが対立の中の中心に横たわっているのではないか。今はまだ証明はできていない。
ズレということでいうと、現実と報道とのズレも意識されるべきであろう。こちらのズレは意図的であまり気分の良いものではない。報道は文章や映像などの媒体を使うので、現実という具体的なものに比べると抽象にならざるを得ないのは、科学と同様である。それに合わせて、報道機関というのは企業であり、利潤を求めている。よってグローバル経済の中で株主の意向がその報道の内容に影響をしているようだ。報道が抽象にならざるを得ないという科学の限界面だけでなく、誰かの意思であり、扇動が現実と報道の間のズレを大きくしている。私は誰かに騙されて生きていきたくはない。
なかなか大きな問題で私には手に負えない気がするが、楽しく美しい世界を作ろうと思う。それには何が必要だろうか。どうすれば、争いのない世界ができるだろうか。「ふでのまにまに」考えてみる。
令和4年4月25日
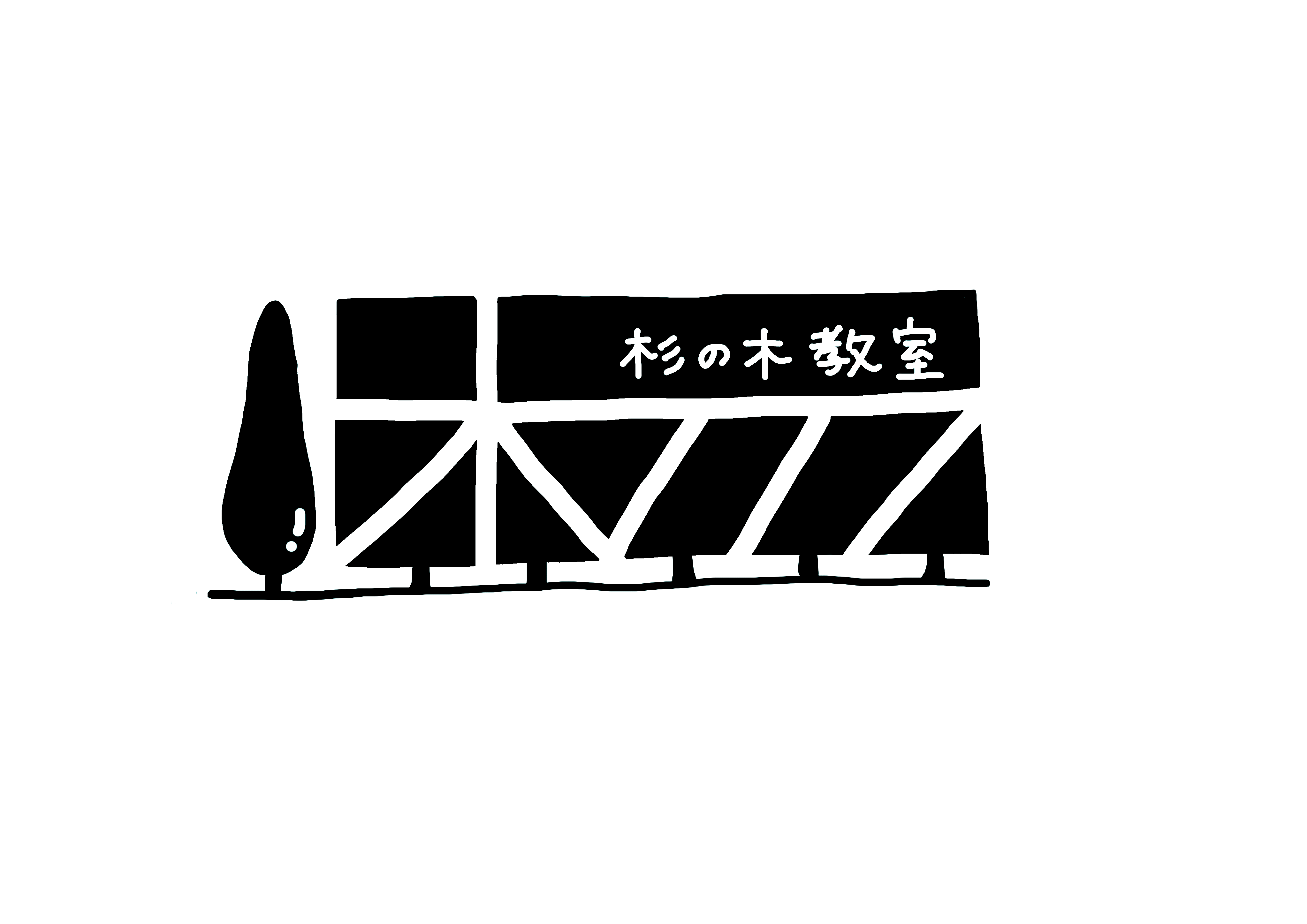
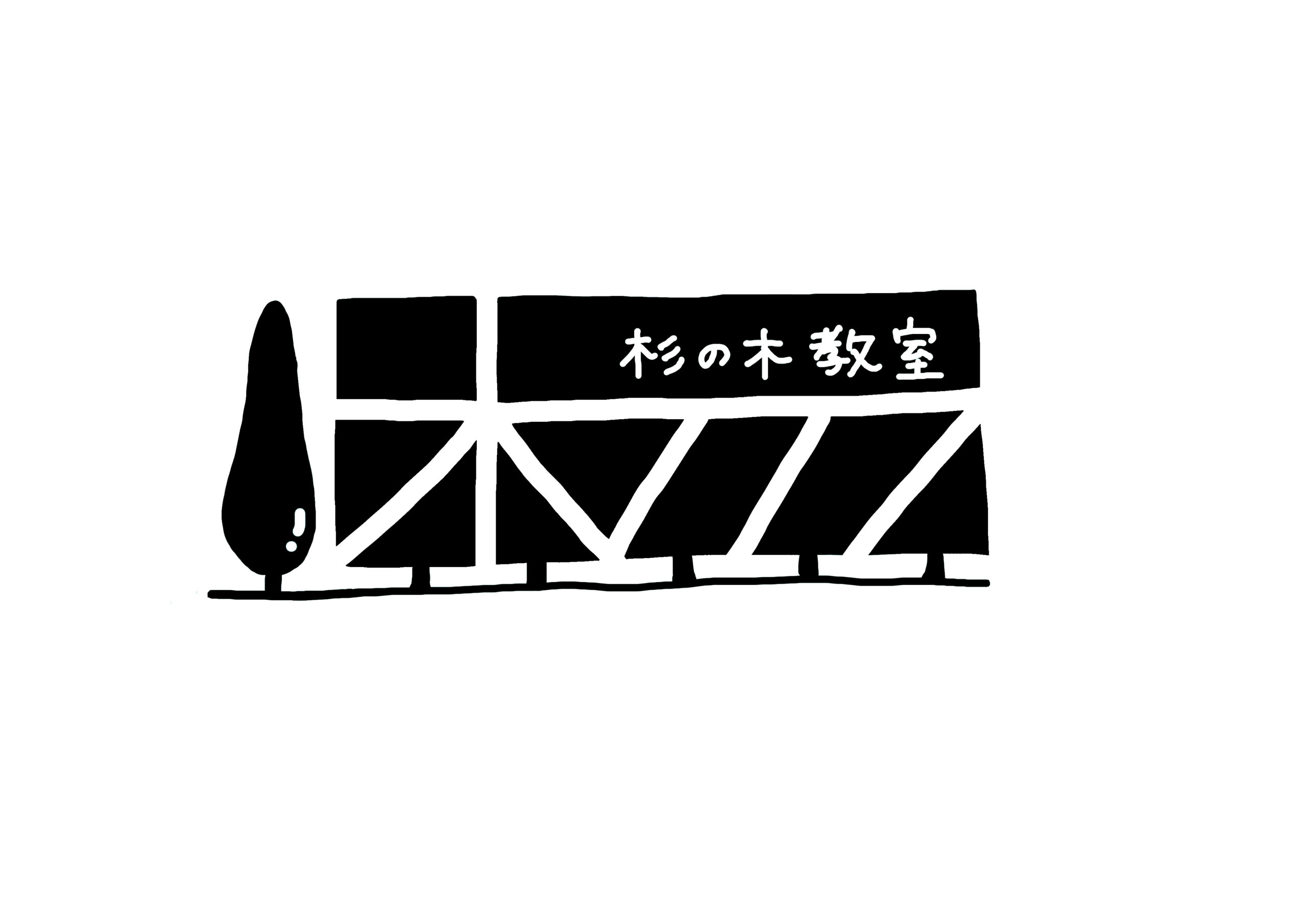
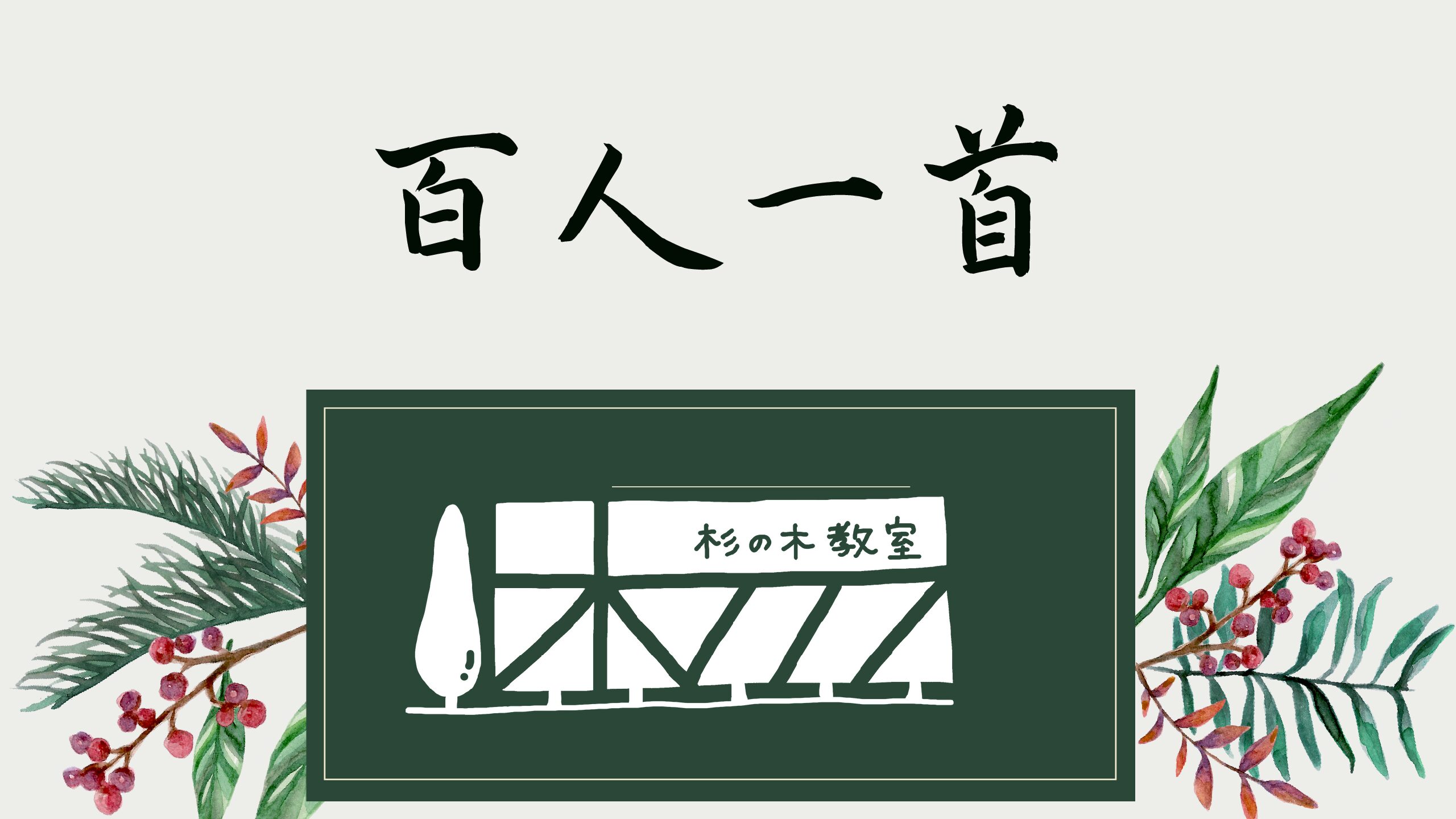

コメント