多言語への憧れから「哲学史」をいろんな言語で読んでみようとした。「哲学史」というある程度知っている内容を読むことで、言語理解へのハードルを少しでも下げようとしたのだ。日本語で理解し、それぞれの言語の表現を見ながら、それらの違いを楽しもうとした。しかし同じ著者の「哲学史」をさまざまな言語に翻訳したものを手に入れることができず、別々の著者のもので、英語、ドイツ語、フランス語で書かれたものを手に入れてみた。できれば内容が同じものの方が楽だが、それができなかったのであった。英語なら調べながらなんとか読めるが、ドイツ語、フランス語となると難しいし、楽しくなかった。今更ながら無謀な挑戦であったことを痛感したのだ。さまざまな本を元の言語で読めたらかっこいい、なんてことは軽々しく言うものではない。しかし諦めるのも嫌なので、まずは英語とドイツ語で読み始めている。少しでもいいので毎日読むことにしている。目標はホワイトヘッドやカントなどの著作をそれぞれの言語で読むことだ。
そんな中、古本屋で伊藤邦武『物語 哲学の歴史』という本を買った。これは哲学史を一つの「物語」として語るというものである。歴史上の哲学者や学説を時代順に並べただけでは、「物語」にはならない。「物語」としての哲学史を書こうとすると、なんらかの主題を必要とする。そこで古代から21世紀の現代への哲学の流れを、「魂の哲学」から「意識の哲学」、「言語の哲学」を経て「生命の哲学」への展開として書いたものだ。詳しい内容は割愛するが、このように歴史を「物語」という形式、すなわち、ある主題を持って語る方法は、現在のみならず古くから用いられているものである。YouTubeで人気を得た、高校世界史の教師である山﨑圭一『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書』においても、年号を使わずに全てを数珠つなぎにして「1つのストーリー」として解説している。また、多くの歴史の解説書にも大きな流れを掴むことが肝要であることが書かれているのである。
「哲学史」についても、さまざまな哲学者がある主題を持ってそれぞれ語っている。ヘーゲルは、哲学の歴史は「自由という理念」に向かって進んでいるとし、シュペングラーは、春夏秋冬のような周期をそこに見出し、現代は冬、すなわち「没落」へと向かっているとした。またトインビーは、周期は一つではなく幾つもの周期が多元的に重なり合って、「無数の渦巻き」があるとし、ローティは、人間の知識に関して確実で疑いのない基礎を哲学的議論によって提供することはできないという、知識に関する「半基礎付け主義」をとり、現代は「哲学の終わり」の時代であるとした。
このように長い歴史を一つの「物語」とすることで捉えやすくなるし、次の展開を予想することもできるようになる。物事を俯瞰して見ることは有益であり、頭の中のものを言語化することが大好きな私としては、快感でもある。曖昧で把握しにくいことを可視化し、整理整頓することは気持ちがいいものだ。
歴史を一つの物語と考えるというこの方法は、最近の私の流行りである「分節」と言う言葉で説明すると次のようになる。まず複雑な生の歴史を一つ一つの出来事に分けてゆき、「これ」と「あれ」を区別する、すなわち「分節」する。そして、分節されたものを俯瞰し、何か共通点がないかを探す。見つけた共通点で分類し、再構成してゆく。この再構成されたものが、歴史、そして物語である。分けたものの共通点を見つけ出すこと、また分類分けすることで、再構成が可能となるのだ。
和辻哲郎は『倫理学』の中で、「言い現わさるべき一つのことがいくつかのことに分けられた時、そのことが『分かった』、すなわち理解せられたと言われるのである。」と述べ、理解することと物事を細かく分けてゆくことの関係を説明している。つまりは分けることによって理解できるということである。物事を分ける、すなわち「分節」することは、理解することなのである。さらに「だから分かるとともに、その分けられたものが『である』によって結合せられる。(中略)しからば陳述とは、統一・分離・結合の連関において人間存在の自覚を現わしたものである。」と述べ、分けたものを再び結び合わせることで、一つの意味を完成させるというようなことを言っている。
ここで「陳述」と言われていることは、私たちの文脈で言うと物語である。さらに「統一」は複雑な生の歴史であり、「分離」は分けること、つまり分節であり、「結合」は再構成することである。ここにはカント以降の認識論が見て取れる。人間が認識することのできない物自体の世界は、「統一」であり、人間が「これ」と「あれ」を区別する前のつながった連続の世界である。それゆえに認識できないが、宇宙の原理によって「統一」されているのである。次にそれらを「分離」する。つまり「これ」と「あれ」に名前をつけて区別する、分節するのだ。そして「である」で結び、「結合」されることによって、意味を持つ世界が始まるのだ。カントの用語で言うと「感性の先天的形式を通して外から与えられた物が、悟性の先天的形式よって総合的に構成されたもの」である。
このように見てみると「哲学史」とは、哲学することであるとも言える。生の歴史を分節し、分節したものを分類して再構成して捉え、全体としての意味を考える。従来の捉え方を疑い、新たな側面から捉え直し、そこにまだ見たことのない意味の世界を与える。歴史であるとともに認識論的存在論でもある。
そんなことを改めて感じながら、哲学史を読んでいったのである。哲学史の初めは古代ギリシャだ。紀元前8世紀ごろからの神話をもとに、人間と自然との関係、人生観や世界観を思索している。ホメロスの「イリアス」、「オデュッセイア」、ヘシオドスの「神統記」などがその代表だ。紀元前6世紀頃には、「万物の根源は水である」と主張したタレスが現れ、自然や宇宙の成立、事物の根源を探究する自然哲学が生まれた。その後、民主政治は堕落し、人々の心から道徳性や個人の尊厳は失われた。そのような危機的な状況にあって、ソクラテスは「徳とは何か」、「善く生きることとは何か」を問うたのであった。
そのソクラテスについてはわからないことが多いようだが、紀元前470年頃アテネに生まれたと言われている。そのころはアテネ民主政の全盛期であったが、その後ペロポネソス戦争でスパルタに敗れ、政治的、経済的に衰退し、精神的にも退廃へと向かう時代であったそうだ。そんな中、ソクラテスは人々との対話を通じて真実を追い求め、魂や死などについても思索を深め、ただ生きるのではなく「善く生きる」ことを実践した。彼は1冊も著作を残してはいないが、その思想は弟子のプラトンや友人のクセノフォンなどの同時代の文筆家の著作を通して知ることができる。その中でも弟子のプラトンの前期の著作にソクラテスの思想は多く伝えられているようだ。
これは哲学史の初めの初めであるが、ここで積読していた本を思い出してしまった。当初の予定では哲学史を通読して、全体としての認識を深め、自分なりの哲学史を作り、述べたようにそれを自らの哲学へと発展させようとしつつ、語学の勉強をしようと思っていたのだが、初めの初めで積読本を思い出し寄り道しそうになったのだ。
思い出した積読本はプラトンの『国家』という彼の主著である。1年ほど前にもプラトンについて興味を持って買ったいくつかの本のうちの1冊だ。神谷美恵子が夢中になって読んだ本として紹介していたことや、都市や国家の設計についての合理主義的で理想主義的な著作である、ルソー『社会契約論』、トマス・モア『ユートピア』、カンパネッラ『太陽の都』、エベネザー・ハワード『明日の田園都市』などのユートピア系の源泉として、プラトンの『国家』が位置付けられていることをどこかで見聞きしたことがきっかけだったと思う。神谷美恵子は著書『本、そして人』の中で『国家』について、「決して古くない」「問題意識」がそこにはあると述べていた。その問題意識を学びとるためというのが1つの目的であり、また他方では、頭の中で考えた論理による合理主義的方法ではなく、実際に起こったことから学びそれらを調整してゆく経験主義的な方法の有効性を主張するために、反対の本を読んでみようとしたのであった。いわば現代に通ずる問題とそれらを批判するために読んでいたのであった。
今回プラトンの『国家』のページをめくったのは、1つ目の目的である。2400年前の昔の書物の中ある現代の問題意識を読み取ろうとした。というのは神谷美恵子が評価しているのと同じように、他の哲学者もその古くない哲学を評価している。現代のイギリスの哲学者ホワイトヘッドは著書『過程と実在』の中で「ヨーロッパの哲学伝統の一般的で最も安全な性格づけは、それがプラトンの一連の脚注からなっているということである。私が念頭に置いているのは、学者があやふやに彼の著作から抜粋してきた思考の体系的構図のことではない。私が暗示しているのは、彼の著作の至る所に散らばっている一般的観念の豊饒さである。」と述べており、プラトンの哲学がヨーロッパの哲学の伝統の中で深く根付いていることと、それが現実の経験としても豊かであることが述べられている。ホワイトヘッドといえば、その著書が難しすぎて有名だが、私の憧れの哲学者である。その憧れの人がこのように評価し、またホワイトヘッド自身の有機体の哲学が、プラトンの哲学の当然の結果であるように述べている。そういったことが原因で結局「哲学史」を通読することから寄り道して、『国家』を手に取ったのである。
前回は批判するためにも読んでいたので少し意地悪な気持ちで読んでいたが、今回はホワイトヘッドが評価する憧れの人としてプラトンに接している。100ページほどで辞めてしまった前回とは違って、あっという間に300ページほど読むことができた。やはり意地悪な気持ちというネガティブな思いを持っていると物事は続かないのだろうか、今回はとても楽しんでいる。ここまでのところで、私が好きなところを紹介する。
最初にケパロスという老人が登場しソクラテスと話をする。その中で、老人になった時の不幸の原因が「老年」であるとする周囲の人々を批判して、もし不幸の原因が「老年」であるとするなら、老人は皆不幸であり、幸福な老人はありえないことになると言う。幸福な老人を知っているケパロスは、不幸の原因をそれぞれの「性格」であるとし、物事の考え方次第で幸不幸は決まるのではないかと主張している。これは哲学的な思索とはいえないかもしれないが、ホワイトヘッドのいう「一般観念の豊饒さ」とも思える。日常生活の中での人生観として、有益なものであろう。
次にケパロスとの会話を引き継ぐような形で息子のポレマルコスが登場する。彼と正義について対話をしてゆく。この対話の流れはプラトンの対話篇の醍醐味であろう。ソクラテスがポレマルコスに質問をし、思索がどんどんと深まってゆく。その途中で、正義が「それぞれのものの使用にあたっては無用、不用にあたっては有用なもの」という結論に達する。これは何かを使用するときにはその専門家が有用であるとの考えから、正義の人は何をするときに有用であるかとの議論を経て、お金を保管するときに有用だとポレマコスが主張する。そのときにソクラテスがその考えをまとめていった言葉で、お金を保管するときというのはお金を使わないときであるから、何かを使わないときに有用なことが正義であるとしたら、「正義は大した代物ではないね」と言う場面である。この場面が、真剣に物事に取り組んでいるうちに何かおかしなものを生み出してしまった時の滑稽さを表していて、とても好きである。
その後も正義についての議論は進んでゆき、次に登場したのがトレマコシュである。彼の主張は逆説的であった。正しい人と不正な人が同じことをした場合には、正しい人は他人のことを優先するので、不正な人よりも結果的には損をする。一方、不正な人は自分のことを優先するので得をする。その得た利益で評判が良くなることをするので、人々からは正しい人と思われるのだ。このような不正を完全な形で行った時、正義となる、という。「このように、ソクラテス、不正がひとたび充分な仕方で実現するときは、それは正義よりも強力で、自由で、権勢を持つものなのだ。」とトラシュマコスは主張するのであった。これは当時の民主政が廃退していたことを物語るものであると同時に、人気取りの勝利というような民主主義、また愚民政治に対する批判であるとも言える。
ここから「何が正義ではないのか」という議論になっていったところにアデイマントスが登場し、何が正義でないものではなく、「何が正義であるのか」を語るべきだと主張する。これは現代の政治で言うと、野党への不満であろうか。与党の政策の批判をするだけでなく、体系的な対案を主張してほしい。何が間違いであるかを語るのではなく、何が正解なのかを明確に述べるべきだという主張は、私たち個人が仕事の現場や他者との会話の中で感じることかもしれない。
そして、正義を語るにあたって、小さな文字で書かれているものよりも大きな文字で書かれているものの方がわかりやすいだろうとした上で、国家の正義を語り、その次に一個人の正義を語ろうと提案をし、理想的な正義の国家を議論し始める。ここの文字の大きさと正義の範囲の大きさを比喩的に関係させながら、プラトンが語りたかった国家について話題が進むところは、推理小説を読むような興奮を覚えたのであった。その後は、国造りや町造りのゲームを連想させるように正義の国家が形作られてゆく。その途中でかの有名なイデア論や哲人政治論が展開されるのだ。だが現在はまだそこまで読んでいないので、以後は別の機会に書くとしよう。
多言語を習得しようと「哲学史」を手に取ったが、最初の最初で寄り道をしてしまう。しかしプラトンの『国家』の英語版も手に入れたので、多言語は実現されるかもしれない。だがそうなるとさらに「哲学史」を通読して認識を新たにして、そこから自分の哲学を刷新するということまでの道のりは長くなったような気がする。しかしこの寄り道は、プラトンという歴史を通じて今もなお問題とされている根源的な道かもしれない。最終的には自分の哲学の一部となり重要な役割を果たすことを祈りながら、筆のまにまに歩みを進めてゆこう。
令和5年10月13日
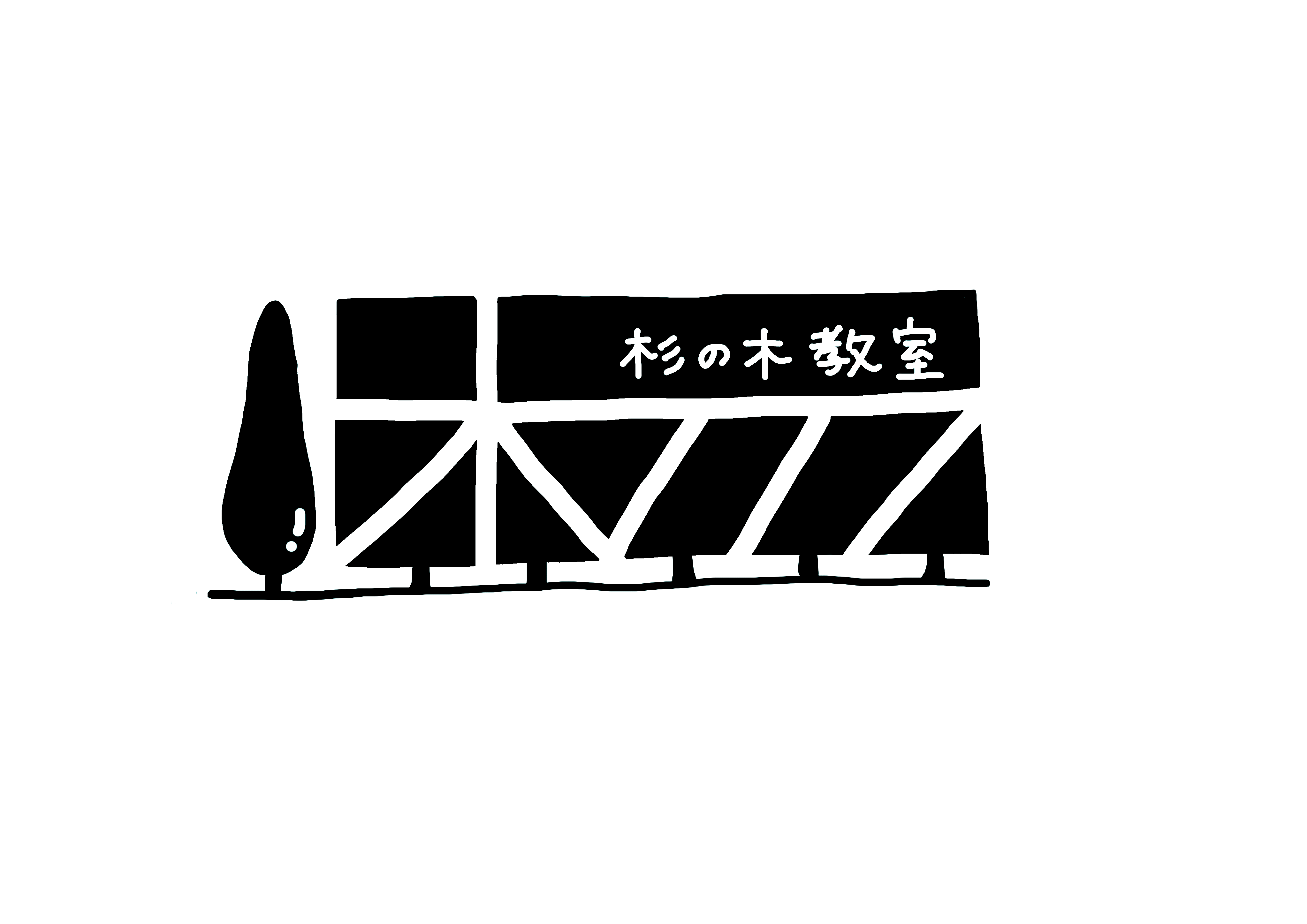
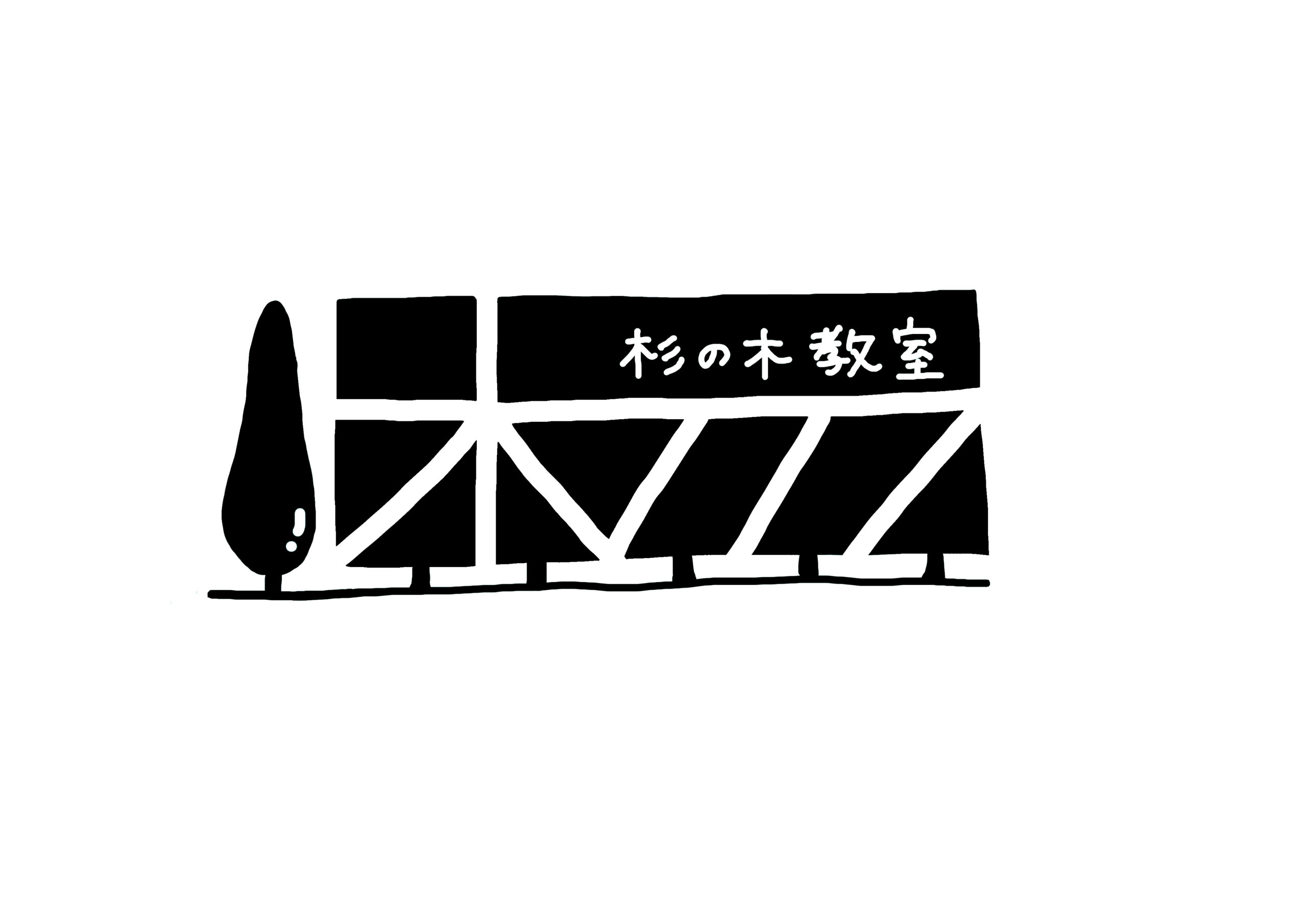


コメント