古文作文に興味を惹かれている。きっかけがあって、検索したら「古文作文」という言葉があることを初めて知った。英作文というのはよく聞くが、古文作文というのはあまり聞いたことがない。受験勉強でもすることはないと思う。しかし、英作文をすると英語を深く理解することができるように、古文で作文すると古文を深く理解できるのではないかと思っている。
学生の頃は古文がすごく苦手であった。覚えているのは、「あり・おり・はべり・いまそかり」や「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみにうかぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世のなかにある人と棲と、又かくの如し。」ぐらいで、あとは全部忘れてしまった。ちなみに「あり・おり・はべり・いまそかり」はラ行変格活用の動詞を覚えるための語呂合わせである。古文にはそんな語呂合わせがたくさんあるが、まったく覚える気にならなかった。そもそも古い日本の話よりも、アメリカで流行っている音楽の方に興味があり、それらの歌詞を理解するために英語ばかり勉強していた。
現代文も苦手で、つまりは日本ぽいものに対する興味がなかったのだ。日本のものといえば、古くて暗くてつまらない、アメリカのものは、便利でおしゃれで優れている、そんな価値観の中で育ったような気がする。英語や西洋哲学に憧れを持っていたのもそのせいであろう。音楽も洋楽ばかりを聴き、サックスを吹いていた。
大学は哲学科に入って西洋哲学を専攻した。まったく勉強していなかったが、何となく西洋の考え方というもののイメージをつかむことができた。卒業してからの方がよく本を読むようになり、ひょんなことから神社でバイトすることとなったのをきっかけに、西洋哲学よりも日本の思想の方が面白いと思い始めたのだった。そのころからの私の認識では、西洋は「分ける原理」であり、東洋は「包む原理」である。この「包む原理」が必要とされ、その力は日本の宗教の中にあると思っていた。だから神主になったのだ。
聖徳太子の言葉にこんなのがある。「神道は道の根本、天地と共に起こり、以て人の始道を説く。儒教は道の枝葉、生黎(人民)と共に起り以て人の中道を説く。仏道は道の華実、人智熟して後に起り、以て人の終道を説く。強いて之を好み之を悪むは是れ私情なり」。神道、儒教、仏教それぞれに役割を与えている。何が正しいかではなく、それぞれの長所を見出そうとする考え方が魅力的である。有名な「和を以て貴しとなす」もそうだが、うまいこと言うものである。一度に10人の話を聞くことができたというような逸話が残っているが、これは10人の話を同時に聞き取る能力があったわけではなく、神道、儒教、仏教の特性を活かして一つにまとめたように、10人の話のいいところをまとめて、全体として均整の取れたものとすることができたということだと思う。この「包み込む力」がとても魅力的なのである。
また鈴木大拙も『日本的霊性』の中で、日本の霊性が浄土真宗と禅の思想において開花したと述べているが、その実態は「一方においては漢民族の実証的論理性を取り入れたが、それにもまして南方系のインド民族的直覚性とも言うべきものを、禅のうちに看取した」と表現している。つまり高度な分節を行う文化的方法を取り入れつつも、無分節の直感性も取り入れたということである。浄土真宗では絶対者の無縁の大悲として、また禅では「妄想することなかれ」という莫妄想の思惟分別の放棄として、日本的霊性の完成を見ている。「包み込む力」が日本の霊性、その心の特性なのではないだろうか。
ずっと日本の文化は中国のまねであり、極端な言い方をするとその劣化版であるという印象を持っていたが、鈴木大拙氏の本などを読むとどうもそうではない。確かに漢字をはじめその文化の多くを取り入れて国を発展させてきたわけであるが、人々の暮らしや倫理観はまったくもって違っており、別物と言わざるを得ない。日本は稲作を中心として形成されたムラという共同体があるが、中国には歴史的にないという。絶対的な皇帝の力によって国が形成されているのであり、日本のように小さな集団の集まりではないそうだ。また中国の天命などの天という思想は、いわゆる一神教的な特性をもち、多神教的な日本のそれとは真逆である。海に囲まれた日本は他者を大陸に求めるしかなく、その高度な文化を記号として取り入れた。しかしその記号が表す内容は、「包み込む力」を持った独自の文明なのであった。
そんな素晴らしい文化を持っている日本に興味がなかったのは、いろんな理由が考えられるだろう。単純に若くて知識がなかったから、その奥の深さに気づかなかったことも一つであろうし、また家庭の環境もその一つであろう。団塊の世代の優等生のような私の両親は、無意識に日本を蔑み、昭和21年のプレスコードに縛られたメディアや教育に煽られるままに、欧米文化の優位性や個人主義の賛美の影響を受けている。だから私も同じように育ったが、さまざまな事柄が少しずつ私のそれまでの認識を変えていったのであった。
「古文作文」と検索したきっかけはニーチェであった。ニーチェ全集の『哲学者の書』の中の『われわれの教養施設の将来について』という講義録では、若い頃のニーチェが森の中で出会った哲学者の教えが語られている。一説には、この哲学者はショーペンハウアーと言われており、物語のような文章は、のちの『ツァラトゥストラ』のようである。
その中の部分を引用する。「要するに、ギムナジウムは、これまで、真の教養が始まる一番最初の最も身近にある対象である、母国語をなおざりにしてきたのだ」。この言葉で私は、古文を勉強してこなかったことや、日本語をそっちのけにして英語に興味を示していた自分を思い出した。また「厳格で芸術的な配慮の行き届いた言語上の訓練と風習の根拠の上に初めて、わたしたちの古典作家の偉大さに対する正しい感情が、強められる」とも述べており、「ゆく河の流れは絶えずして・・・」というような古文に対して、古くて暗くてつまらないと思っていた自分の未熟な感情を再確認した。さらに「ひとは、言葉というものが如何に困難なものであるかを、自らの経験によって知らねばならない、ひとは、永い探究と努力の後に、わしらの偉大なる詩人たちが歩んだ軌道の上に到達し、その結果、如何に彼らが軽やかにまた見事にその上を歩んでいったか、そして如何にほかの者たちが無器用にあるいは気取ってその後からくっついて行っているかということを、追感しなければならないのだ。」という言葉では、この随筆を書くことの困難さとそのわりには出来上がったものの無器用さそして鼻につく気取りを思い、「ゆく河の流れは絶えずして・・・」に代表される古典的名文の軽やかさや見事さを改めて思い知ったのである。
日本語をなおざりにしてきた私は、ニーチェの言う「真の教養の始まり」を無視してきた。教養とは、「学問・知識を(一定の文化理想のもとに)しっかり身につけることによって養われる、心の豊かさ。」のことであり、聖徳太子の神道、儒教、仏教の特性をつかみ、何が正しいかではなく、それぞれの長所を見出そうとするその考え方は、まさに心の豊かさである。そしてそれは日本の霊性でもある「包み込む力」なのである。
シモーヌ・ヴェイユの『根をもつこと』という本のタイトルから、「根」というものに執着心を持った。私の「根」とは具体的に何であるか、漠然と両親から遡ってゆくと日本という国にたどり着いた。そして『国史教科書』という竹田恒泰氏の中学生の日本史の教科書を読み、他人事ではない、自分のこととしての歴史という物語に魅了された。そしてそこからさらに具体的に遡ると、古文という日本語に行き着いたのである。
改めて「古文作文」を思った時、神主である私は日常的に祝詞を読み、作っていることに気がついた。祝詞とは神前において奏上する言葉であり、一般に大和言葉で書かれている。神主は定型分的な祝詞を多く奏上するが、例年の祭りではなく祈願や神葬祭など個別な神事においては、祝詞を自ら作ることがある。私も日常的に祝詞作文をしている。すでに古文作文をしていたのだ。しかしそれでももっと「根」を求めようとしたのは、私の祝詞の深さが足りないことや、また祝詞という限られた範囲だけではなくもっと広範な内容を深く理解したいという欲求であろうか。もしくは、日々の祝詞が「根」の深みへと誘ってくれているのかもしれない。
とにかく今までとは違った刺激を求めて「古文作文」をしたいと思った。その探究の道標にしようと一冊の本を買ったのだ。出雲路修著『古文表現法講義』である。この本は、「平安時代の物語文化のなかに生きていた人々に『物語』として享受されうる言語表現を、実践する」ための講義を記したものであって、その方法は物語を古文で作ることである。著者が言うには、「平安時代の物語めいたものを作るのは、そんなにむずかしいことじゃありません。古語辞典と簡単な文法書とがあれば、だれでもすぐにできます。」とのことだったが、古文が苦手であった私には、にわかには信じられなかった。が、やってみると著者の言うとおり、思ったほど難しくはなかったのである。次に記すのは、私が初めて古文で文章を書いたものである。
「古文を以て己が想いの丈を書きつくさむとするは、初めての試みとて、難しと覚ゆれど、いざやってみれば、さほどにあらず、むしろをかしみこそ覚ゆれば、今ゆ往く先古文を以て書かんとぞ覚ゆる。」
正確とは言えないと思うが、「めいた」ものは作れたように思う。しかし、著者の本当の思いは、「めいた」ものを作ることではなく、もっとその向こうがあったのだ。
著者によると、国文学は「辞世の一首を詠むための学問」であるという。このことを説明するために、国文学と似た学問を考えてゆく。まず中世には歌学というものがあり、これは「よい歌を詠むための学問」である。また近世の儒学や国学は、「自分自身の中に思想を確立するための学問」である。そして宗教もその例に入り、まとめると「自分自身の中に思想・信仰を確立し、それを言葉で表現するための学問」ということになる。この「言葉による表現」を非日常的なものにするなら「歌」となり、「ひとつの」言葉にこだわるなら、「辞世の一首」となるそうだ。つまり、国文学とは「自分自身の中に思想・信仰を確立し、それをひとつの言葉で表すための学問」ということであろう。ここで言う「ひとつの」は、「短い」というような意味でいいと思う。物語作りは、そのトレーニングなのだそうだ。
どうも古文のような国文学は、「ひとつの」つまり短い言葉で、自らを表すことが真髄なのかもしれない。確かに日本の芸術は簡素で華美に走らないが、行間から伝わってくる豊かな味わいがあるものが多いような気がする。これが「包み込む力」や私が思う「根」とどのようにつながるのかはまだわからない。今の私は辞書を引きながら、また文法書をめくりながら、古文作文をするだけである。それが深く「根」をはり、また大きく枝を広げることにつながることを信じて。
ふでのまにまに、あり、おり、はべり、いまそかり。
令和6年8月28日
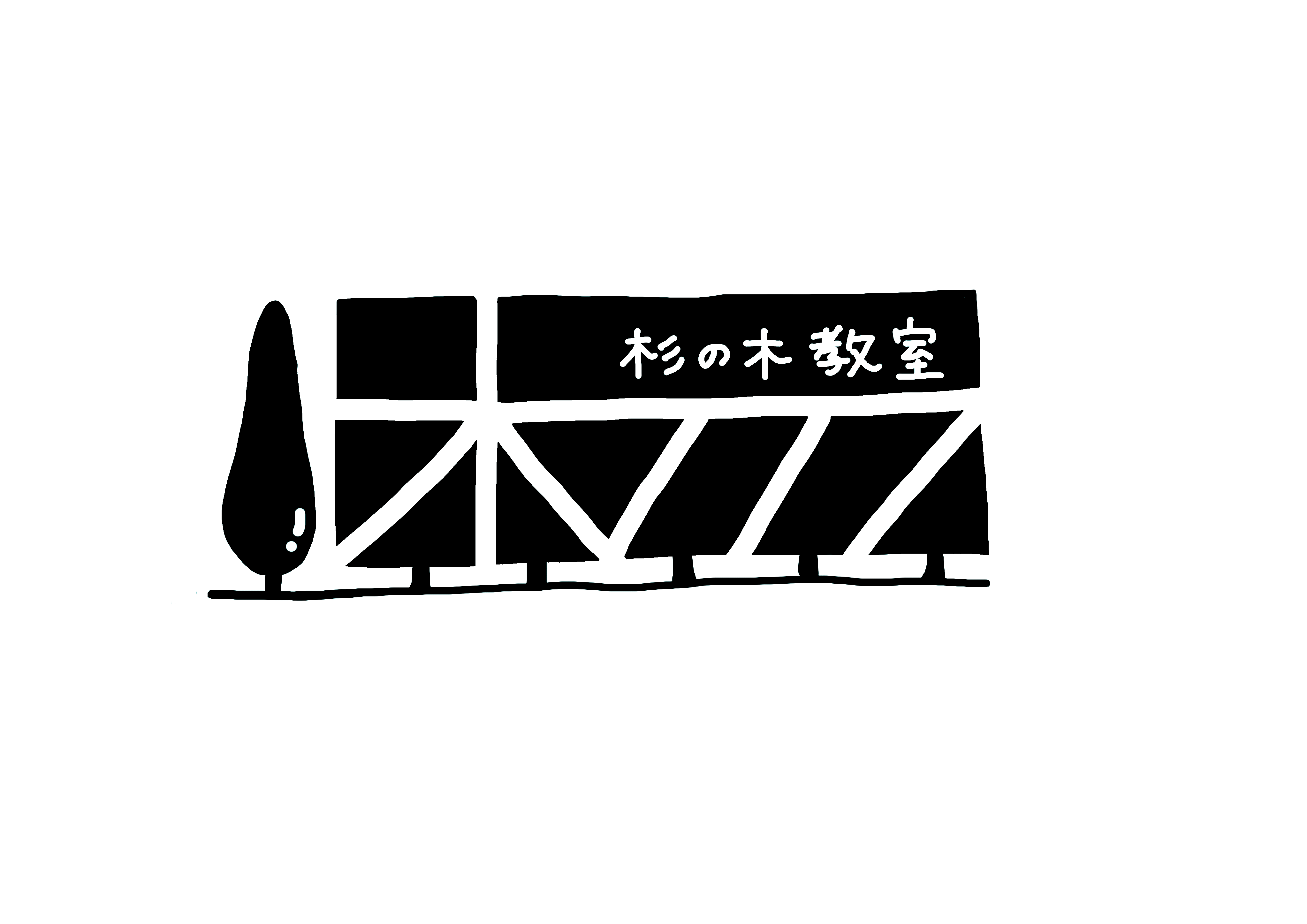
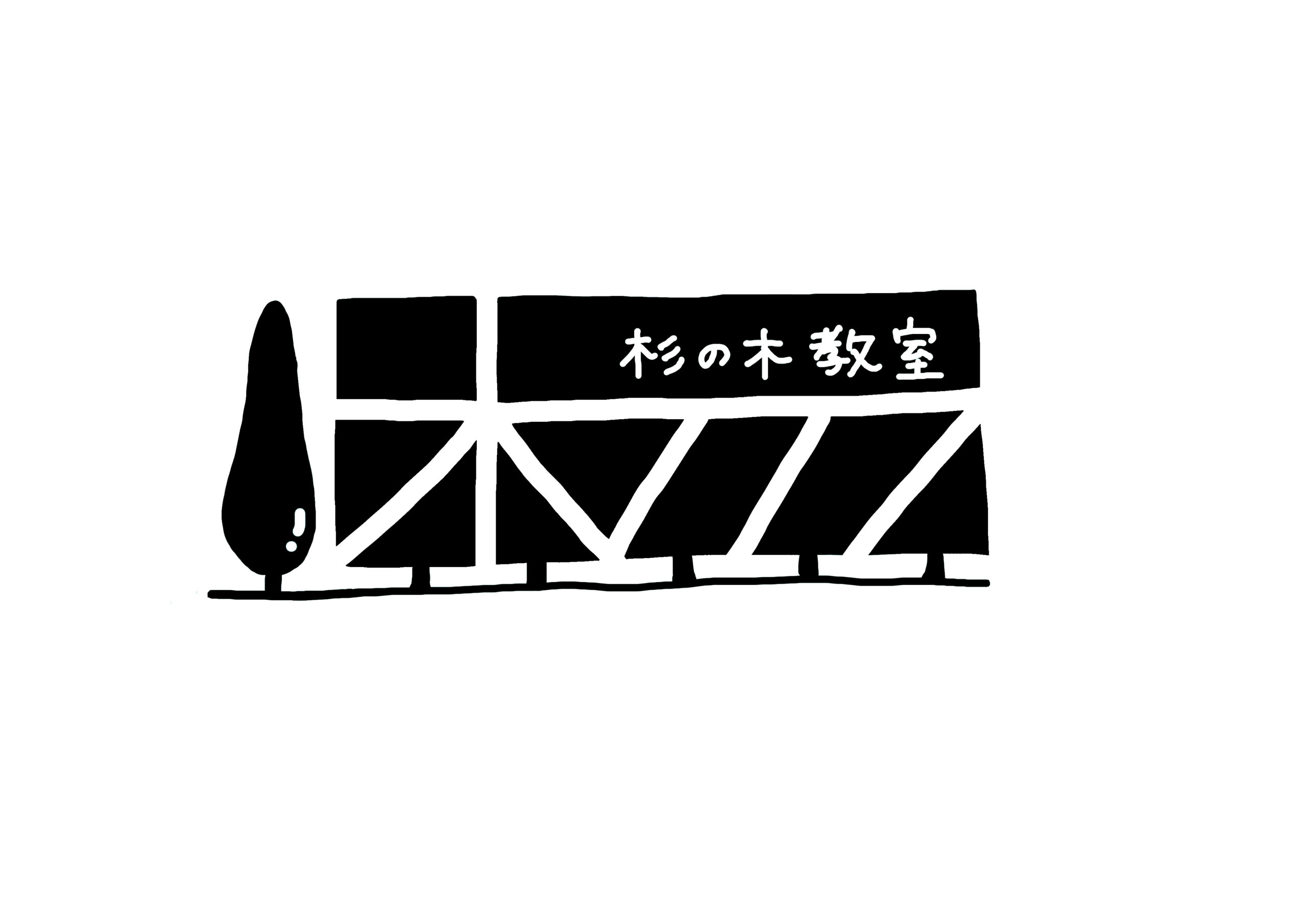
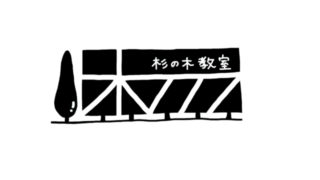
コメント