精神科医である神谷美恵子著「本、そして人」には、私にとって刺激的な本や人が紹介されている。神谷自身も優れた作家であると思うが、彼女が影響を受けた人々も魅力的で才能に溢れている。
神谷が旅のさなか船を乗り間違えてしまったほど夢中になったギリシャ哲学者プラトンの「国家」や、兄が知り合いであり後にその著作の書評を書くにいたったフランスの哲学者ミシェル・フーコーとの出会い。また、父が彼の弟子であったため幼い頃からよく神谷の自宅を訪れていた新渡戸稲造。のちに神谷が彼女の研究書を執筆したイギリスの小説家ヴァジニア・ウルフ。そしてその自宅をヴァジニアの死後に訪れたときの、夫君であるレナド・ウルフとの対話など、私には刺激的すぎる事柄が紹介されている。
その中でも、神谷が翻訳をした「自省録」の著者マルクス・アウレーリウスが好きになった。一般にはマルクス・アウレリウス・アントニヌスと言われているが、なぜ神谷がこのように表記しているのかはわからないが、ここでは、神谷の訳本に従って「アウレーリウス」とする。
彼は西暦121年に生まれ、いわゆる「五賢帝」の5人目であるローマ皇帝だ。生まれつき病弱であったため学校に通う代わりに家庭教師について勉強した。勉学と共に肉体も鍛えたようだが、もっとも心を強く惹かれたのは、哲学であったそうだ。神谷は「当時彼の周囲のローマ社会ではストア哲学がおおいにおこなわれていた。そういう外的な影響にもよるであろうが、彼の内面的な傾向にぴったりするものがあったためであろう、彼はこの学派の哲学にもっとも傾倒し、一生心の支柱となるものを見出した。」と記している。彼は、ローマ皇帝としての忙しい日々の隙間に哲学的な思索をかさね、それを書き記していた。それが神谷が翻訳をした「自省録」である。
「自省録」は、いわばメモのようなもので体系的な思想が語られたものではない。遠征の途中に思いついたことなどが書き記されている。意味の通らないようなところもあるようだ。がしかし、それゆえに彼の生きた哲学がそこには記されている。
私も「自省録」を手に取ってみた。1文目は「祖父ウェールスからは、清廉と温和。
」と書いてある。2文目は「父に関して伝え聞いたところと私の記憶からは、慎ましさと雄々しさ。」とある。2文ともおそらく、「教えられた」などを補って解釈されるべきであろう。最初にさまざまな人から教えてもらったことを書き、それに対して感謝の念を抱いているようだ。このように日常的なことも書き記されているのがこの本の魅力であろう。私は無類のメモ好きであるが、2000年近く前の人のメモを覗き見ることができるのは、大変おもしろい。
メモに感謝することがらを書き記すことは、メモ本、つまりメモを薦めている本のことであるが、それらにはよく出てくる。こうすることで、感謝する気持ちをより強く感じることができ、自分としても気持ちのいいものだし、それによって相手に対して感謝する行動をとると、相手にとっても気分のいいことだ。これをアウレーリウスもおこなっていたのである。歴史に残る、しかも「五賢帝」という特別なローマ皇帝と同じことをしていると思うとメモすることが誇らしくなってきた。
またこんなことも書いている。「念頭に浮かぶ対象についてかならず定義または描写すること。」これはメモ好きの私には好物のものである。心に浮かんだことを流してしまうのではなくて、書き記してしっかりと意識すると新しい発見があったり、具体的な行動や物を対象とすることができる。アウレーリウスは、そうすることで、「すべての付加物を取り除き、その対象だけを裸にして全体としてながめ、それが本質的にどんなものであるかを見ることが」できるとしている。定義や描写は、よく観察することにつながるだろう。佐渡島庸平著「観察力の鍛え方」では、いい観察を次のように定義している。「いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説を持ちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す。」とある。アウレーリウスの「定義」は佐渡島の「仮説」であり、「描写」は「客観的に物事を観る」と対応させると、同じようなことを言っているように思われる。対象を一旦定義してから、客観的に観て描写する。そして定義と描写の間のズレを修正することで本質に迫るのである。
そしてさらに、定義や描写をすると、「その固有の名前とそれを構成する要素、すなわちやがて分解すると再びそれに還元してしまうところの要素の名前を自分に言ってみることができる」とし、科学的な見方をしていることがわかる。物事を細かく要素に分けて考える認識は、科学的であり、別のものへと応用することができる考え方である。神谷美恵子の師である三谷隆正は、アウレーリウスが学んだストア哲学の特徴を「客観的には万有を支配する不動の理があることを確信して動かない」としている。ローマ帝国という巨大な国家には、さまざまな民族が共存し、それぞれの文化を有していた。善悪の基準も違ったことであろう。そのような中で、他民族の間に共通する不動の理を求めたのは当然のことかもしれない。
また、「ダイモーン」という言葉がよく出てくる。一般には神的な存在、すなわち神霊などを表すようであるが、アウレーリウスはこれを「人間の内部にある神的な物や場所」あるいは「理性」のことを言っているように思われる。彼は、人生が戦いや旅のやどりであり、死後の名声は忘却にすぎないというようなことを言う。まるで諸行無常の境地だと思った。その時に、導くものは「哲学」であるという。そしてそれは「内なるダイモーンを守り、これを損なわれぬように、また快楽と苦痛を統御しうるように保つこと」としている。「内なるダイモーン」を守ると表現しているところをみると、それが尊くまた壊れやすいものであるように感じる。「快楽や苦痛を統御する」と言うのは、理性を連想させる。神道では、禊祓(みそぎはらえ)を大切にする。生まれた時が一番清浄な状態であるが、日々過ごし、年をとっていくと知らず知らずのうちに罪や穢れがたまるという。それを定期的に払い清めることで、明(あか)き浄(きよ)き正しき直き誠の心を取り戻すと言われている。人間の内部にある神的なもの、内なるダイモーンが穢れてしまわないように、理性的に快楽や苦痛を統御するべきだとするアウレーリウスの考えに親近感を持った。
そして、この「ダイモーン」は、「今すぐにでもお返ししなくてはならないかのように潔く保つ」、などと表現されている。これは「ダイモーン」が、神からいただいたものであり、自分のものではない、ひいては私たちの命は私たちの命ではない、というような考えがあるように感じた。仏教でも、「この世のものの中で自分のものは一つとない、この自分の命でさえも」というような言葉があったと記憶している。また、神道では、人が死ぬことを「帰幽(きゆう)する」という。人は神々と祖先の恵によって御霊(みたま)をいただき現世(うつしよ)に生まれ生活をして、死しての後の御霊は、幽世(かくりよ)に帰り、やがて神々と祖先の御許(みもと)に帰りつくとされている。神道の「御霊」とアウレーリウスの「内なるダイモーン」はとても似ている。神からいただいたものであって、死するとそれを返すのである。
こういった神道との類似点、またメモという私との共通点を感じたため、私はアウレーリウスに親しみを感じ、好きになったのである。まだまだ熟読できていないが、長い付き合いをしていきたいと思っている。
しかしアウレーリウスの考えにはお手本があるようだ。神谷も「マルクス・アウレーリウスはエピクテートスのあまりにも忠実な弟子であって、そこには思想的になんの新しい発展もない。」と見事に言い放っている。エピクテートス?また新しい人に出会った。後期ストア哲学の代表的な存在であるようだ。そしてアウレーリウスの先生でもある。そう聞くと興味がそそられたので、アウレーリウスの「自省録」もまだ読み終わっていないが、エピクテートスが気になって本を買ってみた。ちなみに「エピクテートス」も一般には「エピクテトス」という。神谷は伸ばし棒が好きなのだろうか。
アウレーリウスの名誉のためにもひとつことわっておくと、神谷は、アウレーリウスのことを思想的には何の発展もないとしたが、ストア哲学の足りないものに、アウレーリウスが身をもってこの思想を生きることで、魅力と生命を帯びさせていると記している。例えるなら、エピクテートスの脚本をアウレーリウスが見事に演じ切ったというようなことであろうか。
エピクテートスは、西暦50年ごろに生まれており、アウレーリウスより70年ほど前の時代の人だ。かたやローマ皇帝であるが、エピクテートスは奴隷であった。主人はエパプロディトスといい、彼がエピクテートスにストア哲学を学ぶことを許し、のちに奴隷身分を解放している。教えを受けてからは、ほとんど自分で哲学の研鑽を積んだと言われている。そして哲学の学校をつくり、そこで講義をして残りの半生を過ごしたそうだ。
彼は著作を残さなかったが、弟子が彼の話を書き留めたものが残っている。その一つに「語録」というものがあり、第一章の見出しは「われわれの力の及ぶものとわれわれの力の及ばないもの」である。
能力にはたくさんの種類がある。例えば、読み書きの能力、音楽の能力。しかしこれらの能力は、たとえば友達への手紙に書く言葉について、音楽の旋律を識別することについては教えてくれるだろうが、書くべきかどうか、歌うべきかどうか、については教えてくれない。では、どんな能力が教えてくれるかというと、「理性的な能力」であるそうだ。この理性的な能力は、われわれの力が及ぶものと及ばないものを判断する。及ぶものについては、最も善いように処理し、及ばないものについては自然のままに扱うようにしなければならない、という。
これを読んだとき私は「7つの習慣」というビジネス書を思い出した。そこには、わたしたちが直面する問題として、「直接的にコントロールできる問題=自分の行動に関わる問題」「間接的にコントロールできる問題=他者の行動に関する問題」「コントロールできない問題=過去の出来事や動かせない現実」という3つをあげて、われわれが主体的に生きるために最も力を注がなければならないことが紹介されている。われわれが最も力を注がなければならないのは、自分の行動に関する問題である。他人が何をするかや過去の出来事に力を注いでみたとて、問題の解決を他者にゆだねて、自らは何もしないという態度を取ることになる。エピクテートスは、自分の行動に関する問題には最善を尽くし、他者の行動、過去の出来事などには自然に任せるがよいと言っている。
さらに「君は私の足を縛るだろう。だが、私の意志はゼウスにだって支配することはできない」とも書かれている。こちらも「7つの習慣」の中で紹介されているものに似ていると感じた。「刺激と反応の間にはスペースがある」。この言葉に「7つの習慣」の著者であるスティーブン・R・コヴィー氏は衝撃を受けたと記している。ある刺激が人に及んだ時、それに対してどのような反応を取るかどうかは、その人の意志である。例えば、罵声を浴びせられた時、傷ついたとしたなら、それはその人自身が傷つくことを選択したのであり、それがその人の意志であるというのだ。これはにわかには受け入れ難いが、傷つかないことや、どうしたのだろうと罵声を浴びせた理由を考えたり、反応はさまざまであり、どれを選択することもできる。そのように刺激と反応の間には、行動を選択するという自由があるということを述べている。エピクテートスも、もし仮に身体的には自由を奪われたとしても、その事柄をどのように解釈して、どのように反応するかの意志は、ゼウスですら支配することができないとしている。またも私の知っていることとの共通点を見つけて親しみを持ち、エピクテートスのことも好きになってしまった。
がしかし、前述の三谷隆正氏はその著書の中で、ストア哲学は個人主義であると同時に世界主義であるとしている。「個人主義に徹する時、われらは必然に個と個と各国境を超えてその価値をひとしくすることに思いを至らざるを得ない。だから個人主義と世界主義とは車の両輪の如しである。」このように述べている。この意味について、まだ深く考えることはできていないが、反射的に世界主義、つまりグローバリズムに対して嫌悪感を覚えている。それは、そんな本やツイートを読みすぎだからかもしれない。しかし、せっかく好きになったストア哲学が、今もっとも嫌いなグローバリズムの元祖ではないかと思って少しがっかりした。
神谷美恵子さんの文書を読んでいると、それらが心の最も美しいところ、尊敬や思いやり、愛情といったところから出てきているのではないかと感じる。言葉ひとつひとつに丁寧な配慮を感じるのだ。私はまだまだ学びの最中である。グローバリズムとナショナリズムの対立なんていう、最近覚えたイデオロギーの衝突に頭の中を支配されて、心を曇らせている場合ではない。アウレーリウスの言うように「内なるダイモーン」を守り、御霊を美しく祓い清め、エピクテートスの言うように、理性的な能力で何に力を注ぐべきかを考えて、神谷美恵子のように、その美しい内面からの言葉で、問題を解決するべきである。
令和4年9月13日
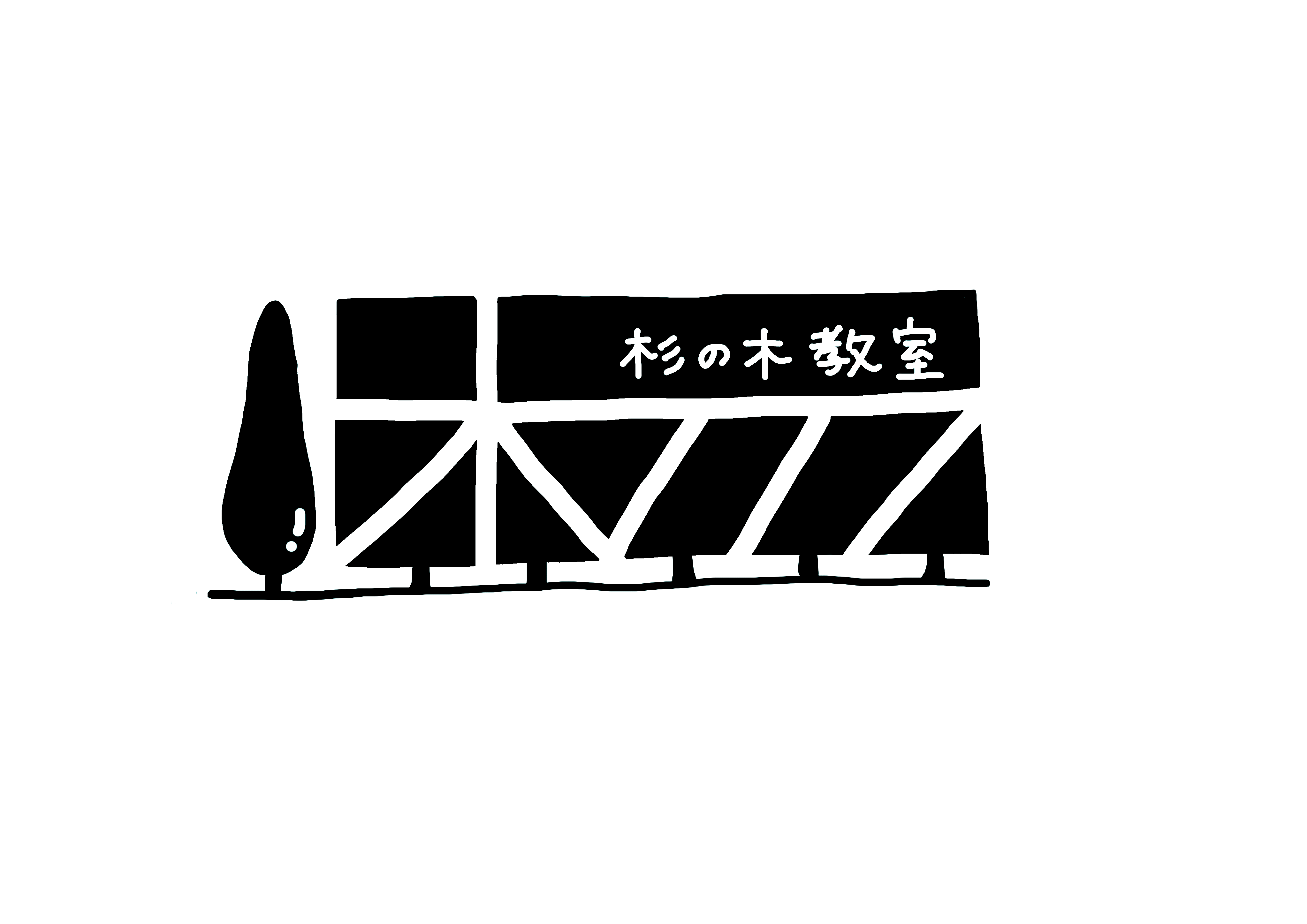
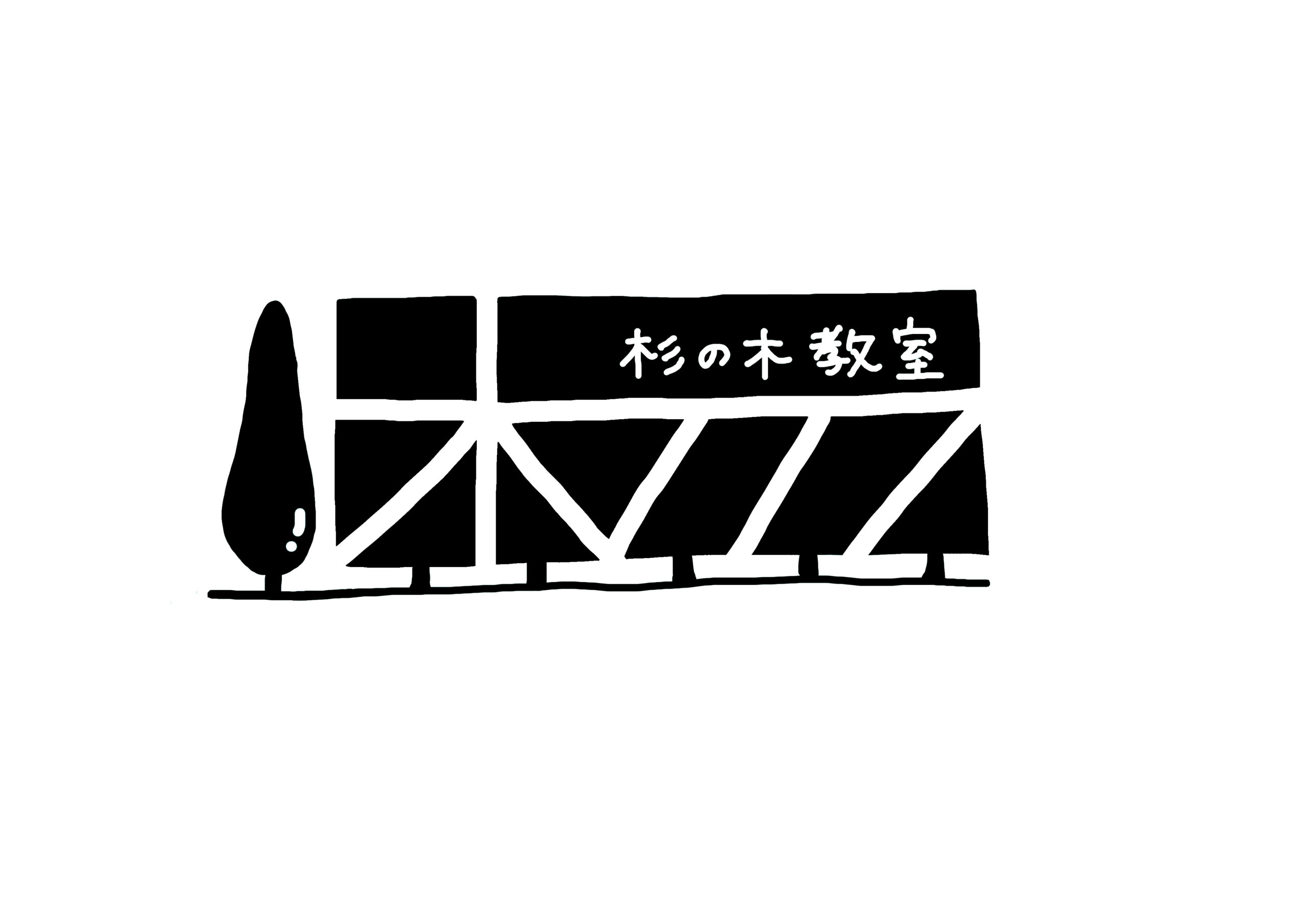


コメント