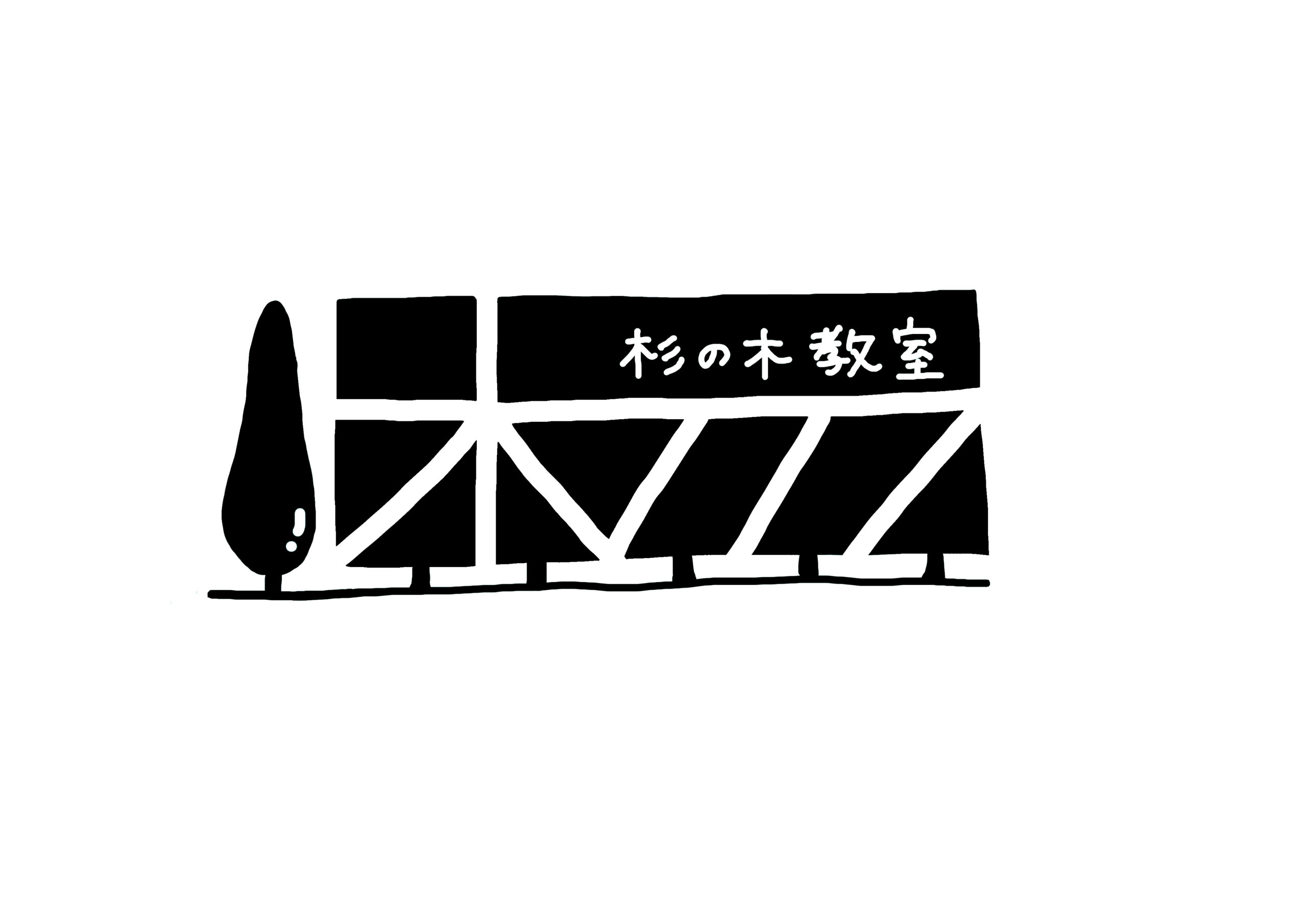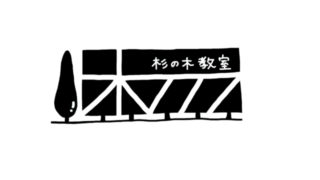仕事の忙しさにイライラしている時は買い物をすると気分が晴れる。秋の繁忙期から正月、そして節分まではとても忙しくて日々ストレスを感じていた。そんな時は書店に行ったり、またインターネットで本を買う。私の場合は本を買うことが一番のストレス解消になっている。もちろん当たり前だが読んで楽しんだり、あるいは変わった楽しみ方でいうと棚にしまってその景色を眺めたり、さらには本を知識のインデックスとして並べ替えたりすることで思索することもある。以前は植物や陶器、張子、漆器などを買うこともあったが、最近は本を買うことが一番多くなってきた。
ポール・クルーグマン、ロビン・ウェルス共著『マクロ経済学』『ミクロ経済学』を買ったのは節分の直前であった。忙しさの最盛期ではなかったが、節分の準備や正月の片付けなどに追われていた頃であった。またインフルエンザのような症状に伏しながら、這いつくばるようにして仕事をしていた頃でもあり、心身ともに限界に近かったのである。ちなみに私は病院に行かなかったのでインフルエンザかどうかは分からず仕舞いであるが、私から感染したであろう彼女はインフルエンザと診断された。ごめんなさい。
ポール・クルーグマンについては、経済学者の髙橋洋一氏の話によく出てくる人であり、ノーベル経済学賞を受賞した人であるというぐらいしか知らなかった。今でもよく知らないが、髙橋氏曰く「打てば響くような博識である」と絶賛していた。
経済学の本についてはポール・サミュエルソン『経済学』を持っていたので充分ではあったが、メルカリで第一版が安くなっていたのでクルーグマンの『マクロ経済学』『ミクロ経済学』を寝転びながらつい買ってしまったのである。あまり確かめずに買ったので送られてきた時にはその大きさに驚いた。B5版で600ページ以上もある。そんな本が2冊も送られてきたので部屋がまた少し狭くなったというと大袈裟であるが、本棚の場所を空けるのには少し苦労をした。
帯には「アカデミック・エンターテイメント」という言葉が使われている通り、とても楽しんで読むことができる本である。日常的な具体例を上げながら解説をし、要約や練習問題も充実しているので、学んだ経済学の知識をまとめたり応用したりしやすくなっている。共著者のロビン・ウェルス氏は「はしがき」の中で、「学生たちがある概念を本当に学ぶのはそれをうまく応用できたときだけだということがわかった。」と述べている。その言葉の通り、練習問題を解いていくことによって解説の意味がもっとよく理解することができた。
たとえば次のような行動が示される。「今朝あなたは次のような決定をした。地元のカフェでベーグルとコーヒーを買い、ラッシュアワーの最中に自分の車を運転して大学に向かい、あなたのほうがタイプが速いということでルームメイトの期末レポートをタイプしてあげた––––––その見返りに彼女は1ヶ月間の洗濯をする」。このような日常が示された後で「それぞれの行動で、あなた個人の選択が他の個人がした選択とどのように相互作用しているかを説明しなさい。」という問いがあるのだ。
なんてことはないが私の経験と比べるとちょっと贅沢な大学生活が示されている。そしてその光景を経済学で説明しなさいというのである。これは最初に示される経済学の9つの原理を使って説明する問題だ。
- 資源は希少だ
- 何かの本当の費用は、それを手に入れるためにあなたがあきらめなければならないもののこと。
- 「どれだけか」というのは、限界での意思決定だ。
- 人々は通常、自分の暮らしを良くする機会を見逃さない。
- 取引は利益をもたらす。
- 市場は均衡に向かう。
- 社会的目標を実現するため、資源はできるだけ効率的に用いなければならない。
- 市場は通常は効率を達成する。
- 市場が効率を達成しない場合には、政府の介入が社会的厚生を高める可能性がある。
以上が9つの原理である。この9つの原理を使って先ほどの問題を説明してみよう。
行動を順を追って見ていくと、まず「地元のカフェでベーグルとコーヒーを買った」。これは多くの中からあなたが選択した結果である。私たちは、大きな家や高級な車、最新のパソコンや家電、美しい衣服や貴重な美術品など欲しいものはたくさんある。また、3つ星のレストランや話題のテーマパーク、映画や演劇、大自然の中でのキャンプなど行きたいところもたくさんある。どんなに豊かな国であっても、それら全てを手に入れまた体験できる人はほとんどいないであろう。それは所得が足りないということが1つの原因である。家は買えても車は買えないかもしれない。以前テレビでポルシェを買うために六畳一間に住んでいる人を見たことがあるが、それは全てを手に入れることはできない現実の良い例であろう。また時間も限られている。どんなにお金をかけても1日は24時間であり、ある活動に時間を使うということは、別の活動には時間は使わないということを意味するのだ。このように人は全てではなく、いくつかを選択しなければならない。ではなぜ選択しなければならないかというと、究極の理由は資源が希少だからである。資源とは土地や労働、機械や建物など何か別のものを生産するのに使えるもののことだ。
「地元のカフェでベーグルとコーヒーを買った」というのは、1つの選択であり、その選択は資源が希少だからである。あなたはお金がなかったから街の高級なカフェではなく、地元のカフェに行ったのかもしれない。またもっと食べたかったが、時間がなかったからベーグルひとつだけにしたのかもしれない。いずれにせよこの行動は資源の希少性が生み出したものである。
また相互作用を見てゆくと、あなたがこの行動をとったことで、あなたはベーグルとコーヒーを自分で作らなくても良くなった。一方、代金をもらったカフェ側はそれで営業や生活を営んでいくことができる。ここには取引があり、取引をすることによって互いに利潤を生み出している。
次に「ラッシュアワーの最中に自分の車を運転して大学に向かった」。あなたは便利だからという理由で自分の車で大学に向かったわけであるが、このことがラッシュアワーの交通渋滞をさらにひどくしていることには気づいていないかもしれない。交通渋滞が起きているとき、1人ひとりの運転者は同じ道路にいる他のすべての運転者に費用を強いている。文字通り、互いに邪魔しあっているのだ。さらには大気の汚染やエネルギーの消費など環境に対する費用もかかっている。
これは「8、市場は通常は効率を達成する」の例外であり、「9、市場が効率を達成しない場合には、政府の介入が社会的厚生を高める可能性がある」の良い例である。通常あなたがあなたの利益を追求することは、「見えざる手」と言われる効果によって社会全体にとっても良い結果をもたらすことが多い。しかし「市場の失敗」と言われるものもあり、この「見えざる手」が働かず社会にとって良い結果を生まないこともある。その場合には政府が介入して社会的更生を高めるのが普通である。交通渋滞の場合には、公共の交通機関を整備したり、自家用車に対しての課税などが挙げられる。
次に「あなたのほうがタイプが速いということでルームメイトの期末レポートをタイプしてあげた––––––その見返りに彼女は1ヶ月間の洗濯をしてくれた」わけであるが、これについては、先ほどのカフェの利用と同じように「1、取引は利益をもたらす」で説明できる。取引の利潤で重要なものは特化という言葉である。これは個人がすべての仕事をしてしまうのではなく、分業してそれぞれの作業に特化することによって、すべての仕事をするよりも多くのものを手に入れることができるというものだ。今あなたとルームメイトの目の前にタイプと洗濯という仕事があった場合、それぞれが自分の分だけをするのではなく、役割を分担して互いに相手の分まですることによって、早く仕事が終わり、余剰の時間を持つことができるというものである。取引は互いに利潤を生み出すのだ。
このように具体的な例を用いて概念を適応していくことによって、その概念を深く理解することができる。またここに挙げたもの以外でもいわゆる経済モデルを使って説明してゆくこともできる。非常に楽しい本の内容になっている。
ある概念を具体的な事象に応用させていくことによってその概念を深く理解してゆくことができることは、経済学だけでなく哲学にも当てはまるだろう。そう考えて、そのような哲学の練習問題を掲載している本は無いかと探してみた。
スティーブン・ロー『考える力をつける哲学問題集』は、「宇宙はどこからはじまったか?」や「意識という謎」、「意味とは何か?」「タイム・トラベルは可能か?」など毎日の暮らしの中でふと気になる疑問について、哲学的歴史も踏まえつつ読者が自ら思索できるように、さまざまな工夫がなされた著作である。著者のスティーブン・ローはやさしい哲学入門書を数多く書いているイギリスの人気のある哲学者である。問題ごとに難易度が初級、中級、上級と示されており、それぞれ読み切りの内容となっているため気になる問題から読むことができる。語り口もさまざまで、対話形式のものや哲学の物語のものや思考実験が展開されているものもある。
「歯医者には患者の痛みが理解できるのか?」という章では、他人に心があることを信じない歯医者が、治療をしながら患者に語りかけてゆくという対話が繰り広げられている。人は他人の心の内側で何が起きているのか直接知ることはできない。心の内側は私秘的なものである。がしかし歯を削っているときに脳の内部をスキャンしてみれば、痛みのニューロンが燃え上がっているのがわかるだろう。このことが他人にも心があり、自分と同じように痛みの感覚があることの証拠のように見える。ところがそれでも直接の証拠とは言えない。他人の脳で、この種のニューロンが燃え上がっているからといって、意識があるとか、痛みの感覚があることの証拠にはならない。なぜなら脳の活動に心の活動が伴うのは自分だけかもしれないのだ。それは「根拠のない一般化の誤謬」を犯している。
「根拠のない一般化の誤謬」とは、例えばサクランボを10,000個集めてきて中に全部石が入っていたら、サクランボの中には石が入っていると一般化することはできるであろう。しかし1個のサクランボの中に石が入っていたからといって、すべてのサクランボの中には石が入っていると決めてしまうのは間違いである。一般化するならばもっと多くのサクランボを調べなければならない。これと同じことが心についても言える。私たちは自分に心があるというたった1つの事実を以って、他人にも心があると一般化している。確かに先のニューロンや外側から見た反応から推測すると他人にも自分と同じように心があるようには見えるが、私たちは他人の心を直接見ることはできない。さらには自分の心の外に出ることもできないのである。
このように日常的な風景に対して哲学的な考察を加えている。哲学的な問いが、果てしなく遠くにあるのではなく身近にあることに気づかせてくれ、当たり前の日常の見方を変えてくれる良いきっかけになる本である。
しかしよく考えてみると、そもそも「ある概念」とは具体的な事象から必要な要素だけを取り出したものである。多くの事象に共通に存在する事柄をまとめ上げたものなのだ。人々の経済的活動に1つずつ注目したとき浮かび上がってくる共通点。心などの目には見えないものの共通点。人間がよく犯してしまう間違いの共通点。そういったものを扱いやすく単純化したものである。よって学問的な「ある概念」が、日々の生活の中に点在しているのは当たり前である。逆に日々の生活の中にはたくさんの学問的要素が溢れているということだ。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、その著書『形而上学 上』(岩波文庫 出 隆訳28頁)の中で次のように述べている。
「けだし、驚異することによって人間は、今日でもそうであるが、あの最初の場合にもあのように、智恵を愛求し(哲学し)始めたのである。ただしその初めには、ごく身近な不思議な事柄に驚異の念をいだき、それから次第に少しずつ進んではるかに大きな事象についても疑念をいだくようになったのである。」
偉大な学問は、普段の何気ない生活の中にあるのだ。生活の中の素朴な疑問や驚きから、大きな成果を上げる学問が生まれてくる。私の哲学は私のこの生活から生まれてくるのだ。
たくさん本を買ったからであろうか、最近はイライラせずに過ごしている。神社も静かになり、忙しかった日々の片付けをゆっくりとしている。時間ができたので久しぶりに本屋に行ったりもした。忙しくても本、暇になっても本なんだなー。そういえばインフルエンザは本当に人から人へとうつっていったなー。またインフルエンザにかかっているのに病院に行かない人もいるんだなー。そんな日常に驚きながら、ふでのまにまに本を買ってしまった。
令和7年2月14日