数え年というのは、正月が来ると皆いっせいに1つ歳をとるという年齢の数え方だ。新年の1月1日がみんなの誕生日みたいなものである。だから「あけましておめでとう」なのだ。個別の誕生日を祝うのではなく、みんなでみんなを祝福する。それが日本の正月である。
わたしの仕事は神主だから、もちろん正月は忙しい。10月の後半から1月下旬の現在にいたるまで、ずっと慌ただしい日々を過ごしていた。七五三、紅葉、結婚式、年末年始、あらゆる仕事が一気に押し寄せてくるのだ。それゆえに、読書が趣味である私だが、その時間もなかなか確保できなかったのである。
今の読書傾向は哲学書だ。なんだか難しそうだが、いわゆるスルメのような書物で、噛めば噛むほど、つまり読めば読むほどにその味わいは豊かになる種類のものであると思う。本当は人気の小説や以前読んでいたビジネス書などを読まなくてはいけないと思っている。なぜならそうしないと世の中から取り残されてしまうような気がするのだ。哲学書はあまりに日常から離れていると感じる。しかしよくよく考えれば日常の根底を流れている地下水脈のようなものかもしれないが、その言葉たちは非日常的で生活の匂いがしない。だが、そこに不思議な魅力を感じて、慌ただしさのあいまにインターネットで、時間がないから読むこともできない哲学書を買ったりしていた。
家に届いたのはフッサールの『デカルト的省察』であった。フッサールといえば現象学の祖である。哲学の中に現象学という学がもうひとつあるのだ、難しそうな予感である。ちょっとした予備知識はあったが、実際に読んでみると全くわからなかった。なぜ選んだのかは忘れてしまったが、現象学を理解するとさらに面白くなるんじゃないか、スルメのいい味がするんじゃないかと期待に胸を躍らせていたので、少し落ち込んだ。自分の知識のなさや頭の悪さを恨んだが、じっとしていても仕方がないのでYouTubeで検索したのだ。
多くの入門動画を見た後、竹田青嗣さんという哲学者を知った。弟子の苫野一徳さんとの対談がYouTubeにあったのだ。そういえば私にとって哲学者といえば本の中の人たちであったので、動く哲学者は興味深く、画面にかじりつくように見た。動画は新刊本のPRのための対談イベントで、竹田青嗣さんと苫野一徳さんが本の内容や昔の思い出、これからの展望や質問に答えていた。対談はとても刺激的であった。2人の知識の深さや哲学に対する情熱が伝わってきた。本からも同じような熱を感じることはあるが、動く哲学者のそれは私にとって新鮮で、ますます哲学に対する興味をそそったのであった。
もちろん新刊本の『哲学とは何か』を買った。新刊本と言っても動画は3年前のものであったので、今では新刊本ではない。竹田青嗣さんを調べると、早稲田大学の名誉教授で哲学者であり、また文芸や音楽の評論家でもある。在日韓国人二世ともあり、偏見を持っている私は眉をしかめたが、本を読み始めるとそんな思いはあっという間に消え去った。
本の内容はいわゆる入門書であるが、専門的な用語も多く決して簡単ではない。竹田氏の観点から哲学の歴史や問題、そしてこれからのことが語られている。ここでこの「竹田氏の観点から」というのはキーワードとなる。私は現象学でこの動画を検索したのであるが、「竹田氏の観点」というのは現象学、とりわけ「竹田現象学」ともいわれる独自の観点からの哲学であった。
竹田氏は初心者にもわかりやすく丁寧な文章を書くことで有名である。本もたくさん出版されていて、影響を受けた人は多いようだ。難解なヘーゲルの『精神現象学』やカントの『純粋理性批判』の解説は高い評価を得ている。弟子の苫野一徳氏は、「先生の読みの深さに驚く」「哲学の歴史が全て整理されて頭の中に入っている」などと述べ、竹田氏の理解の深さやその見識の広さを讃えていた。そんな竹田氏の中心的な思想がいわゆる「竹田現象学」で、独自の現象学だと言われている。竹田氏本人は「これが正しいフッサールの読みである」と言っているが、一般的には異端的な読みであり、人によっては「竹田氏の現象学の本は読むな」とまで言うほどであるようだ。
「世界説明」という言葉を聞いたことはなかった。竹田氏がいう宗教と哲学の役割である。宗教は「神話という物語」で世界を説明し、哲学は「概念」と「原理」で世界を説明する。「世界」と「説明」、2つとも日常的に使う言葉だが、この2つが結びつけられるとどこか哲学的な雰囲気が漂う。私は神主であるから「宗教者」であり、趣味でこのように「哲学書」に興味を持っている。なるほど私は「世界」を「説明」したかったのかもしれない。今更ながらなぜ私がこのような仕事につき、このような趣味を持つにいたったのかを教えてもらったような気がした。日常的な言葉の組み合わせから哲学的な雰囲気を感じたことによって、私にとっての哲学の非日常性が緩み、地下水脈から湧き出た泉のような潤いが心を満たしたようだった。
現代は価値の多様性が叫ばれ、いわゆる相対主義の時代だそうだ。相対主義とは簡単にいえば、「絶対的な真理はなく、みんなそれぞれ正しい」と世界を説明する考え方だ。確かに現代には多様性を容認し、その考えを広げていこうとする風潮を感じている。相対主義の対義語は普遍主義であって「真理は1つである」という考え方だが、この現代の多様性の容認の風潮の根底には、マルクス主義という普遍主義の大失敗があるという。唯一の正しい世界観として出現したマルクス主義であったが、次第に矛盾を露呈し崩壊したとき、ポストモダン思想としての相対主義が立ち上がった。価値の多様性が重要視されるようになったのである。
みんなが違って、みんな素晴らしいというのはいいことで、理想的な雰囲気だと感じるが、喜んでばかりはいられないようだ。たとえば多様性を容認しない人間を糾弾し、必要以上に叩くような事件が起こったり、少数派を擁護するあまりに多数派の多くの人々が不便を被るなどの事態が起きている。竹田氏によると相対主義が煎じ詰められると、「力がすべてを決定する」という論理に行き着くそうだ。またドイツの哲学者ニーチェも示唆したように、最も強力なものが真理を僭称し、やがて皮肉なことに多様な価値が認められない世界となる。みんな素晴らしいと手放しで価値を認めることによって、理性ではなく、本能的な力の原理で価値が決定され、それに逆らうものは力によって消されてしまうのであろうか。そんな危惧があるからこそ竹田氏は相対主義的な現代において、哲学によって「万人が納得することのできる普遍的な真理」を打ち立てようとこの本を書いたということであった。
この考えには大変共感をした。「人それぞれだから」とか、「あなたにはあなただけの価値がある」などの言葉は、たいへん耳障りはいいがあまりに無責任であり、たとえば子供の暴走をどこまで容認するかの基準を曖昧にさせ、ゆくゆくは非常に野蛮な状態をも是とすることになるのではないかと感じている。「万人が納得することのできる普遍的な真理」をぜひ打ち立てたいと私も思うのである。
その方法として竹田氏は「現象学的還元」をあげている。「現象学的還元」とは、意識にのみ注目することである。①普通、外界に物があり、それをわれわれが知覚すると考えるが、②ここではまずわれわれの意識の中に物が現れ、だから外界に物があると考えるのである。①では、外界に物があることが「原因」となり、それをわれわれが認識することが「結果」となるが、②ではわれわれの認識が「原因」となり、外界に物があることが「結果」となる。このような世界の見方を「現象学的還元」という。
このことによって何が得られるかというと、意見の違いを克服することができるという。①では意見の違いの根を「原因」である外界の物に求めてきた。しかしこの外界の物の認識は、デカルト以降大きな問題であり、外界の物すなわち「存在」と「認識」は一致しないというのが定説である。フッサールにおいても外界の物を認識することが可能になったわけではないが、②の見方によってもう一つの世界が広がったのである。つまり、②では意見の違いの根を「原因」であるわれわれの意識の中に求めることになる。意識の中のこととなればわれわれは時間をかけさえすれば、相互に認め合い、共に納得する理解を作ることができるとするのである。真理は発見されるのではなく、共に作るという仕方で現れるというのだ。竹田氏はその真理のことを「確信」と呼び変えて、外にあるものではなく、意識の内側に生成されるものとして強調している。
ここに「竹田氏の観点」、つまり一般と違うフッサール理解があるようだ。竹田氏はわれわれの認識と外界の物という「主観―客観」の図式を完全に取り除き、主観の意識内に焦点を当てるが、一般には「客観」を「主観」の前提として、「主観」はまだ「客観」ではないという意味での「主観」としているそうだ。この違いは私がインターネットで見つけたラファ鉄さんという方の意見を参照した。ラファ鉄さんも勉強し始めた時はこの違いがわからなかったと述べていたが、今の私にもわからない。「主観」であるわれわれの認識は時が経つか、あるいは認識が進むと客観へと変わるのだろうか。
この違いは竹田氏のもう一つの方法であるニーチェの「本体論の解体」にヒントがあるのかもしれない。わからないながらも私はそう思っている。竹田氏は、認識の問題はフッサールとニーチェによってほぼ解明されていると述べている。がしかし一般にはこれが認められていないと主張しているのだ。
「本体論の解体」についてはまだはっきりと掴めていないが、竹田氏によるとカントの「物自体」の考えは、「完全な認識」があり、人間にはそれが不可能であるというものであった。しかしニーチェでは、この「完全な認識」、「物自体」もないということである。「真に存在するのは、個々の生き物にとっての『生の世界』だけ、(略)『客観的に存在する世界』とみなしていたものは、各人が『生の世界』を言葉で交換しあうことから成立する、『想定された世界』にすぎない」ということである。つまり「客観」はないのである。
このことをさまざまな生物の感覚器官の違いに由来するという、その生物の特有の世界観を例にあげていた。これはユクスキュルという生物学者の研究で、ある種のダニは成長すると木に登って適当な枝にしがみつき、下を哺乳動物が通りかかるのを何年でも待っている。うまく何かが通ると酪酸の匂いを感じてその背中に落下する。そして触覚を頼りに皮膚まで潜り込み、血を吸って卵を産む、というサイクルを繰り返す。このサイクルにおいてダニは、嗅覚、触覚、温覚という3つの感覚しか持たないが、これがダニにとっては最適であり、世界を客観的に写し取ったのではなく、世界を自分の体に相関して「分節」しているのである。「この事情は、あらゆる生き物にとって同じであることもわかるはずだ。」として、ニーチェの「本体論の解体」を解説している。
私には「物自体」の考えとどう違うのかがわからなかった。ダニは「物自体」ではなく、カントのいう「悟性」で世界を認識し生きている。生き物がその体に相関して世界を「分節」したとしても、「物自体」の世界がなくならない、「客観的な世界」の可能性がなくなることはないと思うのだ。その生物の分節の外側が「物自体」なのではないのであろうか。ここが、「主観―客観」の図式を完全に取り除くか、取り除かないかの違いであり、取り除けない私は竹田氏のいうようにまだ理解していないのかもしれない。この部分に関しては、ニーチェの『権力への意志』の「認識としての力への意志」と竹田氏の『欲望論』の第十七章〜十八章に詳しく書いてあるのでそちらを読むべきだと紹介されていた、、、ということはまた私は哲学書を買うことになるのだろうか。
正月の慌ただしさも緩んできて、読書の時間も確保できるようになってきた。『哲学とは何か』はまだ半分ぐらいしか読んでいないが、目次を見る限りニーチェの「本体論の解体」についてはもう書かれていなさそうだ。私が「竹田氏の観点」の鍵と思っている「本体論の解体」についての理解を進めるには、『権力への意志』と『欲望論』を購入するしかないだろう。また哲学書を買って、世の中から取り残されてしまうのではないかと不安にもなる。「世界説明」という言葉のように日常と哲学の世界を結んでくれる言葉はあるだろうか。さらに、読んでも理解できるとも限らない。これらの本を理解するための本をまた買わなければならないかもしれないのだ。しかし読書百遍とはよく言ったもので、何度も読んでいると自然とその意味がわかってきて、以前と比べ哲学書の理解は進んでいると思う。その先には「万人が納得することができる普遍的な真理」が待っているのだろうか。たとえば新年を迎えて皆が皆を祝福して「あけましておめでとう」と言い合えるような、そんな真理が私たちには訪れるのだろうか。ふでのまにまに注文を確定した。
令和6年1月21日
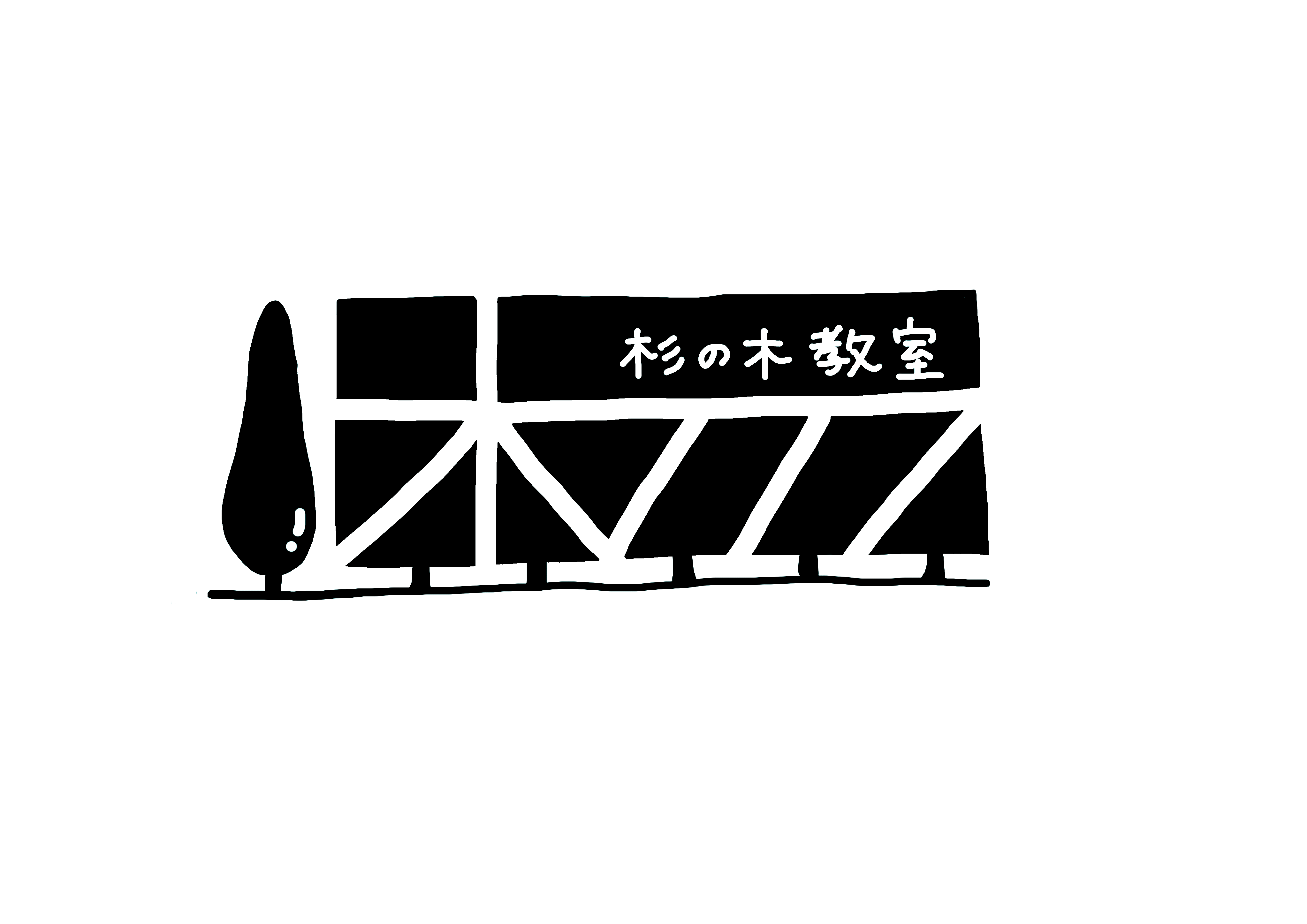
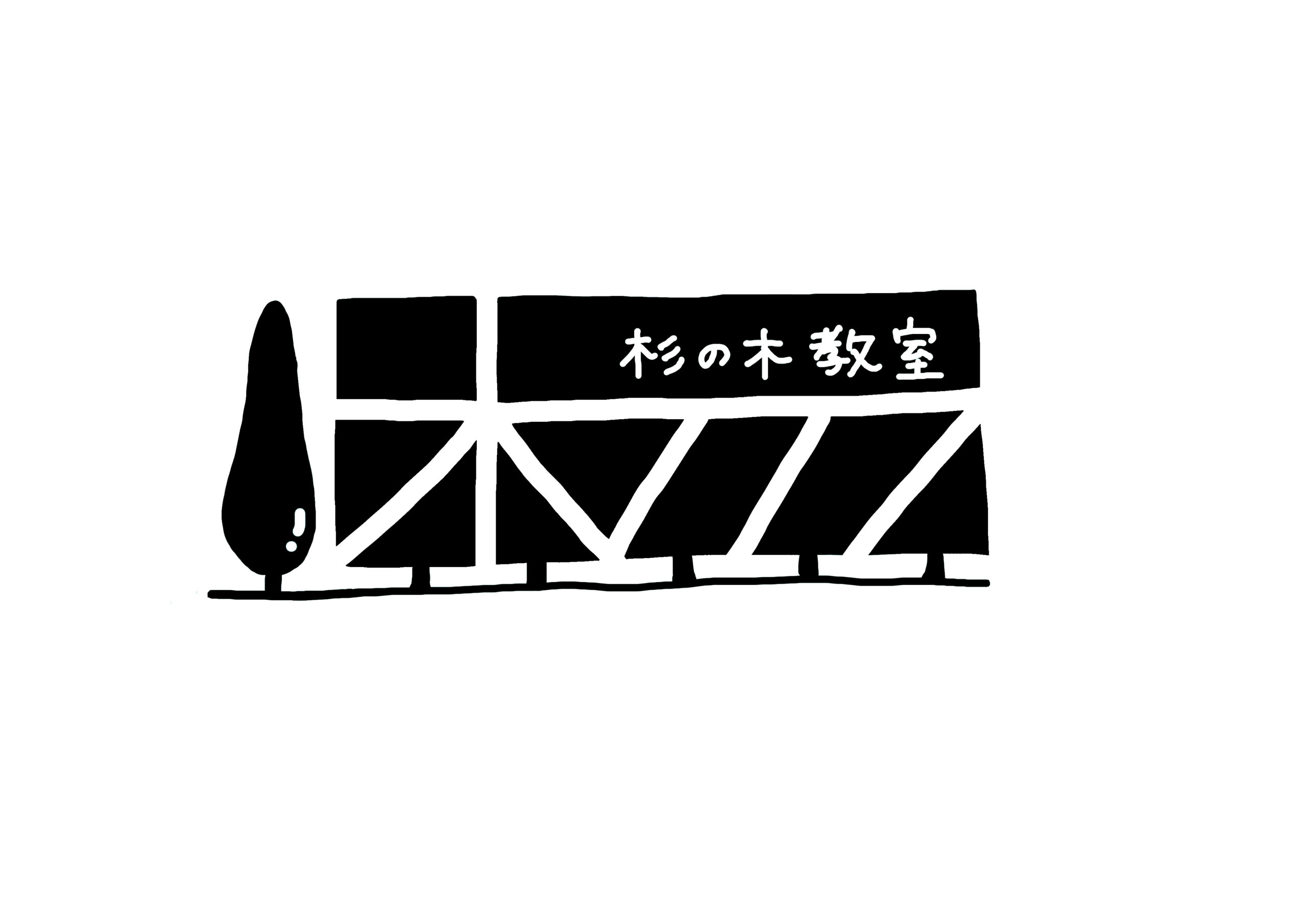
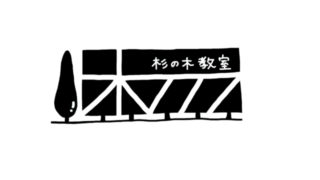

コメント