私は存在の全体像が知りたい。なぜなら全体を知らずには本当の個を知ることができないからだ。
例えば、音楽では「ミ」と「ソ」が鳴っているときと、「ファ」と「ラ」がなっているときとでは、同じ「ド」を鳴らしたとしても意味が変わる。前者は根音で主となる音であり、後者は5度の音で根音を支える音となる。つまり同じ「ド」の音でも他との関係によってその意味は変わるのだ。
また彼岸花という花がある。秋口に土手などに赤く咲き誇る美しい花だ。別名「曼珠沙華」(まんじゅしゃげ)と言って、サンスクリット語では「天上に咲く花」という意味であるという。「おめでたい事が起こる兆しに、赤い花が天からふってくる」という、仏教の経典によるものだそうだ。しかし日本の古い言い伝えでは、この花を家に持って帰ると、火事になるというのだ。土手で見た時には、天から降ってきた花だが、家の中で見ると火事をもたらす危険な花となる。このように時と場所が変われば同じ花でも意味が変わってしまう。ちなみになぜ火事になるかといえば、彼岸花には毒があり、家に持って帰ると危険であることから、これを戒めたものであるという。
さらに例を挙げると、白地に赤丸は日本の国旗になるが、緑地に赤丸はバングラディッシュの国旗になる。こちらも同様に他との関係において個の役割や意味が変わり、表すものも変化する。このように個々のものだけを見ていたのでは本当のことはわからない。他との関係、全体像を知ることによって真実が見えてくる。
私がこの随筆の中で何度も述べてきた「関係性の存在論」はその興味の結晶だ。ライプニッツがいうように、他のものと存在を可能ならしめあう「共可能性」こそがそのものの存在する理由であったり、龍樹が言うように、そのものだけでは「空」、存在しないが、「縁起」する、関係しあうことでものは存在することができるのである。そのほか「相対論」や「量子論」なども取り上げて、存在の全体像について考えを巡らせてきた。
カントの言う「物自体」は、人間ではその真の姿を知ることができない代物だ。われわれの周辺に広がる世界は、従来思われてきたように物のあるがままに現れているものではなくて、感性の先天的形式を通して外から与えられた物が、悟性の先天的形式よって総合的に構成されたものである。したがって、われわれのもっとも素朴な感覚与件でさえ、すでに空間・時間という主観の形式を経由したものであるから、われわれは感覚を刺激する外なるものをそのあるがままに認識することができない。つまり、われわれは世界をあるがままに見ているのでなく、われわれが見ることができるようにしか見ていないと言うことである。このカントの「物自体」の考えは、その他の哲学にも見ることができる。東洋哲学では「渾沌」といわれたり、「無分節者」、またはバタイユなんかは「連続」と呼んでいる。最近よく見ているYouTubeチャンネル「何か分かりづらいチャンネル」では、分かりやすく「ぐっちゃんこの世界」と言っている。
この「ぐっちゃんこの世界」を人間の仕方で分節する、つまり区切りをつけて認識しやすくするのだ。それが、カントのいう「感性の先天的形式を通して外から与えられた物(を)、悟性の先天的形式よって総合的に構成」することになる。具体的には言語を用いて区切り、関係を築いてゆく。それは便宜上であって、本当は「物自体」は一気に存在し、区別をつけることはできない。なぜなら全ては関係しあっているからだ。我々が区別できているように見ているこの世界は、本当は全て繋がっている。だから、バタイユはその世界を「連続」、人間が分節した世界を「非連続」と呼んだのだ。
このように「連続」である「物自体」を表すことはできない。しようとした瞬間に「物自体」は変化する。なぜなら「物自体」に我々も含まれていて、我々の行動が「物自体」の一部だからである。がしかし学問の営みは、この「物自体」を正確に表そうと発展してきた。相対論や量子論、哲学では構造主義などが、関係しあう流動的な事物を表してきた。気象学なども予測困難で不確定な世界を表している。カントのいう通りなら、人間は「物自体」を表すことはもちろん、認識することもできないが、以前と比べるとその複雑な体系を認識し表現できるようになったわけである。
ここで関係しあう流動的な事物を表してきた構造主義について私が知っていることをまとめておく。それは、恣意的であり、差異的であり、共時的であるということだ。恣意的というのは、その時の気ままな配置で構造が決まるということ。差異的というのは、周りとの差異、関係性でしか意味は決まらないということ。共時的というのは、事物の秩序は、ある時間で切ったところにその全体を一挙に捉えねばならないということ。これらは、事物の全体を把握する上での注意点のようなものだと思う。
例えば、箱の中でいくつかの風船を同時に膨らました時を考える。そうすると箱の中ではそれぞれの風船が接し合い、いろんな形になる。この時の構造は、全くもって気ままである、というより予測は不可能であろう。いろんな要素が重なり合ってその時の構造になると考えられる。予測が不可能なことを恣意的と表現している。そしてある風船の形は、隣の風船の形に影響される。つまり横の風船がより強く膨らんでくると、自ずとその風船の場所は狭くなり、周りとの差異、関係性によって自らの形が決まってくる。さらには、その箱の中の秩序は全体を一気に捉えなければいけない。なぜなら、ある風船が割れてしまった時、全ての風船は形や場所を変えることになるからだ。これを共時的でなければならないと表している。
このように構造主義は、私が興味を持っている「関係性の存在論」と通じるところがある。事物をそれだけで認識するのではなく、周囲との関係性の中で意味を見出し、また他と関係することによって事物は存在することができているのだ。この構造主義という事物を認識する方法論はソシュールが言語に、レヴィ・ストロースは文化全体に適用していった。このほか、文学作品、音楽、生物学とさまざまな分野でも構造主義がその方法論として使われるようになっていった。また認識できないがそこにあるかもしれないものを想定して、全体像を予測するやり方もある。その一つとして、フロイトの無意識などが挙げられる。さらには静的な構造のみによって対象を説明することに対する批判から、構造の生成過程や変動の可能性に注目する視点がその後導入され、ラカンやデリダなどのポスト構造主義というものも出現したのであった。
ここまでが今までの私の興味の範囲であった。以下は最近読んだ本、浅田彰著「構造と力」の中から、そこからさらに広がる興味を書いてみたい。
以後、カントの「物自体」の世界を「ぐっちゃんこの世界」、それに対して、人間が認識し文節化した世界を「文化の世界」と便宜上分けることにする。
私は「ぐっちゃんこの世界」を表現するために「文化の世界」のさまざまな思想を見てきたが、この二つの世界は交流があるというのだ。この交流について、ジュリア・クリステヴァ、栗本慎一郎、ジョルジュ・バタイユ、などが思想を展開しているようだが、そのほか東洋思想や坐禅や禅問答の禅の修行なども二つの世界の行き来を扱っている。
私なりに簡単に説明をすると、「ぐっちゃんこの世界」は、人間が認識する前の世界であると同時に、理想の世界であったり、動物性、死、聖なるものの世界でもある。例えばプラトンのイデア界、つまりものごとの真実やものごとの原型の世界、あるいはあの世と言われるような観念の世界がある。これらの世界は人間には知覚不可能であるが、その世界を人間は欲求しているそうだ。それをプラトンはエロスと呼び、真実を知ることへの欲求や、性的な欲求、ひいては死への欲求とも考えられている。このエロスに溺れてしまう、つまり「ぐっちゃんこの世界」を求めすぎてしまうと、われわれの現実、「文化の世界」では生きることができなくなってしまう。しかし完全に無くしてしまうことはできないと言われている。それをジュリア・クリステヴァは日常と祭りの関係になぞらえて、「抑圧と再流動化」と称し、普段は押さえつけられている「ぐっちゃんこの世界」への欲求が祭の時に噴出し、再流動化、つまり文化で固定され凝固してしまった人間の生を活気あるものにするとしている。また栗本慎一郎は、その著書「パンツをはいた猿」の中で、普段はパンツをはいていないと生活することはできないが、しかるべき時が来ると人間はパンツを脱がなくてはならないと言っている。こちらも文化的にはパンツを履くべきであるが、動物的な観点から見るとパンツを脱がなくてはならない時もあるので、「文化の世界」と「ぐっちゃんこの世界」の交流を表していると言える。また、ジョルジュ・バタイユも同じように「ぐっちゃんこの世界」と「文化の世界」との交流の反復を言っている。この二つは統合されることなく交流が反復されるがゆえに、一方に激しく振れば、もう一方に激しく振り戻されると言う。
この二つの世界の交流を担ってきたのが宗教と芸術であろう。祭りは文字通り宗教的な儀式であり、普段とは違う価値観、むしろ反対の価値観で動く。神輿を担いだり、危険な行動をとったり。普段はそんな非合理なことをたくさんの人間がすることはない。命の危険があることをあえてしても何も得られないのに、危険な行動をとることはあまりにも非合理だ。しかし、それらが世界中で長年にわたって続けられている。人間にとっては、なくてはならないもの、二つの世界の交流なのだと思う。また、理想的な美しい風景を描いたり、天国や地獄のような目には見えない世界を可視化したり、この世ならざるものを現前させて、人々に刺激を与えるのは芸術の役割だ。宗教も芸術も「文化の世界」にいながら「ぐっちゃんこの世界」を少し見せてくれ、「文化の世界」を再流動化、つまり活き活きとさせるのだと思う。
また戦争も二つの世界の交流の一つであろう。非日常的であり、そこでの行動は「文化の世界」では禁止されている。敵を倒すことが目的となる、日常ではあり得ない状況。これも「ぐっちゃんこの世界」のものであり、これらへの欲望を人間は秘めているのかもしれない。戦争も世界中で長年にわたって続けられている。人間にはなくてはならないものなのであろうか。
バタイユがいうように「ぐっちゃんこの世界」と「文化の世界」との交流は、振り子のように片方に激しく振れると、もう片方へも激しく揺れるとするならば、「文化の世界」が「ぐっちゃんこの世界」を抑え込めば押さえ込むほど、その反動は強くなるのだろう。現代の振り子はどの位置にあるのだろうか。
押さえ込まれた「ぐっちゃんこの世界」を見ることが必要なのであれば、宗教や芸術が力を発揮すると、戦争は無くなるのかもしれない。戦争が起こる理由がこのようなものであったなら、私にも力になれることがあるだろう。日々祈り、楽を奏でる、見たことのない「ぐっちゃんこの世界」を現前させてみせよう。
「関係性の存在論」を中心としている私の思考に、新しく添えられた二つの世界の交流という花は、天上に咲くように美しくもあり、また火事を起こし毒を持つように危険でもある。この花も他の事物と同様に他と関係し合いながら存在している。全体の中でこれらがどのような役割を果たし、どのように世界に影響を与えていけばいいのかが少し見えたような気がした。美しくて危険なこの花を見事に咲かせたいものだ。
令和5年7月30日
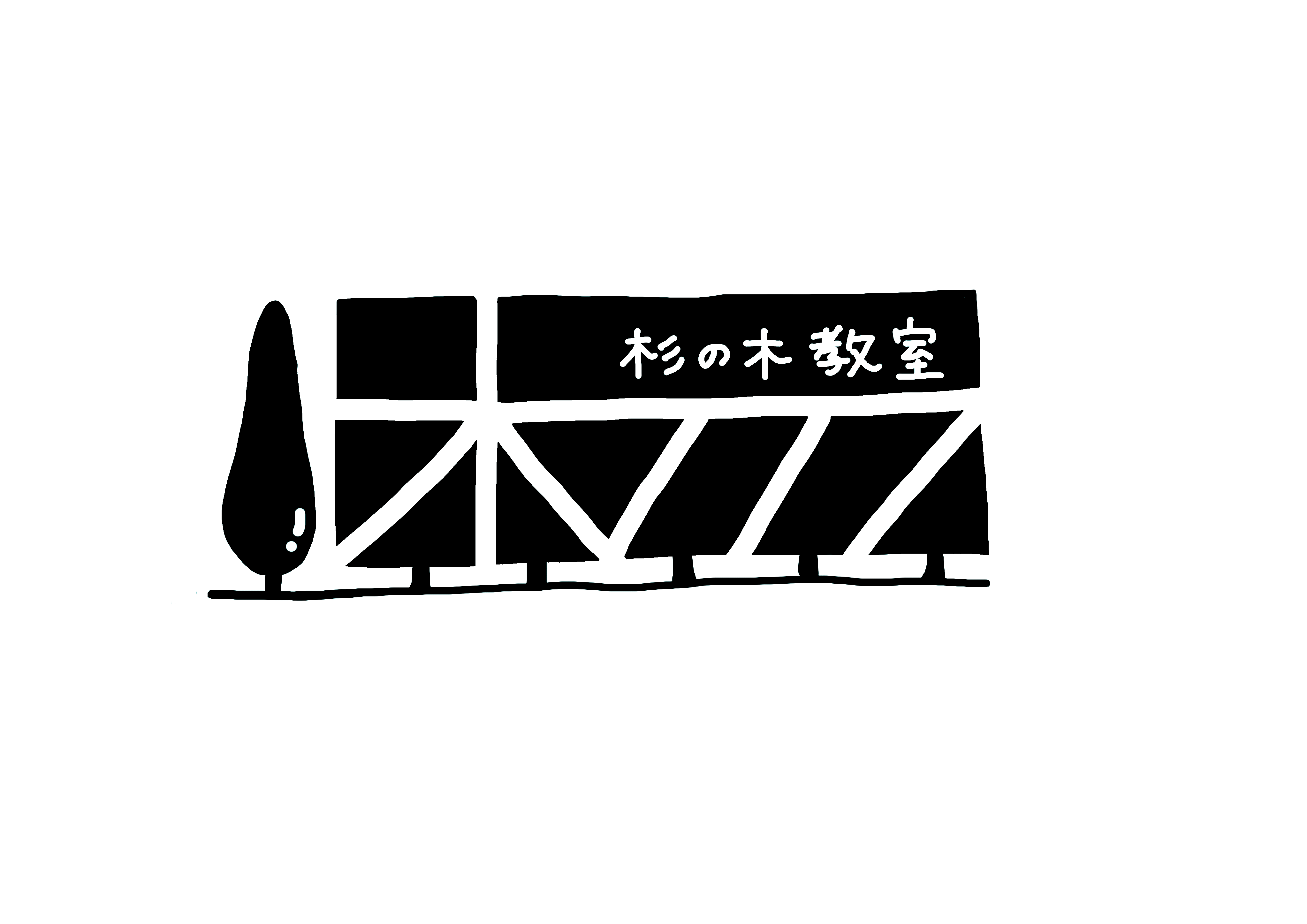
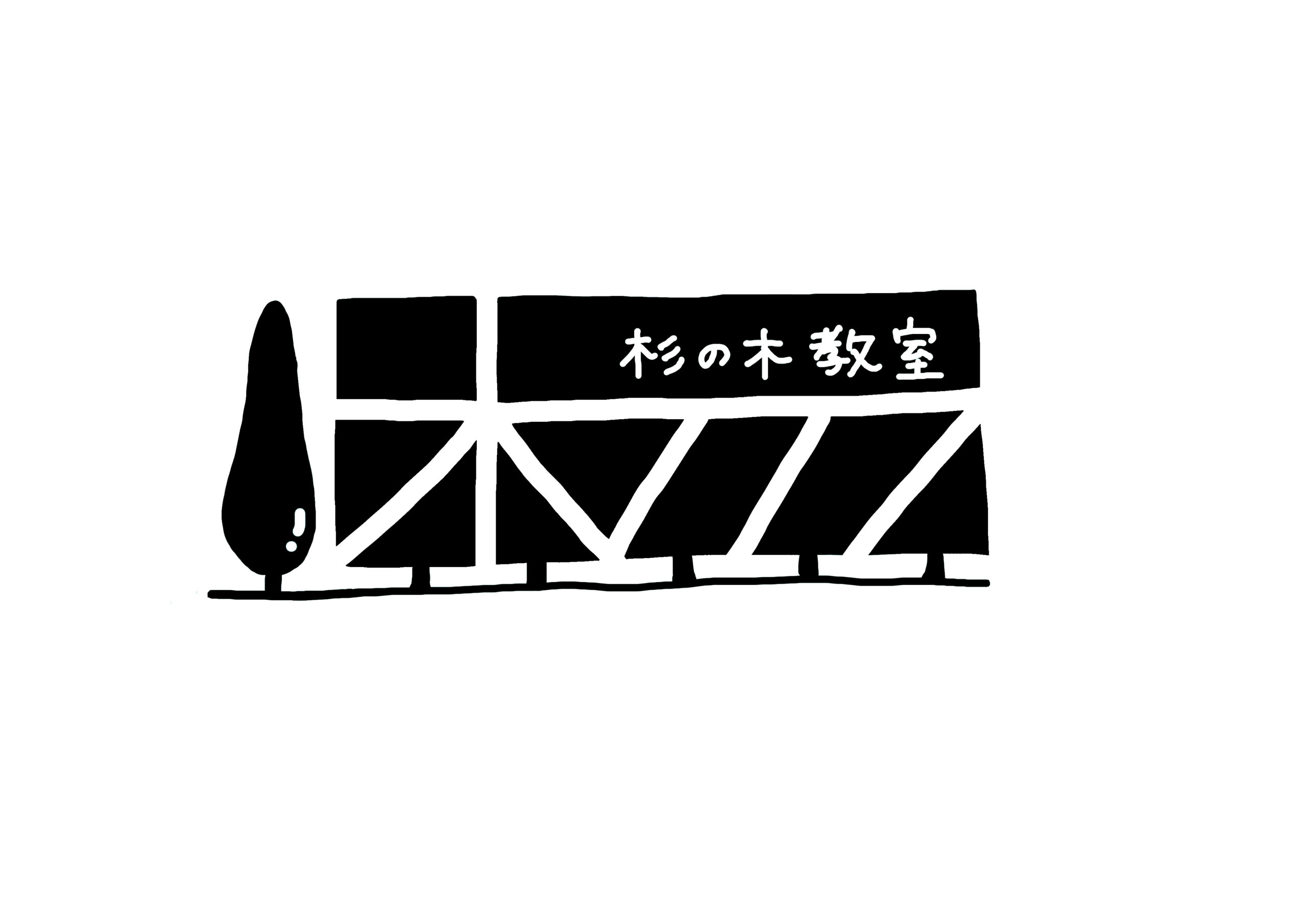

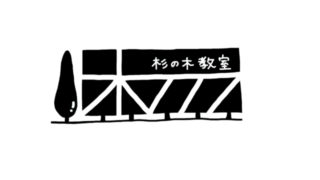
コメント