「100度のお湯で淹れます、そうすると農家さんの考えていることまでわかります。」これは日本茶のセミナーの先生の言葉。「一流人物の書はともかく精彩があって生きている。二流人物となると、半死半生である。三流人物すべてに取るところはなく、最早問題にならない。」一方こちらは魯山人の言葉だ。二人の言葉は、ある対象を通してその作者の精神をうかがい知ることができるという点で一致している。
日本茶にはいくつかの種類があって、それぞれに合わせた淹れ方がある。ほとんどはぬるめのお湯でじっくりと淹れて旨みを楽しむ。しかし敢えて100度の熱湯で淹れて、旨味だけでなく苦味や苦渋味、香りに至るまでの茶の全てを味わい尽くす。茶の先生はそうすることで、その味の向こう側にいる人を想像することができるのだという。
「書相は、よくその人の価値を表現する。」「人品良き者は品良き書を、下品なる者は下等なる書を、強き個性を有する者は、強靭なる書を、個性軟弱なる者は、その線極めて脆弱にて、筆力剛健ではない。」魯山人は、有名無名に関わらず、その書にはその人の真の姿を見てとることができるという。「大人物なるが如くして、決して大人物にあらざることを書相に表しおるもの」として具体的に名前をあげたりもしている。
茶を飲んでも、書を見ても、その向こう側に存在する人格を想像することはなかったが、確かに双方ともそれらを作り出した人物が必ずいる。茶の木は勝手に生えているが、生えているだけでは茶にはならない。葉を摘み、熱を入れて乾燥させるなどの作業をする人が必要だ。もちろん書も人が墨をすり、筆を持って紙に向かわないと存在しない。そこには必ず人がいるのである。そしてその人には、独自の人格というものがあるのだ。
茶の先生はまだ若いがたくさんの茶を飲み、茶畑を訪ね、生産農家との交流も重ねており、自分なりの茶のあるべき姿を持っている。魯山人は言わずと知れた書の名手であり、また陶芸や料理など日本の美を体現した芸術家である。この二人はそれぞれの対象を通じて学び、自己の内面を形成してきた二人であるから、たとえばあるお茶や書を通して、それが生まれてくる精神的な土壌を窺い知ることができるのかもしれない。
茶や書よりも、それが生まれてくる精神的な土壌を想像しやすいのは言葉であろう。美しい言葉や下品な言葉、そこからそれを発した人の心を想像することは容易いことだ。
言葉については井筒俊彦の考えが興味深い。彼は大乗仏教の思想を取り上げ、言葉の源について述べていた。それは、心の奥底にあり、あらゆる経験がそこにはたまってゆく。それらの経験は煙のように漂い、言葉の種となり、種同士が結び合わさって、意味を持つ言葉となるのだそうだ。言葉は、外部からの刺激が私たちの内部に蓄積して、ある一定の量に達したり、適当な組み合わせとなったとき、われわれの内部から生まれてくるものだと述べている。
一方メルロ=ポンティを訳した中山元は、その解説の中で次のようなことを述べている。言葉で表現をすることは生きてく中で重要な行為であるが、その言葉とは自分だけが使うものではなく、他者も使い、他者から学ぶものである。そして、他者と交流することによって自己を形成する。つまり「<わたし>という存在は、言葉を使うことを学び、言葉によって他者と交通することによって、はじめて可能となる」そうだ。
ここでは自己を形成する言葉は、自己の中から生み出されるというよりも、他者から与えられるものとして述べられている。さらにまたその自己は、言葉を語ることによって思考を示し、個人として社会の中に具体的に存在する。メルロ=ポンティ自身の言葉では「この実存的な意味は、言葉によって訳されるだけでなく、言葉に宿り、言葉から切り離すことができない」と述べられており、私たちの思考は、他者から与えられた言葉によって成立し、言葉なしでは存在しないとされている。「言葉を語ることで、わたしの思考がはじめて存在するようになるのであり、その言葉以前に思考が独立してあったわけではないのである。」つまり言葉は私たちの内部から生まれてくるものではなく、外部にありながらも私たちを作っているものなのである。
確かに私たちは言葉を発明したわけではない。言葉は他者から学んだものである。その他者からのもので自己を形成し、また他者に影響を与える。この共に影響を与え合う関係は事実に即していると思う。井筒のいうように自己の中で生成されると感じると同時に、それは自己が介在しない完全なる他者のものであるともいえる。例えば「腹が立った」と口に出すことで本当に腹が立ってしまう。「こんなことするなんて、あいつを許してはいけない」などというとますます腹が立つものだ。しかし「こんなことするなんて、どうしたのだろう」というと、私たちの意識は怒りよりも相手の行動の原因に向いて怒りは収まることがある。「腹が立つという状態」は、「腹が立つという言葉」なのかもしれない。
井筒の説は、言葉を覚えた大人が、日々の経験に触発されてある詩を書くようなイメージかもしれない。言葉にならないような経験をさまざまな例えで輪郭を描くように表現するようなものであろうか。メルロ=ポンティの説は、子供が言葉を覚えていく中で、複雑な思考を持つようになることのイメージかもしれない。刺激に対して泣いていただけであったが、笑い、声を発し、その名前を呼ぶ。そして好きや嫌い、さまざまな反応を見せるようになる。内部からの言葉と外部からの言葉、いずれも私たちの言葉なのであろうか。
魯山人の造語に<坐辺師友>というものがある。これは「自分の身辺にあるものこそが、おのれの師であり友である」という意味で、日常の道具にもこだわりぬいた彼の信念である。自らの中に外部からどんな刺激を受けるかによって、自己は形成されると考えていた。美術品など当時のものだけでなく古いものも、金のない頃からこつこつと集めて、それらから多くを学んだという。
私の坐辺には何があるだろうか。そしてそれらから何を学んでいるであろうか。身の回りを眺めてみたのであった。
まず初めに飛び込んでくるのは、狭い部屋には多すぎる植物たちである。冬になると外には出しておけない熱帯の植物たちが、狭い部屋の限られた棚に所狭しと並んでいる。ゆっくりではあるが確実に成長し、その環境、例えば日当たりなどを、そのままに映してそこに生きている。学ぶなどという大それたことはしていないと思うが、植物をかまいすぎていた最初のころと比べると、それぞれの植物にとっての快適を理解することができるようになり、いい距離を持つことができるようになった。
次に見えるのは、楽器だ。サックス、ギター、ベース、電子ピアノ。押入れを開けるとまたベースとキーボード、クラリネット、従妹からもらったフルート、ウクレレ、祖父の形見の尺八。こちらも私の部屋には多すぎる数がある。主にサックスとベースを演奏しているが、ほかのものは長くほったらかしにされている。楽器に関しては、その演奏と音楽自体を学んだ。がしかし最近はお手本にしたい演奏家や音楽が見つけられないまま、何を演奏すればよいかわからなくなっている。音楽の向こうに自由や平等、革命などの思想を感じてしまって、嫌悪感を持っている。楽器に囲まれているものの、心の中では美しい旋律や和音は響いていない。
最後は本である。一時期、電子書籍を主に買っていたが、ある時期からまた紙の本を買うようになった。書き込みをしたり、すぐにページをめくることができたりと、やっぱり紙の本が好きなのであった。こちらは文字通り多くを学んでいる。本は人のようであると感じていて、そこに示されている思想もさることながら、同時に存在としても私に刺激を与えてくれる。最近になるまでプラトンとアリストテレスの原著、翻訳本ですら読んだことがなかった。解説本や哲学史で一応の概説は知っていたが、直に彼らの言葉に触れたことはなかった。そして翻訳本を買って家に持って帰ったときは、本人が家に来たというのは言い過ぎだが、それに似たような興奮と今までとは違うといういい意味での違和感を感じたのだった。本はもちろん読むものであり、その内容から影響を受けるが、また同時に物としての存在感とそれにまつわるこちらの観念が刺激されて、何とも言えない学びとなっていると思う。
話をメルロ=ポンティに戻すと、外部から受け取り我々を存在させている言葉は、歴史性、時間性をそのうちに持っている。言葉、すなわち言語は長い年月をかけてその文法や語彙が整理されて、現在も変化し続けている。そこにはそれが経てきた歴史や時間が織り込まれているのだ。そういった言葉を自分の内部に取り込むということは、同時にその歴史性や時間性をも取り込むことになる。よって我々は先人たちとのつながりを持った存在となるというのだ。
茶の先生、魯山人は、それぞれの坐辺に茶、書を置き、それらを通じて自己を表現している。それと同時に、茶や書が二人の内部に浸透し二人を形成してもいる。茶は自然の営みの息づかいも共に内部に吹き込むのだろうか。書は先人の創意工夫の汗も共に滴らせるのだろうか。言葉が、それが経てきた歴史や時間を人に与えるのなら、茶や書も同じように、その歴史や時間を与えるのだろう。もっというなら私たちに表現の道具として使われるだけでなく、私たちをその歴史や時間の表現の場として使っているのかもしれない。
メルロ=ポンティはフッサールの現象学を引き継ぎ、物心二元論を<身体>の両義性で解決しようとした哲学者である。物心二元論とはデカルトの思想で、物体と心的なものとの相互交渉を排して、両者を完全に独立したものとする。この考えは、物体のみで完結するニュートン的近代物理学の成立を可能にし、その後の科学の飛躍的発展の土台となった。しかし体と心の相互交渉が全くないとすることはあまりにも不自然であり、デカルト自身もこの点を問題としていたのであった。デカルトは脳内の松果腺がその交渉を可能にするとしたが、のちに大脳生理学の発展によって否定された。この心身問題は、現在でも哲学の根源的な問題とされている。
メルロ=ポンティは、知覚の主体である<身体>を、物体と心的なものの両面を持つものとしてとらえ、世界を人間の身体から考察することを唱えた。身体から離れて対象を思考するのではなく、身体から生み出された知覚を手がかりに、身体そのものと世界を考察したのであった。この考えに惹かれて私の本棚にはメルロ=ポンティの本が並んだ。私の知覚がメルロ=ポンティを認識する、そうしたらメルロ=ポンティが私の心の中で植物や楽器と共に動き出し、何か表現してくれるのだろうか。茶の先生のように100度のお湯を私にかけたら、全てすぐに出てくるかもしれない。がそういうわけにはいかない、ふでのまにまに茶を淹れて待つ。
令和6年12月26日
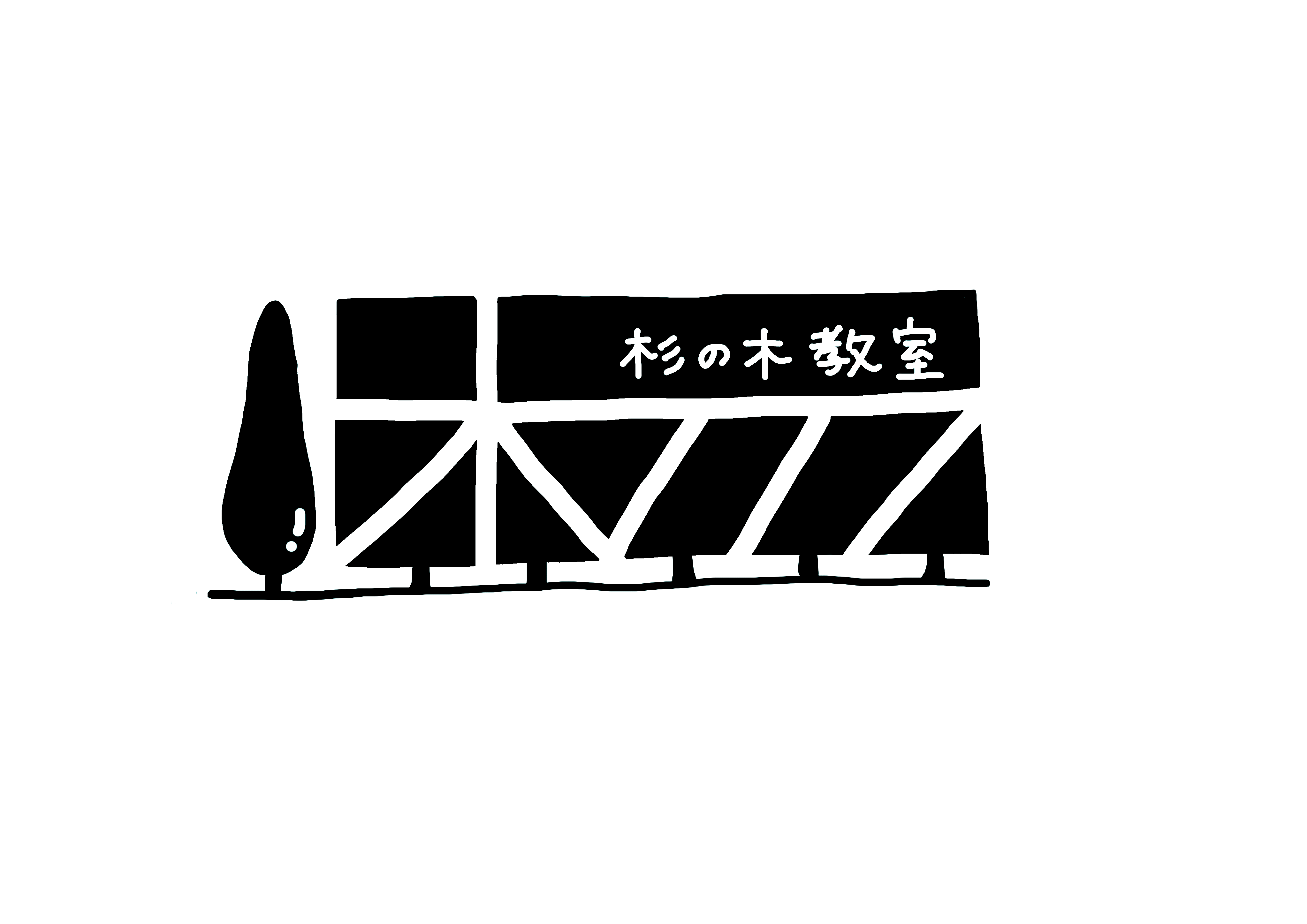
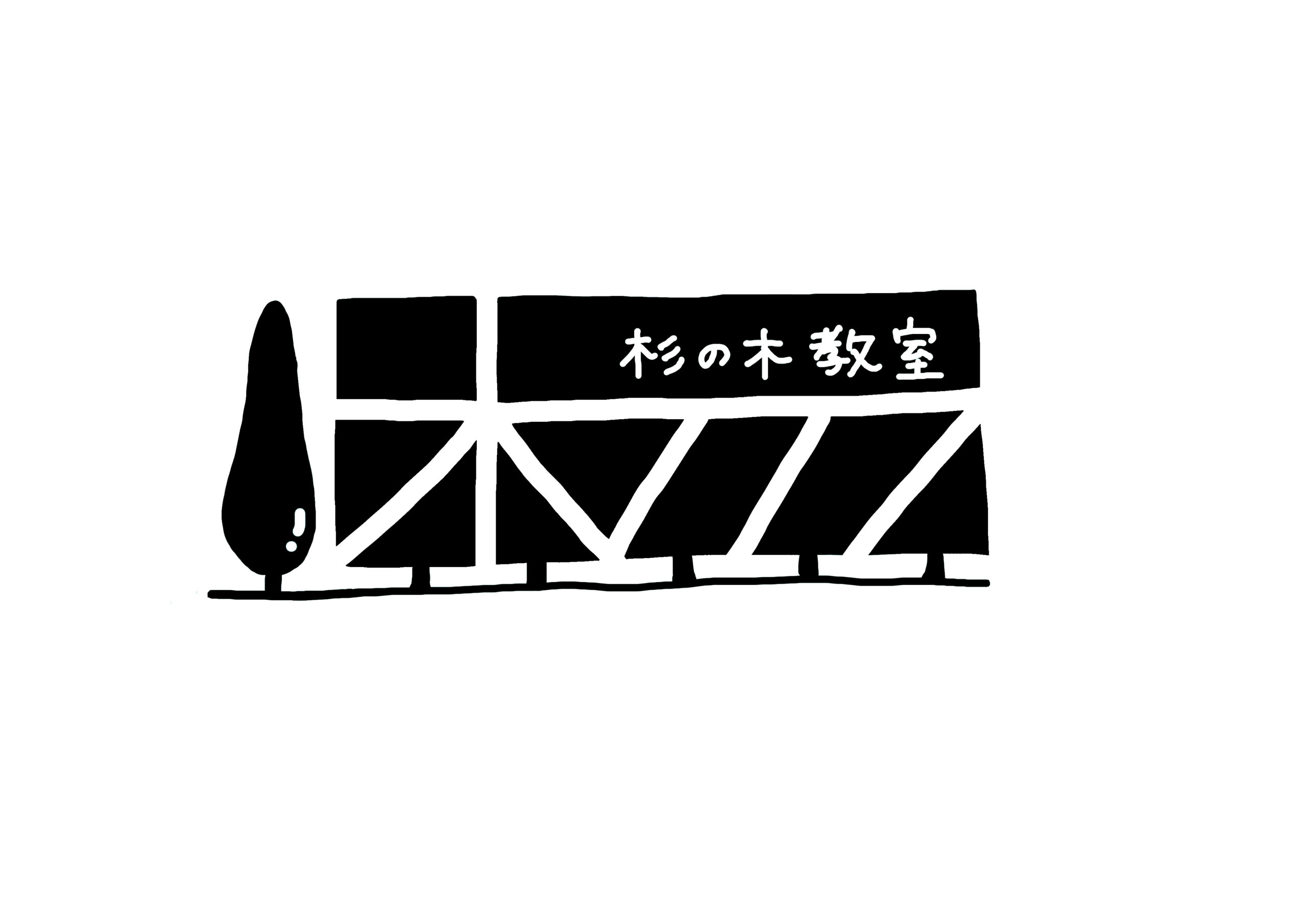
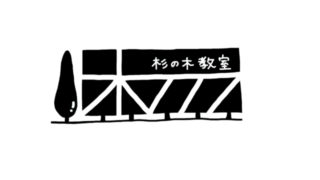
コメント