若い頃、音楽を一緒にやっていた友人から連絡が来た。故郷の世羅でピザ屋を開店してから10年が経ったので、そのお祝いのパーティーをやるから来てくれないかと。パーティーは日曜日で、仕事柄休みは取りにくいが、なんとか都合をつけて行ってきたのだ。
世羅とは広島県世羅郡世羅町のことで、簡単に言えば田んぼと畑だらけの田舎である。友人はこの田舎の町から音楽をするために大阪に出てきていた。全力の広島弁で元気よく喋る楽しい男である。彼はドラムを叩き、私はサックスを吹く。初めはそれぞれのバンドで演奏していたが、仲良くなって同じバンドで演奏するようになった。
17年ほど前に彼も私も結婚をして子供ができた。それと同時に彼は故郷の世羅に帰って、ピザ屋を開店するための修行を始めたのである。その頃からは年賀状のやり取りだけで実際に会うことはなかったので、今回の再会は17年ぶりであった。互いに歳を重ねて、特に外見において変わってしまったところもあったが、気持ちの上では昔と変わらない気の合う仲間であった。
彼のお店は人気店で行列のできるピザ屋のようだ。地域の集まりでは中心的な役割も担っているようで、元気よくみんなを引っ張っていってくれるその人柄は、昔以上に力強く頼りがいのある印象になっていた。
彼の他にパーカッションの友人と私と同じくサックスを吹く友人も来ていた。この2人も世羅郡の出身で、3人は幼馴染である。その3人で大阪に来てバンドをしていたので、パーカッション、サックスの友人とも私は仲が良く、その2人との再会も合わさって今回のパーティへの参加の喜びは一入であった。
パーティーではピザを食べたり、演奏を一緒にしたりと本当に楽しい時間を過ごした。移動に時間がかかったが、その価値は十分にあったのだ。旧友との再会は古今東西、素晴らしいものとされているが、私のそれもその例に漏れず筆舌に尽くしがたい感情を抱いたのであった。
世羅についてはよく知らないが、江戸時代には島根県の大森と広島県の尾道を結ぶ石見銀山街道の宿場町として発展していたそうだ。しかし近年は若者が減り高齢化が進み、いわゆる田舎の町の悩みを抱えているようだ。そんな世羅をこよなく愛する彼らは、清掃活動や音楽イベントをやって町を盛り上げている。
彼らは田舎らしい大きな家と広い田畑を持っている。先祖代々受け継いできたそれらを引き継ぎ守ってゆくのだそうだ。転勤族のサラリーマン家庭の私には想像もつかない感覚だが、大地に根を張っているような安定感は羨ましくもある。
私の本棚にはフランスの哲学者シモーヌ・ヴェイユの『根をもつこと』という本が積読されている。積読とは読まずに積んである本のことであって、この本の内容はあまりわかっていない。題名に惹かれて買ってから、最初を少し読んだあとは積んだままであるが、気になっている本である。
人間には身体的と精神的な欲求があり、それぞれに対応する「糧」がある。その中でも精神的な欲求を満たすものとして「根をもつこと」があり、最も切実なものであるそうだ。
私がそもそもこの本の題名に惹かれたのはなぜであったか、自分には「根」がないのではないか、自分の「根」は立派なものではなく、まがい物ではないだろうか、そんな思いを持っていたからかもしれない。世羅は本当に美しい町であった、高い空と穏やかな山、田畑が広がり、その上を風がさらさらと音を立てて通ってゆく。おおらかで落ち着いた家屋が並び、まばらに人が動いている。イメージ通りのふるさと、そんな故郷を私は持っていない。両親や祖父母との深いつながりや、自然と響き合う思い出、そんな「根」と言えそうなものを私は持っていない、美しい世羅の空の下、時折みじめな気持ちが心に見え隠れしていた。
ひとつも持っていないなどと言うのは、あまりにも自分を悲しい存在として演出しすぎている。がしかし、帰るような場所もなく目指すような場所もないと感じているのは確かである。「根」がなければ伸びてゆくべき太陽の方角も感じられないのかもしれない。
私が奉職している神社も世羅と同じような山と田畑に囲まれたところにある。悠久の歴史と美しい自然に囲まれたその環境は、「根」とするには申し分のないところである。この神社に骨を埋めるつもりで毎日働いている。その発展に貢献しようと奔走している。地域の方ともふれあっている。がしかし、この神社で働く者が私でなくてもいいし、私もこの神社じゃなくてもいいのではないかと思うことがある。強いつながりをもつことができていない、もっと厳密に言うならつながりを試してみたくなっている。
私の父はサラリーマンだ。私は普通の家庭に生まれて神主になった。別に悪いことではないが、一般的には、家が神社の人が神主になることが多い。それに比べると必然性がないような気がする。神社の家の人はやめたくてもやめられない、しかし私はいつでも辞めることができる。小さい頃から頻繁にお参りをしていたわけでもなければ、父や母が神社を崇敬しているわけでもない。神主という仕事と必然性を感じるつながりを私は持っていない。
先日は子供の誕生日であった。私は離婚をしているので、別居している子供とご飯を食べに行った。中学1年生で、身長は伸びてきたが中身はまだまだ幼い、欲しいゲームを買ってくれないとわかると、機嫌が悪くなり帰っていってしまった。直情的な性格は幼い頃からだ。そんな彼ももう少し成長してきたら、自らの「根」について思いを巡らせる時が来るのだろうか。その時、私は彼の「根」の一部である。自らの「根」に悩む私ではあるが、よく考えるとすでに誰かの「根」であった。
両親や祖父母との深い繋がりがないと書いたが、別にいがみあっているわけでもなく、幼い頃に放っておかれたわけでもない。しかし取り立てて繋がりを表す現象がないのだ。例えば、職業が一緒であるとか、趣味が一緒であるとか、何かを相続することになっているとか、特別な関係性が特にはないのだ。
私は「根」という幻想を見ているのかもしれない。「根」という抽象的な言葉から連想する「現実には存在しない理想的な私という人間の始まり」を夢見ているのかもしれない。
「神道は、日本の有史以来の土着信仰として、歴史的変遷を超えて根強く生き続いてきた伝統である」。このような主張を我々神道人はする。「そこには、縄文時代のアニミズム、または古代天皇が体現した『和』が、神道の儀礼を通して今なお作用しているという信念。そして、現代社会は堕落していても、神道の伝統的な理念を守れば遠い昔の黄金時代を再現することができるという展望。この神道神学は、『古代の和・現代の堕落・古代の復興による将来の新たな和』というユートピア思想」であるとノルウェーのオスロ大学教授のマーク・テーウェン氏は指摘した。
私が神道を通してみているものと「根」を通してみているものは、同じようにユートピア思想なのだろうか。それは現実には何も作用することのない机上の空論なのであろうか。
このあとマーク・テーウェン氏は「神道」と「神社」を区別している。「イスラム教とモスクの場合には、神学が先にあり、それを実践するために建てられた施設がモスクですが、神社の場合は、順番が反対になっている気がします」と述べている。つまり「神社」が先にあり、そこに後から理由づけのように「神道」という神学が生まれたということだ。私が考えている「根」もここでいう「神道」のように、具体的な「神社」のような存在に後から付け加えた概念であろうか。
世羅に行った時の写真を見返していると、ドラム、パーカッション、サックスの友達の3人と私が肩を組み、満面の笑みを浮かべていた。子供が帰ってしまった食事の日の最初の方の写真には、回転寿司のはまちを4皿も並べてあの子が笑っていた。母の日の写真には、父と母が花束を挟んで笑っている。明日は朝一番に神社の外でのお祓いがあり、帰ってからは結婚式がある。この随筆を書いている途中には、彼女と毎日の電話をしていた。
これらが私の「根」であろうか。いや、「根」とはもっと古いものであろうか。私が求めているもの、私の精神が求めている糧とはなんであろうか、まだ言葉にはなっていない。
マーク・テーウェン氏は、神道神学の真髄を①日本特殊主義と②ユートピア的懐古主義と述べている。日本には他と違って独自のものがあり、それらが古代から連綿と続いている。その伝統をもっと強く蘇らすことによってさらなる発展がある。このような考えのバリエーションが歴史を通じて繰り返されてきているという。そして神道・神社が今後どのようなユートピアを追求するかを見守ってゆきたいと締めくくっている。
今はまだ言葉にならない「根」を表現することは、新たなユートピアの創造となるだろうか。ふでのまにまに世羅の空を想っている。
令和6年7月12日
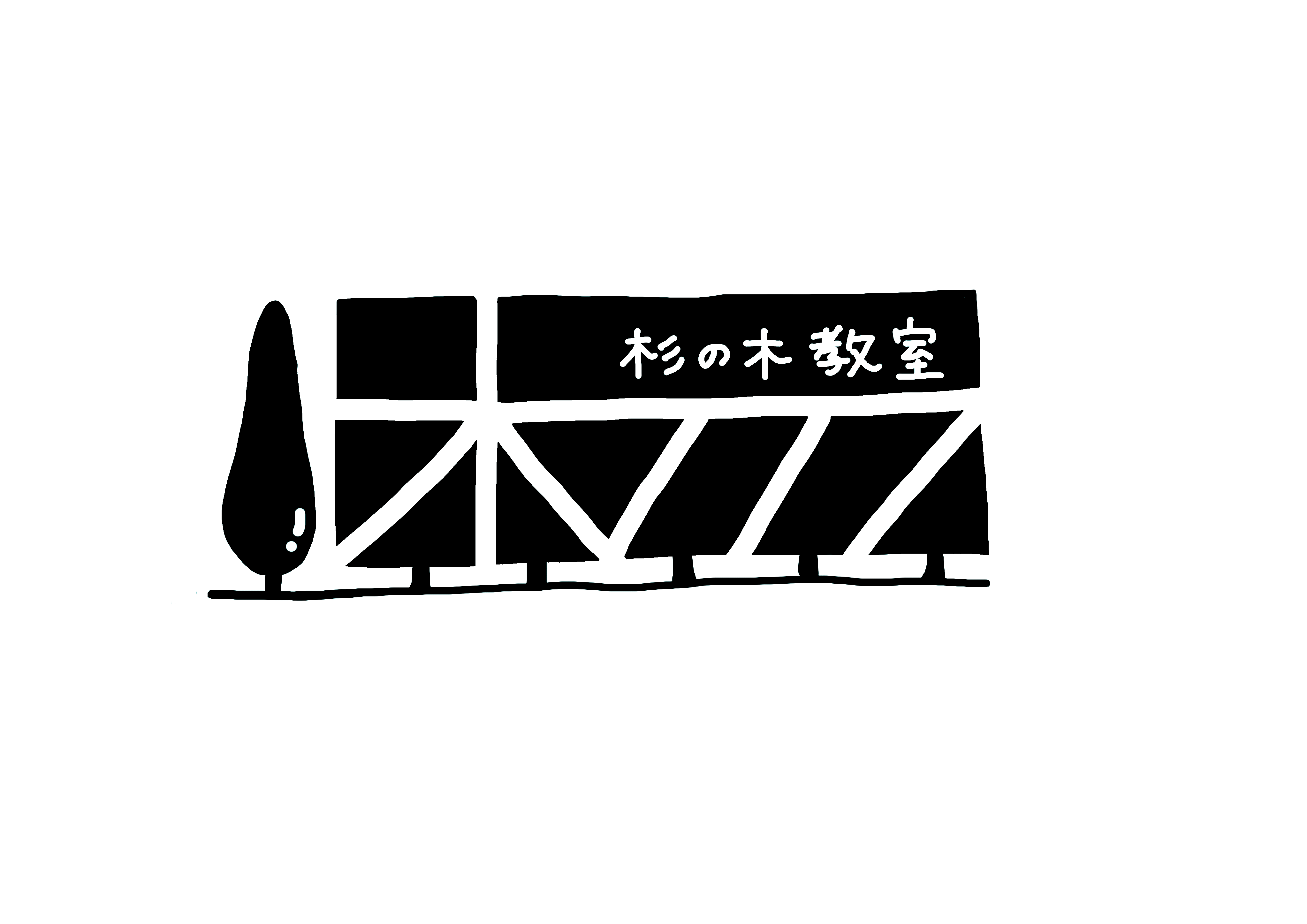
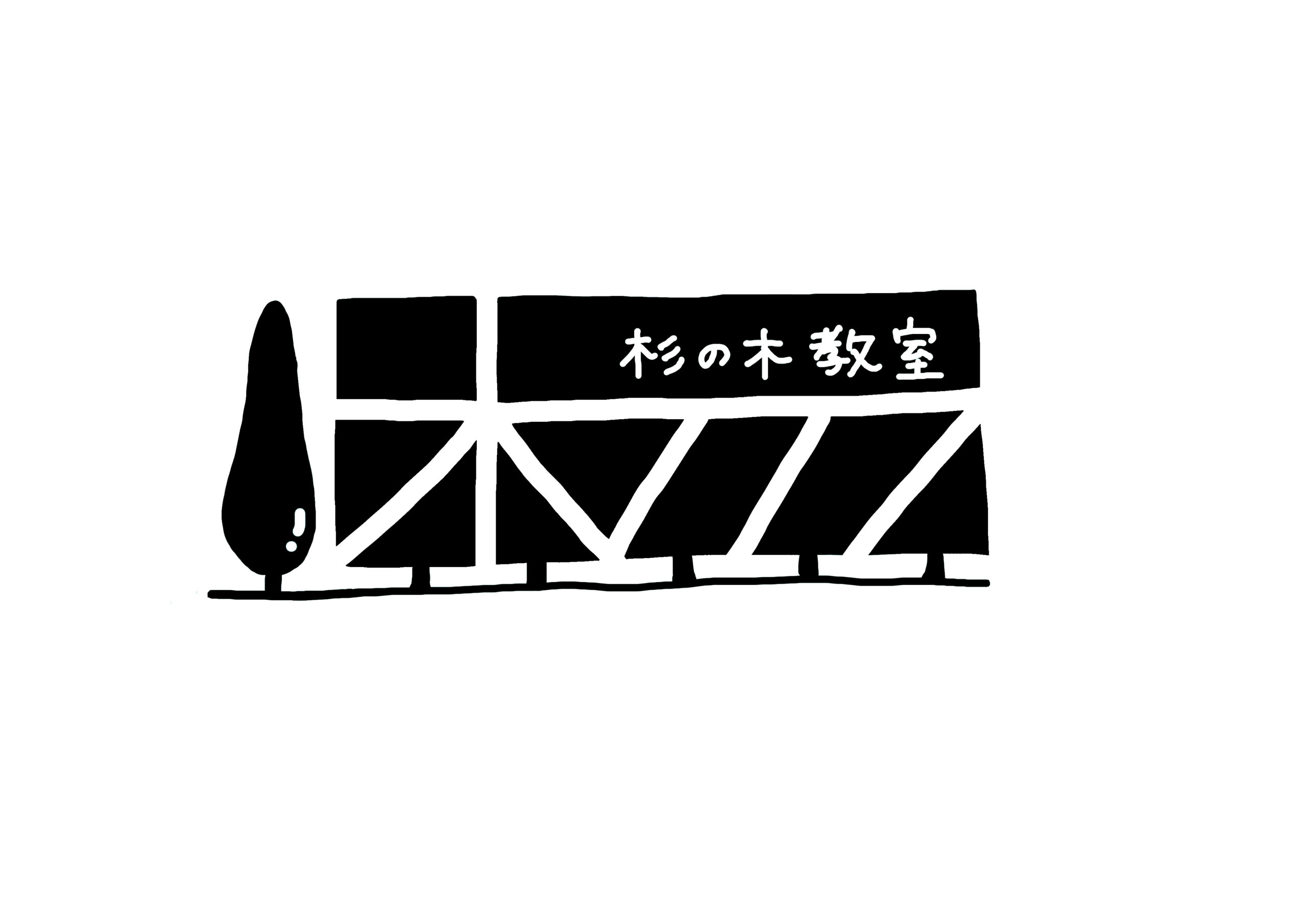
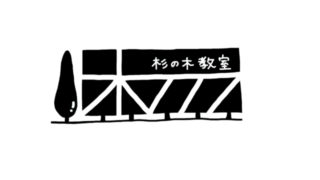
コメント