日本は国民主権の自由主義国家ではなく、官僚主導の社会主義国家である。このような認識のもと、実際に日本を動かしている官僚になる子供たちに正しい国家観を教育するために、竹田恒泰氏は中学校日本史の教科書を作った。竹田氏は将来国を動かすべき徳の高い人間を日本史の教科書を作ることで残そうとしている。現在の官僚の思想を変えることやその機構の変革は、竹田氏一人の力では出来ないと述べていた。だから将来官僚になる子供たちに正しい国家観を教育するのだという。竹田氏の教科書で学んだ中学生が官僚になり、実際に国を動かすまでは30年から40年ほどかかるかもしれない。時間はかかるが正しい国家観を持った人間を育てることができれば、日本を守ってゆくことができるだろう。「金を残すは三流、仕事を残すは二流、人を残すは一流」という言葉がある。人を教育し正しく導いてゆくことは、最も尊い仕事であり、最も困難な仕事でもある。
日本には選挙があり、国民の代表として選ばれた人間が政治を行なってゆく。国民主権であり民主的で自由な国であるという認識が一般的ではあるが、竹田氏の調べたところによると、総理大臣になったとしても全体の2割ほどしかやりたいことはできないという。残りの7割から8割は官僚が国を動かしているのだそうだ。官僚は選挙で選ばれた人間ではない。その彼らが国を動かしているとしたら民主主義ではないと言える。そして選挙で選ばれていないと同時に辞めさせることもできない。国民が政治に関わることができていると言えるだろうか。しかもその官僚が偏った思想を持っていたり、私利私欲に走っている場合、この日本という国の将来は危機にさらされていることになる。
竹田氏は政治評論家であり作家であるわけだから、そんな官僚機構を政治的に改変させることよりも、言論の力で正しい国家観を広めようとしている。言説を持って人々を啓蒙し、正しい歴史認識にたって日本の今後を良くしていこうとしている。今現在の官僚を感化して変えてゆくことよりも、これからの人間を教育して導いてゆくことのほうが容易であるし、また将来的に価値のあることだと考えたのであろう。
この歴史の教科書の主題は、「日本人の日本人による日本人のための歴史」であると思う。これは令和2年に出版された竹田氏の「天皇の国史」の「はじめに」に述べられた氏の主張である。「これまでの『日本史』は、外国人が学ぶ日本の歴史と同じだった。感情を排して淡々と綴られていた。しかし、日本人が学ぶべき日本の歴史はそれとは異なるはずである。」と述べている。この主張は、安倍晋三元首相のそれと一致している。安倍氏は平成18年に「教育基本法」を改正しているが、旧法に対して次のような言葉を残している。「確かにいいことも書いてあると思いますが、この基本法はどこの基本法か分かりません。非常にコスモポリタン的で日本の香りがしません。戦後の教育の問題はこの教育基本法にあります。」両氏ともに、日本を外側から客観視するだけの、他人事のような姿勢に不満を持ち、内側からの目線で自分のこととして捉える積極的な態度を求めている。新法には、伝統と文化を尊重すべきことと、日本国と郷土を愛すべきことなどが書き加えられている。これによって具体的には、国歌の君が代や日本神話などの指導ができるようになったそうである。
私は実際に誰が日本を動かしているのかを知らない。それらを調べる術もない。だから竹田氏の官僚が日本を動かしているという認識が正しいのかはわからないが、その志には共感する。「日本人の日本人による日本人のための歴史」を学びたいと思うのだ。
高校の時は世界史を選択していたし、歴史自体得意ではなかったので、日本史はよく知らなかった。卒業してから自分で本を読んで勉強したが、あまり面白いとは思わなかった。しかし興味を持つきっかけとなったのは、平泉澄氏の「少年日本史」であった。その名の通り子供向けの歴史の本であるが、とても親身に日本のことが書かれていた。「私たち」のご先祖さまの物語として親しく読むことができたのだ。これと似たもので戦前の教科書復刻版の「初等科国史」もある。こちらも日本という国を「私たち」の国と考え、過去の人々を「私たち」のご先祖さまと呼び、自分自身のこととして歴史を捉えることができた。
今回出版された竹田恒泰氏の「国史教科書」は、この2冊と同じ印象を持った。世界市民として日本という国の歴史を見たのではなく、日本国民として、さらには自分のこととして捉えることができるのである。
私は今哲学書を書いていて、骨子となるものに「関係性の存在論」とそして「根」というものがある。「関係性の存在論」とは、すべては関係していて、この「関係の外側」はないというものだ。この歴史についての態度で言うと、我々は日本人であるということの「関係の外側」には出ることができない、さらには「関係の外側」はないと思っている。祖国を飛び越えた世界市民なんてないのだ。なぜなら世界というのは個々の国が抽象化された概念で、この世のどこにもないからだ。そして、人間を支えるものとして「根」を想定し、それは物理的肉体的なものと、精神的なものに分けて考えられる。その精神的な「根」については国家が大きく関わっていると考えており、その国家を愛すること、もっと具体的にいうと愛する行為が「根」を強くし、精神を安定させると考え、日本の場合その行為として祭祀があると思っている。つまりは、私は日本人であり世界市民ではない。このことは他国のことを気にかけないということではなく、この国土に生き、日本語で話し思考しているなどの文化的事実から明らかである。この事実の外側を想定せずに、またそのことを肯定しそこから建設的に未来を切り開くための具体的な行為として、「日本人の日本人による日本人のための歴史」を学ぶことが重要だと考えている。こんな興味から「国史教科書」を手に取り、そして夢中になって読んだのだ。
興味深く読んだ箇所をいくつか紹介したい。
日本についてのもっとも早い時代の記述は、前漢の正史「漢書」地理志だそうで、そこには紀元前1世紀ごろの日本は100以上の小国が分立していて、日本から前漢に定期的に朝貢する国があったそうだ。朝貢とは、周辺の国や民族が、中国王朝に貢物を献上することである。朝貢する国が中国王朝に服従を誓い、その見返りとして皇帝から称号や官職を授かったという。この外交の仕組みを冊封体制という。この冊封体制について日本人の誇り高き独立心が書かれていた。
一人目は雄略天皇で、宋が478年に滅亡すると、以後朝貢を行っていない。理由は主に3つ考えられる。①北魏が山東半島を支配下に置いたため、使者を派遣することが困難になった、②宋が滅び、身分の低い者が次々と皇帝に即位したため、遣使の価値がないと判断した、③支配体制が成熟したため中国王朝からの冊封を必要としなくなった。この中で③がもっとも支持されているようで、大国に頼らず自立しようとするその意思が勇ましく思った。
2人目は聖徳太子だ。600年に朝鮮半島での影響力を保つことと、先進文化を摂取することが目的で、122年ぶりに大陸への使節、遣隋使を送った。この時は随には馬鹿にされたようで、その悔しさからか「日本書紀」には記述がない。しかしその後、冠位十二階や十七条の憲法を定め、先進の中央集権国家を築いた。その上で607年に第二次遣隋使として小野妹子が派遣された。推古天皇が隋の煬帝に宛てた国書には「日の出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙無きや」とあった。日本の天皇にも天子という語が使われていることに隋の煬帝は激怒したようだが、この表現には「朝貢すれども冊封は受けず」という中国王朝に対して対等な地位を築く方針が表れているという。これに関して、太子が礼儀も言葉遣いも知らずに国書を書いたという学者もいるようだが、冠位十二階で儒教の徳目を日本独自に改変し、「徳」という日本独自の徳目も加えたり、さらには神道、儒教、仏教のそれぞれの良きところを取り上げ、それぞれの役目があるとした説話などから考えるに、太子の知的水準が礼儀や言葉遣いも知らないほど低かったとは思えない。「朝貢すれども冊封は受けず」とは、先進の文化を学ばせてもらうその礼として朝貢をするが、冊封を受けるという服従関係にならないというしたたかな思惑があったと思われる。随と日本の力を推しはかり、その上で日本が対等に独立国として付き合っていけるように計算された高度に知的な書であると思う。独立心とそれを実現するための実力がとても誇らしく感じたのだ。
次は時代が飛んで、明治天皇の御製である。
よもの海みなはらからと思う世になど波風のたちさわぐらむ
これは明治37年(1904)の日露戦争の開戦の頃に読まれた御製である。『よも』は「いたるところ、あたり一帯」、『はらから』は「兄弟姉妹」、『など』は「どうして、なぜ」の意であり、「世界の海は、みな兄弟姉妹のように思っている世の中なのに、なぜ波風が立ち騒ぐのだろう」といった意味であろうか。なぜ人々は争い戦争をするのであろうかという、戦争そのものを憂う気持ちを詠んだものであると思われる。
この当時、ロシアを含む欧米諸国は、アフリカや中東地域、アジア地域を次々と植民地化していた。日本は欧米列強と肩を並べる有色人種で唯一の大国となっていたが、楽観視することはできなかった。明治36年(1903)5月、ロシア軍は、清と大韓帝国の国境に流れる鴨緑江を越えて、満州から大韓帝国に侵入し、軍事拠点の建設を始めた。ロシアの軍備増強を放っておけば日本の独立は脅かされる。日本は戦争を避けるためにロシアに満韓交換論という妥協案を提示したが、ロシアはこれを拒否した。明治天皇は開戦に慎重で、内閣に対して戦争を避ける方法を模索するように求めていたが、最終的にはロシアとの国交断絶を裁可し、開戦の火蓋が切られたのであった。
日本は海戦においても陸戦においても画期的な戦法で敵を圧倒し、ロシア軍を破ることになった。この戦争は世界史における近代戦争の転換点ともなったそうだ。しかしながら、このような華々しい戦況が伝えられても明治天皇は表情一つ変えなかったと伝えられている。
そこでこの御製が紹介されている。戦争には勝ったが、戦死者約8万4000人、戦傷者約14万3000人、明治天皇の御心を伝える記述である。
もう一箇所この御製が紹介される場面がある。昭和16年(1941)9月6日、昭和天皇の臨席のもと御前会議が開かれ、陸海軍が対米戦争の準備に入ること、10月上旬までに日米交渉が妥結しない場合は開戦することが示されていた。枢密院議長が政府と、部隊を指揮する統帥部に、外交と戦争準備のどちらを軸にするかを問うたところ、政府の海軍大臣は答弁したものの、統帥部は発言をしなかった。すると昭和天皇が、統帥部が枢密院議長の重大な問いに答えないのは遺憾であると仰せになり、ポケットからメモをお取りになって、この明治天皇御製を二度お読みになった。天皇が御前会議で発言なさること自体が異例であり、また天皇の発言が政治を動かすことは、大日本帝国憲法においては許されていない。にもかかわらず昭和天皇は、明治天皇御製をお読みになることで「開戦を望まない」ということを暗黙のうちにお示しになったのであろう。
明治天皇も昭和天皇も侵略戦争を推し進めたように伝えられることがある。最終的には戦争に至ったわけであるが、このようなお気持ちを最後まで持っていらっしゃったことがよくわかる記述である。
昭和20年(1945)日本は戦争に敗れた。その後の7年間はGHQによる占領政策のもとにあった。その中のメディアに対するプレス・コード(検閲基準)には、連合軍に対する批判を禁止したり、日本を肯定するような言説に対する禁止もあったようだ。すなわち極端に言えば、アメリカを愛し、日本を憎むように教育されたのだ。そのように教育された官僚が日本を動かしてきたとすれば、戦後に立ち戻り、真実をありのままに知ることから始めるべきだろう。この点を克服するためにも、この「国史教科書」は必要だと思う。
「根」は過去ではなく、現在の糧である。因果の初めではなく、中心である。私たちは歴史という物語を自己の中で何度も繰り返しながら生きている。その物語は真実でなければならない。そうでなければ、私たちの「根」は大地とのつながりをたたれることになるだろう。真実はいかに。それらを探し求め愛することを望んでいる。
令和6年8月4日
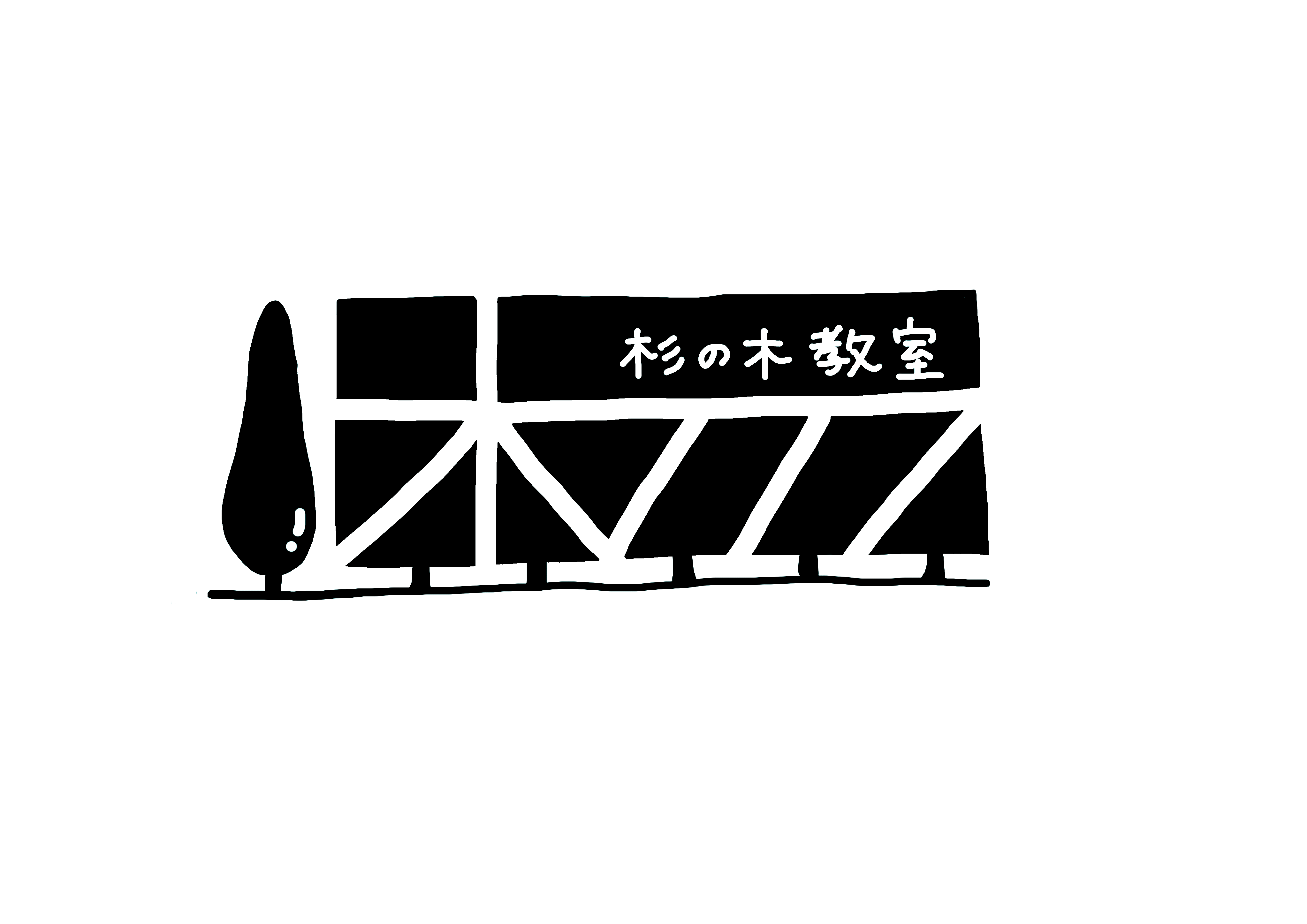
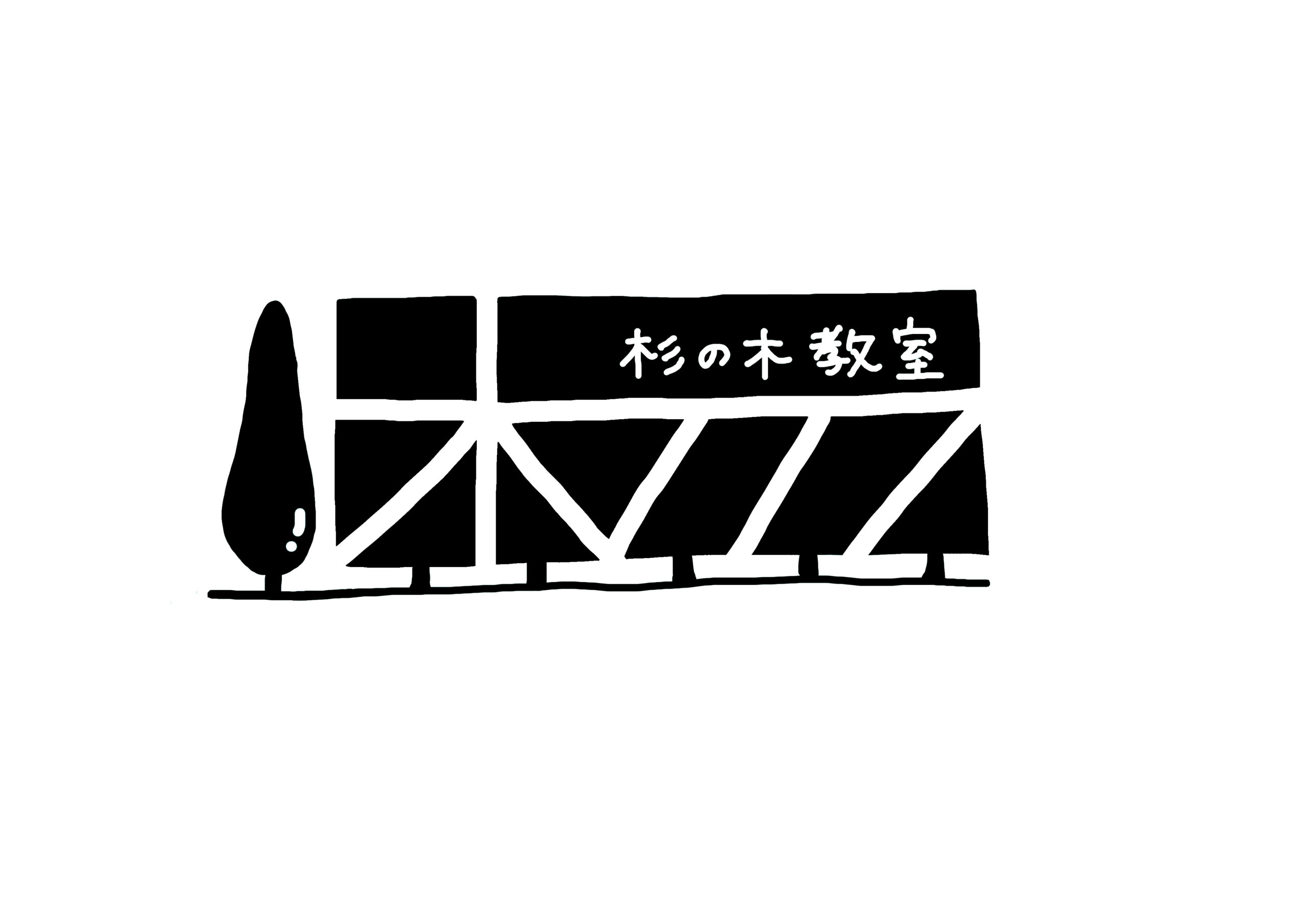
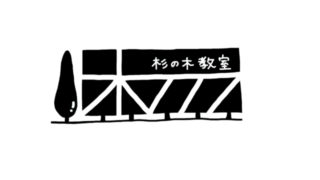
コメント