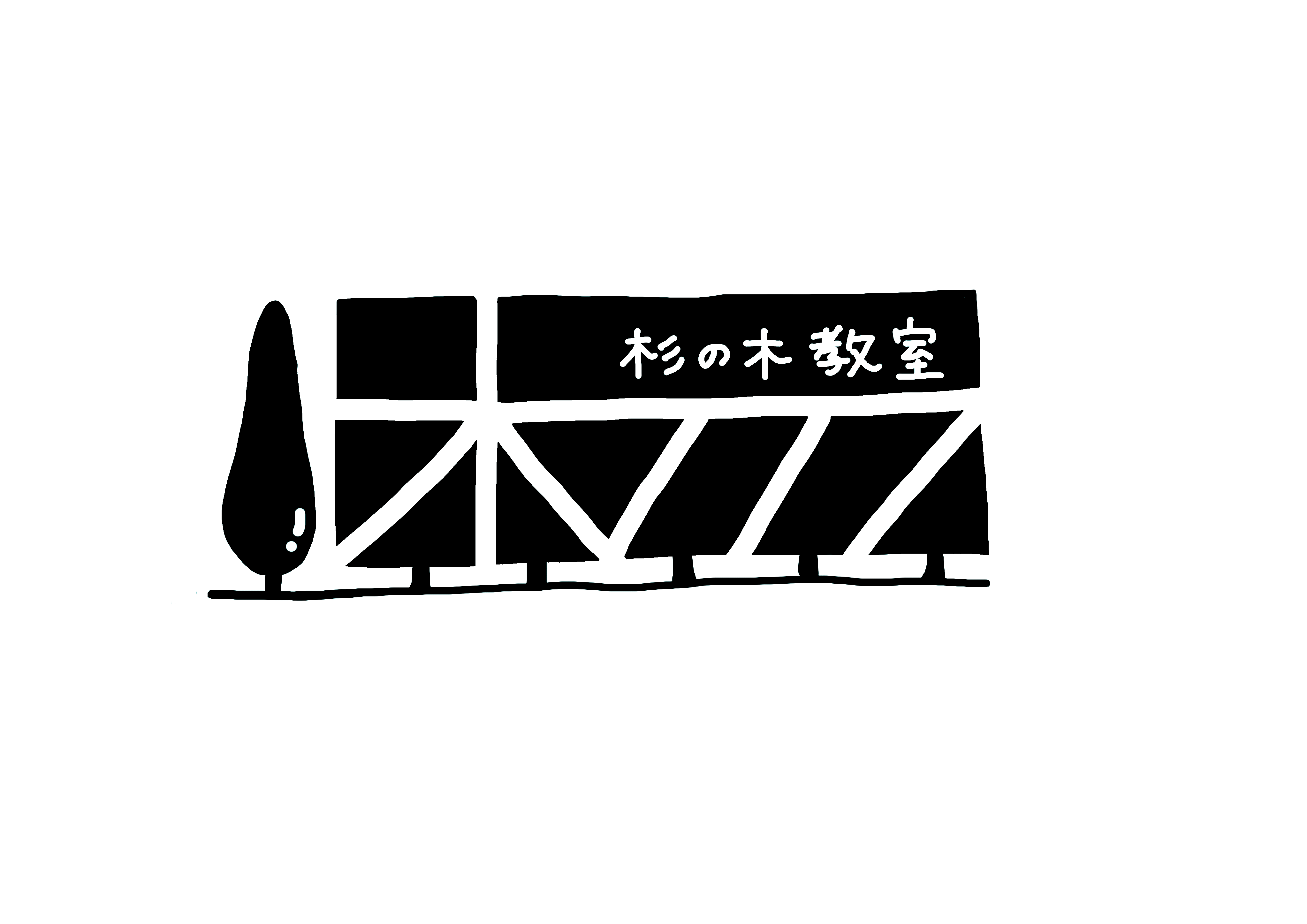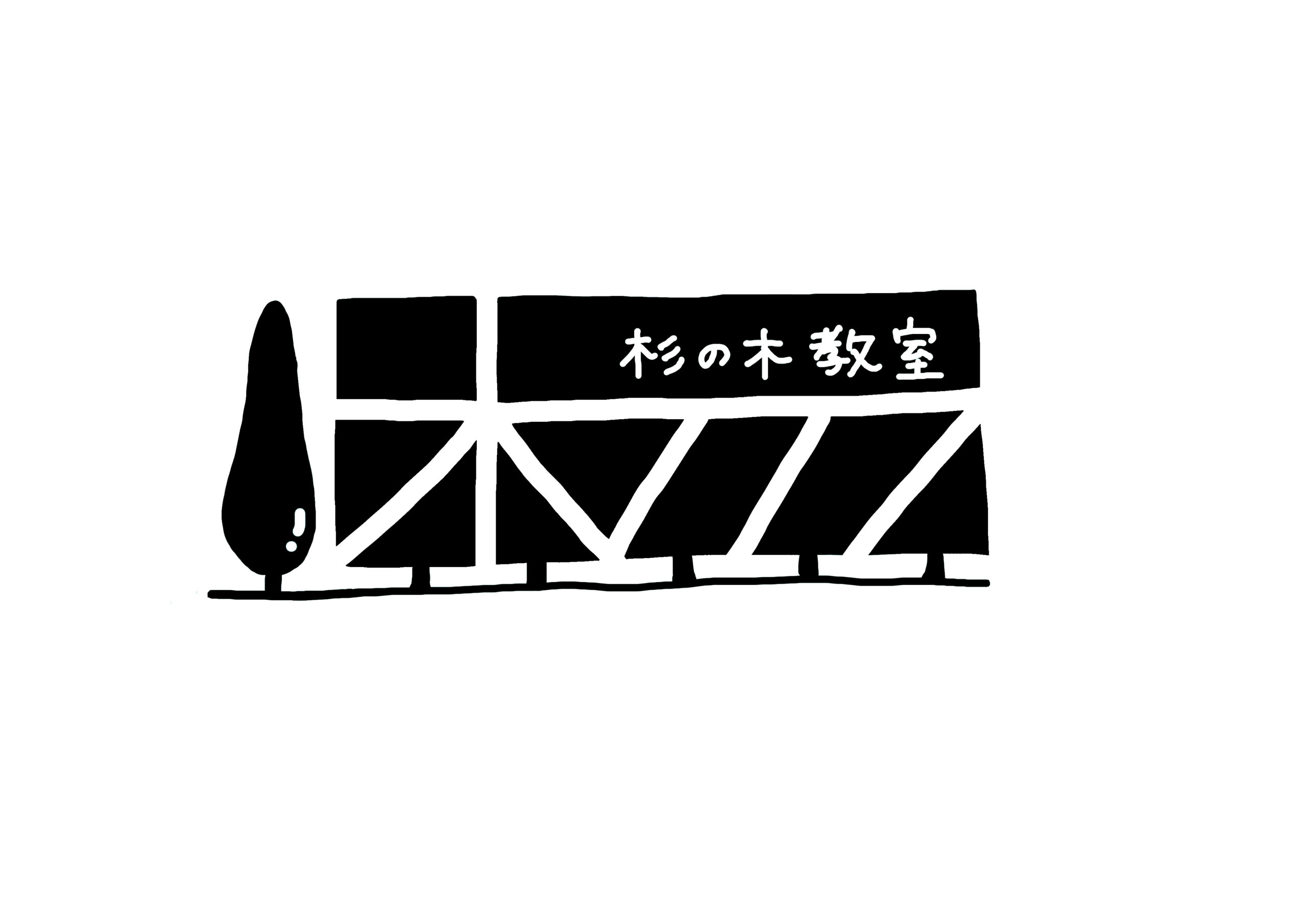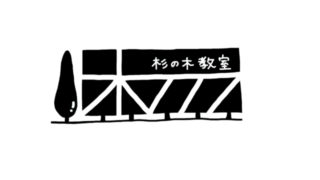金谷武洋氏の『日本語と西欧語』は、本屋で見かけて、なんとなく買った本である。そこに書かれていたのは、日本語には主語がなく、それによって主語が絶対必要な英語話者とは世界の視点が違うというものであった。ここにヒントを得て、文法を探れば、そこには存在論が潜んでいて、その存在論の歪みは、文法を操作することによって補正できるのではないかと思ったのだ。この道は半ばで、これからもっと思索を重ねなければならないが、日本語を深く知ることについては他の興味とも結びついている。
ニーチェは本当の教養は母国語の深い理解によって得られるとしている。それは「自然的な実り豊かな地盤」であり、私が考える「根」と重なる部分がある。母国語の深い理解のためには、二通りの道が必要だろう。一つに言語を通した「精神文化の理解」と、二つ目には「言語自体の構造の理解」である。
ニーチェはいう、「厳格で芸術的な配慮のゆき届いた言語上の訓練と風習の根拠の上に初めて、私たちの古典作家の偉大さに対する正しい感情が強められる」。詩や物語から、それらが生まれてきた精神を凝視し、自らもまたそのような詩や物語を生むような精神を持つ。これが母国語の深い理解の一つ目の道である「精神文化の理解」となる。
また他からも同じようなことを感じた。こちらもまた古本屋で見かけたずっと気になっていた本だ。小林秀雄『本居宣長』。残念ながらまだ最初しか読めていないが、こちらの本がきっかけで宣長の原文を読みたくなって購入したものに『紫文要領』という『源氏物語』についての一編がある。そこには「もののあはれ」についてのこんな文章があった。「右のやうに古物語を見て、今に昔をなぞらへ、昔に今をなぞらへて読みならへば、世の有様、人の心ばへを知りて、物の哀れを知るなり。」また「さてその見るもの聞くものにつけて哀れなりとも悲しとも思ふが、心の動くなり。その心の動くが、すなはち物の哀れを知るといふものなり。」古い物語や人々との共感が、「もののあはれ」を知るということであり、私たちの「根」を自然的に太く強くしてゆくものであると思う。つまり母国語を深く知るための言語を通した「精神文化の理解」は、いわゆる「もののあはれ」を知ることであり、言い換えればさまざまな感動を通時的に体験してゆくことである。
私にとっての「精神文化の理解」への手段はなんであろうかと、具体的に列挙してみた。①『古事記』、②『万葉集』、③『古今和歌集』、④『源氏物語』、⑤器などに代表される民藝。
① 『古事記』は、私は神主ということもあるし、日本最古の歴史書でもあるので外せないと思う。『日本書紀』も似たような神話が書かれているが、『日本書紀』が国外向けに漢文で書かれているのに対して、『古事記』が国内向けに万葉仮名で書かれていることは、日本という私の祖国の精神文化を理解するには適しているだろう。
② 『万葉集』は、こちらも最古の勅撰和歌集であり、貴族から庶民に至るまでの日常の悲喜交々が歌となって記されており、さまざまな感動を通時的に体験するにはまず手に取るべきであろうと思う。また、『万葉集』以後の歌がその影響を受けているため、それらの理解にはまず『万葉集』を知ることが必要であろう。
③ 『古今和歌集』は、いわゆる「たをやめぶり」を味わうためには必要であろうか。『万葉集』は「ますらをぶり」の歌集であると近世(江戸中期)國學者の賀茂真淵が主張したものであり、「ますらをぶり」とは「男らしく」「日本男児らしく」というほどの意味で、「男性的で大らかな歌風」のことをいうものだ。一方、『古今和歌集』の歌風を「たをやめぶり」といい、女性的で優雅な歌風のことを言う。賀茂真淵は、本来の日本の歌風は「ますらをぶり」であるべきと言ったが、本居宣長は「たをやめぶり」であると言った。と言うのは、男性的なものは中国にあるが、女性的なものは日本にしかなく、それこそ日本独自の精神文化であるとした。私も宣長の意見に賛同であるために、「たをやめぶり」である古今和歌集は読むべきであると考えている。
④ 『源氏物語』については、物語文学の最高傑作と言われており、宣長も取り上げ、「もののあはれ」つまり日本における中世のさまざまな感情を体験し理解するには適しているであろう。また今年の大河ドラマでは紫式部が主人公である「光る君へ」が放送されており、それへの単純な興味からも深く内容を知りたいと思っている。
⑤ 民藝については、文章だけでなく、器や郷土玩具、布や調度品に至るまで、それらを作った人々、そして使った人々の心が身をもって知ることができるものであり、「精神文化の理解」に役立つものであると思う。単純に美しいと感じ欲しくなるとともに、それらの向こうにある人々の息遣いと寄り添うことができるような気がするので興味がある。また大量生産されたものにはない温かみと言われるような個物としての美しさが、抽象化をされて消え去ってしまった物事の本質を捉えていると思う。
これらの他にも学ぶべきものはたくさんあるだろう。ここにあげたものは時代が偏っているし、現代に近くなると国外からの影響も多く、全てを学び体験し尽くすことはできない。量にこだわらず、ひとつひとつ丁寧に向き合いたいものである。
物語と歌とは、人が「もののあはれ」を知り、そのことを表現して他人の共鳴を求めるところに生まれるという点で、本質を同じくすると考えたのは、本居宣長である。民藝についても長い歴史をかけて共鳴された形や色が、現在の私たちの心にも届くのではないだろうか。理論だけではなく、心や体が響きあうようなものが「もののあはれ」の本質であり、それは提示されるというものではなく、体験されるものなのかもしれない。物事を外から眺めるのではなく、自らがその中に入ってゆくという外側のない世界は関係性の存在論であって、哲学という普遍を求める学問が突き当たる問題であろう。概念で語る世界説明だけではなく、体験として広がる世界説明の側面がここにはあると思う。
母国語の深い理解には、このような「もののあはれ」を体験し「精神文化の理解」を深めてゆく道と、もうひとつ「言語自体の構造の理解」への道がある。こちらの道は、具体的には日本語文法の理解であり、「もののあはれ」とは違って、外側から日本語を観察するものである。
日本語文法については全く知らない。金谷武洋氏の本を読んで興味を持ち始めたところである。私が日本語文法に期待していることは、その構造から日本語話者の世界観を引き出し、他の言語との比較、ならびに世界観の補正が必要な場合は、日常的な言葉を変えることによってそれをなすことができるようになることである。現在私が興味を持っている二つの文法的側面から存在論的側面への考察を紹介する。
一つ目は金谷武洋氏の視点の考察である。金谷氏によると、「日本語はある状況を、自動詞中心の『何かそこにある・自然にそうなる』という、存在や状態の変化の文として表現する。一方、英語は同じ状況を、『誰かが何かをする』という意味の、他動詞を挟んだSVO(主語―他動詞―目的語)構文で示す。つまり、人間の行為を積極的に表現する傾向が強い」という。例えば、日本語の「お金がある」ということを英語では「I have money」という。お金がそこにあるという存在や状況を示す日本語に対して、英語では「私は」お金を持っているという人間の行為を示している。その他「中国語がわかる」に対して「I understand Chinese.」、「時間が要る」に対して「I need time.」、「声が聞こえる」は「I hear a voice.」。
このように日本語には動作主としての主語はないが、英語には動作をする主語がある。このことが世界観の違いを生むというのだ。このような違いが世界観を変えるというのは、どういうことなのであろうか。
金谷氏は川端康成の『雪国』の英語訳と原文との比較をとおして説明している。この名著の冒頭は、原文では、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」であるが、E・サイデンステッカー氏の英語訳では、「The train came out of the long tunnel into the snow country.」となっている。この二つの文章の間には「視点の違い」があるという。原文の方は、主人公が汽車に乗っている情景を思い起こさせ、読者もそれを追体験するような表現だ。暗いトンネルを抜け、明るくなった外の景色は、雪に埋もれていた。そのように「時間の推移とともに」景色が変わっていく様子が思い浮かぶ。一方、英語訳の方は、汽車が走っている風景を思い起こさせ、それを上方から見下ろすような表現となっている。列車がトンネルから頭を出しており、トンネルの外には雪が積もっている。このように暗闇から雪景色というような「時間の推移」は感じられず、止まった景色が思い浮かぶのだ。
これら二つの文を比較すると、原文には主語がなく、時間とともに変化する主観的な体験の描写がある。確かに「自動詞中心の『何かそこにある・自然にそうなる』という、存在や状態の変化の文として表現」している。これに対して、英語訳は「The train」という主語があり、時間の経過はなく、上方から見下ろす客観的な描写となっている。「『誰かが何かをする』という意味の、他動詞を挟んだSVO(主語―他動詞―目的語)構文で示」している。金谷氏はここに世界観の違いを見ている。そしてそれぞれを「虫の視点」と「神の視点」と呼んでいる。「虫の視点」では、話者の視点は対象化、客体化されずに出来事の内部にとどまっており、まるで虫が草むらを這ってゆくように次々と出来事が起きて、時間が経過してゆく。一方「神の視点」では、自分を包んでいた自然から自己を引き離し、もはや自分自身も対象化して、出来事の外部の上空から客観的に眺めており、その出来事を一気に把握し、時間の経過がない。この脱近代的な違いを言語の主語の有無やその視点において捉えているところが、私には大変興味深く、そして思索を進めることとなった。
二つ目は浅利誠氏の、場所格の格助詞の三つの類型と西田幾多郎の「場所」の概念についての考察である。格助詞とは、体言や体言に準ずるものに付いて、文中で他の語とどんな関係にあるかを示す助詞のことである。現代語の格助詞には、「が」「の」「を」「に」「へ」「と」「より」「から」「で」「まで」(「まで」については副助詞と分類するものもある)などがある。ここではこの中でも場所に関係するものを取り上げているので、「が、に、へ、と、より、から、まで、で、を」を分類している。これらを三つに分類したとき、西田の「場所」の概念とピッタリと重なることを指摘したものである。西田の「場所」の概念とは、中村雄二郎氏によると「(たとえば)ふつう自己とは、物体と同じく、そのさまざまな属性の集まり、つまり主語的統一と考えられているが、そうではなく、自己とはむしろ、そこになにかが起きる場所、つまり<述語的統一>と見られるべきである。自己とは点ではなくて円であり、物ではなくて場所なのである。」と説明されるものである。つまり静止的で名詞的ではなく、動詞的で出来事的な存在のあり方をいうものである。
浅利氏は格助詞を①「で」、②「を」、③「そのほかのすべて」の場所格の格助詞(が、に、へ、と、より、から、まで)の三つに分けて、それぞれの機能を説明している。
① 「で」
場所が円のイメージを伴って動詞(動作)と結び付けられる。
例:「庭デりんごを食べる」「庭デ遊ぶ」「庭デ読書する」
特徴:包摂
② 「を」
所定の場所がある動作=動詞と接触点を持って表象される。
例:「道ヲ渡る」「道ヲ通る」「廊下ヲ歩く」「床ヲ踏みつける」「家ヲ出る」
特徴:接触
③ 「その他すべて」の場所格の格助詞(が、に、へ、と、より、から、まで)
ある一点が矢印によって示されるイメージとして表象される。
例:「椅子ニ座る」「学校ニ行く」「会社カラ帰る」
特徴:分離
このように分類したのち、この中でも「で」は、すべての場所格の格助詞が「で」による限定を前提にして成り立っているという点で、特異なものであると述べている。浅利氏は、格助詞の条件は、「二つ以上の物や概念の中からあるものを選び取る」ことであるとしていて、この三つの分類の背後には格助詞「で」が隠れているという。たとえば、①「庭デりんごを食べる」といった場合には、他に「家デ」、「車デ」、「学校デ」、という選択肢の中から選び取っている。また、②「道ヲ渡る」と言った場合にも、他に「橋ヲ」、「海ヲ」、という選択肢の中から選び取っている。③「椅子ニ座る」についても同じことである。そしてここからさらに「この三つの分類の背後には格助詞「で」が隠れている」とはどういうことかというと、例にあげた選択肢をすべて包み込むような範囲の場所が隠れているということである。つまり、「大阪デ」や「日本デ」などの広範囲を含むということである。大阪という広い範囲の中の、特に「庭デ」りんごを食べるという、大きな円の中にある、いくつかの小さな円を選び取るのである。この意味で、「で」の背後にも「で」があり、その特異性となっている。
これらの場所についての格助詞の弁別範囲と西田幾多郎の「場所」の概念が重なるというのである。浅利氏は、「西田は、『個物があるためには、それがおかれてある場所がなければならぬ』という基本命題を通して、個物と場所との関係を、格助詞が喚起させる空間性、形象性に依拠して考えたと言える。すなわち、個物=点/場所=円という二項対立で考えたと言える。」と述べており、つまり、個物=点=格助詞「を」、「その他すべて」という対応と、場所=円=格助詞「で」という対応を指摘している。「場所」の概念が、そこで何か起きる場所、すなわち述語的統一の円のイメージと格助詞「で」の背後の存在としてのイメージが合わさったようなものとして語られているところは、浅利氏の格助詞の分類とよく重なり合っているし、存在論としても奥行きのあるものであると思う。
このほかには、助詞の「は」と「が」の違いなど興味深いものがある。少し触れると、「は」は、主題を表し、文末まで意味を及ぼし、文末と呼応する。「が」または「を」などは、最寄りの用言に係る。というもので、一般に主語を表すと言われているものでも、実は意味が違い、そしてその違いは、係り方、影響の及ぼし方にあるというものである。「は」の影響の及ぼし方を考えると、それは主語的ではなく、むしろ述語的に文末と呼応するというもので、こちらも西田の「場所」の概念と響き合うものがある。
いずれにせよ、まだまだ道なかばで、もしかしたら一般的には周知のことなのかもしれないが、日本語文法の中に存在論を見出すことに夢中になっている。「もののあはれ」を知り、深く共感することで日本の精神文化を知る。そしてまたそれらを体験する。その精神文化を伝える言語の構造も深く知ることで、また内容も豊かに深く響いてくるであろう。そしてそれらの説明が終えたら、存在と私というものがよくわかるのではないかと考えている。
令和6年11月8日