ある作家の全集を全部読むというのが、作家になるためにはいい方法だという。小林秀雄が言っていたから信憑性は高そうだ。他にも薦める人がいたので影響され、全集読みを始めている。そのコツは好きな作家の全集で、なおかつ量が多くないものがいいと聞いて調べていたら、ニーチェが15冊だったので、私にとっては少なくはないが、他の著者はもっと多かったし、ニーチェに興味もあるので決めたのだ。
そもそも神主である私が作家になるための方法を日課にしているのはどういうわけかというと、哲学書を書いているからだ。哲学に興味があるというのはちょっと照れ臭くてあまり人には言わないが、大学は哲学科であって、哲学愛好歴は結構長いのだ。しかしなんの思想も持ち合わせず、なんなら哲学書をまともに読んだこともなかった。全て理解した本でいうと1冊も読めていないと思う。このままではダメだという思いと、少しずつわかることも増えてきたので、もっと勉強するために自分に負荷をかけたのだ。
ニーチェに興味もあるし、また全集の冊数が他のものより少ないからといって、ニーチェの全集を読むことが簡単かと言えば全くそうではない。本当のことを言えばかなり苦しい。辞めたいと思ったことは1度や2度ではない。しかし一度決めたことだし、全集を全て読み終わった後の達成感を想像したら、なんだか力が湧いてくるので頑張れている。
さらに苦しさを和らげるために、少しハードルを下げて読んでいる。私は本を読むのは好きだけど得意ではなく、黙って読んでいるとどこを読んでいるかわからなくなったり、違うことを考えていたりと、うまく読めない。眠気も襲ってきたりしてすぐに辞めてしまうこともあるのだ。だから黙読するのではなく、声に出して読んでいるのだ。他の本はレジュメを作りながら読むこともあるが、全集読みでそれをしていたら何年かかるかわからない。だから理解ができなくても、とにかく先にいってしまうという「素読」をしている。「素読」とは理解を度外視して音読することを言う。理解を度外視するので、全集読みの効果は半減するかもしれないが、こうしないと途中で辞めてしまいそうなのだ。
しかしこの「素読」が結構いいかもしれない。消極的な意味で「素読」を選んだが、もしかしたら一番いい方法かもしれないとさえ思っている。この「素読」には主客を合一させる、簡単に言えば参加型の読書をさせてくれるような気がしている。「主」である私と「客」であるニーチェの著作が一緒になるのだ。もちろん「素読」が西田幾多郎の主客合一であるとか、二元論の解決策であると言うような大それたことを言おうとしているのではないが、しかし半分冗談で、半分真剣にこの「素読」のことを考えてみたのである。
声に出して読むことによって、黙読よりも刺激が多くなる。このことで別のことを考えたり、眠気が襲ってきたりするのを少しは防ぐことができる。これらだけでもかなりありがたい。読書が苦手な私を支えてくれている。しかしさらに「素読」は私を「その気」にさせてくれるのだ。ニーチェの言葉遣いや長い一文、古代ギリシア哲学者たちの読みにくい名前、これらが文字のままではなく音となって私の耳に届く時、私は一歩ニーチェに、古代ギリシアの哲人たちに、そして哲学に憧れているだけではなく自らも思索する哲学者に近づいたような気になる。そして音を通して彼らの情熱が伝わってくるような気がして、楽しくなってくるのだ。
このことはソルフェージュと似ているような気がする。ソルフェージュとは、音楽の用語であるが、楽譜にしるされた音楽と、実際の音楽を結びつける勉強の総称である。しかし、ここで私が言いたいのは、単に旋律を口に出して「歌う」ことである。例えば複数の人数で旋律のニュアンスを揃えるために、楽器を置いて口で「歌う」ことをする。こうすることで言葉での説明よりも具体的に音楽を感じることができ、よくニュアンスが揃うのである。また一曲を最初から最後まで歌い、盛り上がるポイントを体を通して掴むことによって、作曲家の意図がよくわかることもある。さらには違うパートの旋律も歌って体に入れると、自分の楽器だけでなく他の人の楽器まで自分の音楽と感じることもある。このように「口に出して言うこと」は、筆舌に尽くしがたい何かを掴むことを可能にすると思う。
音楽におけるソルフェージュのように、「素読」は本の内容のみならず、行間に込められたいわば著者の息遣いのような言葉にできないものを私に与えてくれていると思う。だからと言ってニーチェがのりうつったように私が思索できるようになったわけではないが、最初に感じたニーチェに対する違和感というか、人見知りをしているような感覚は無くなっていったのであった。
すなわち私が言いたいのは、黙読するよりも「素読」の方が積極的になれるということである。積極的にニーチェの著作の中に入っていくことによって、自己と対立する外部のものという違和感のあるものから、自己の内部に湧き起こる感情のように親近感のあるものへと、ニーチェの著作が変わっていくということである。例えば祭りにお神輿を見にいったとすると、遠くからりんごあめを舐めながら神輿の渡御を見ている状態が「黙読」である。一方、着ていたアロハシャツを引きちぎって汗と怒号の中にわけ入り、自らも神輿を担ぐことが「素読」である。あまりに極端な例えであるが、それぐらい違いがあるかもしれない。見物客と神輿舁、臨場感がまるで違うであろう。
そもそも全集読みの効用は、その作家の傑作だけでなく駄作や日記を読むことによって、その作家に世間がはったレッテルを剥がし、生の姿を感じ、何を捨て何を残したかを知ることによって、作家としての進み方を参考にすることができるということである。この効用から考えた場合、積極的にその中へと分け入っていく神輿舁的な読み方、すなわち「素読」はもっとも良い方法と言えるのではないだろうか。著作の一つ一つを丹念に読み込み、その思想を正確に理解し、記憶に留めておくことはもちろん重要なことであるが、神輿の雑踏の中に飛び込んでもみくちゃにされることによって、祭りとは何であるかを肌を通して感じる、そのように一流の哲学者という激流の中にその身を晒して自己の思想の崩壊の危険さえ感じるような体当たり的な「素読」は、作家の仕事の文字にならない心構えのようなものを体得するにはうってつけであるように思う。
外山滋比古はその著書『異本論』の中で、「文学作品は物体ではない。現象である。」と述べている。これは古典作品がその誕生の時からたくさんの読者に読まれてゆき、さまざまの解釈がされて、「古典」となるのであって、その原始の姿こそが真の姿であるという「原稿至上主義」を批判していった言葉である。もちろん著者の原稿に他者による書き換えがあるままがいいというようなことは言わないが、その書き換えもまた一つの価値のあるものだとする考え方である。その意味で作品は原始の姿という「物体」ではなく、その後たくさんの読者に読まれ、さまざまな解釈をされているという「現象」であるというのである。
神輿は神様の乗り物であって、神様に神輿に乗っていただく神事が行われる前はただの「物体」である。そこに神様がお乗りになられて、それを神輿舁たちが「わっしょい」とすることによって生きた祭りという「現象」となる。もちろん見物客も祭りには必要だ。こういったさまざまな立場の人たちが関わることによって祭りは「現象」として生きたものとなる。本は誰にも読まれていない時は「物体」であり、読まれることによって「現象」となり、現実に働きかけてゆく。ニーチェという哲学者の著作は現在でもたくさんの人たちに読まれており、ニーチェ哲学という生きた「現象」である。私はその「現象」の中で神輿舁のように積極的に関わりたいのだ。つまり見ているだけでは嫌なのだ。その試みとしての「素読」であり、哲学書の執筆である。
世の中をよく見渡すと、「声に出す」ということは重要な行為と考えられている。齋藤孝『声に出して読みたい日本語』では、「かつて暗誦することは言語感覚を養い、心と身体を鍛える訓練法の一つだった」と紹介し、安全度では世界トップクラスを誇る日本の鉄道では、「指差し声出し確認」が徹底されている。また雅楽の世界では、楽器を練習する前に一年ほど「唱歌」という歌を口伝で覚えさせられ、その上で楽器を持つことを許される。「声に出す」ことで、理解や注意の確実性が高まり、心身ともに鍛えられるというのである。
フランスの現象学者メルロ=ポンティは知覚の主体である身体を、主体と客体の両面を持つものとして捉え、世界を人間の体から柔軟に考察することを唱えた。身体から離れて対象を思考するのではなく、身体から生み出された知覚を手がかりに、身体そのものと世界を考察した。「素読」をするとき、客体である「文章、それが指し示す内容」は、主体である「私」の「体」を通して声、音となり、それを耳で認識し理解する。「文章」と「私」の間にある「体」は、主体と客体の両面を持つものなのだろうか。
現在ニーチェの全集は15冊中2冊目である。まだまだ始まったばかりだ。1冊目の『古典ギリシアの精神』は、文献学者としてのニーチェの姿を見ることができる。ディオゲネス・ラエルティオスの著書を分析し真実に迫ろうとする情熱や、ギリシア人の祭祀について詳細に語る筆致は、『ツァラトゥストラ』などの著作とはまた違った印象を私に与え、ニーチェの学者としての変遷を少し見ることができた。今後はさらに読み進めながら、それが書かれた時代の言葉や表現の意味をもっと感じていきたいと思っている。というのはミシェル・フーコーの分析方法に興味を持ったからだ。
フランスの哲学者ミシェル・フーコーは、同じくフランスの比較神話学者ジョルジュ・デュメジルに影響を受け、その緻密な方法で研究をした。膨大な資料を丹念に読み解き、そこに現れる要素をそれぞれのレベルで振り分け、それらの差異を比較検討し成立条件や背景を規定していくという分析手法だ。資料には、モニュマンとドキュマンという2つの意味がある。モニュマンは記念碑という意味で、資料の物質的な側面だ。ドキュマンは記録で、内容的な側面である。ある資料に対して、物質的側面からは、それがなぜ紙や木簡に書かれているのかを分析し、内容的側面からは、どんな影響を受けているかなどを分析する。ここで特徴的なのが、モニュマンは物質的なものであるが、ここに言語や表現もフーコーは含めるのである。ある言語や表現がどのような歴史的社会的条件で成立して、知識や権力と結びついたかを分析するのである。すなわち言葉や表現に対する反応の差異を明らかにするために資料を収拾して分析するということである。よってどんなものでも資料になり、それらに序列はなく、膨大な資料から浮かび上がる無意識的な構造を明るみに出すのだ。言説の背後にある社会的構造や権力のメカニズムを明らかにするという分析方法である。
このように言葉の意味を現実社会の中で捉え直し深く吟味していくというところに、平面的で静止した「物体」ではなく、常に動き変化する「現象」として言葉を捉える姿勢を感じたので興味を持ったのだ。「素読」をするときにもその言葉がどこからきたもので、どのような影響を与えるかを想像するとまた違ったものとなるかもしれない。
ちなみにフーコーは、人間という概念は近代にできたもので、さらに近代の学問は結局のところ人間を扱うものであり、近代の知の枠組みが崩壊すると、人間という概念も崩壊するというのだ。(『人間の終焉』)この背景には、相対主義的な「真実はわかりっこない」という思想があると思われる。それは主客の合一はあり得ないという考えだ。その解決に竹田青嗣氏は、フッサールとニーチェを用いていた。このことについては今後の課題とするが、半分冗談に、またしかし半分真剣に、この主体と客体の両側面を持つ身体的な「素読」に解決の糸口はないだろうかと、ふでのまにまに「素読」をしている。
令和6年5月24日
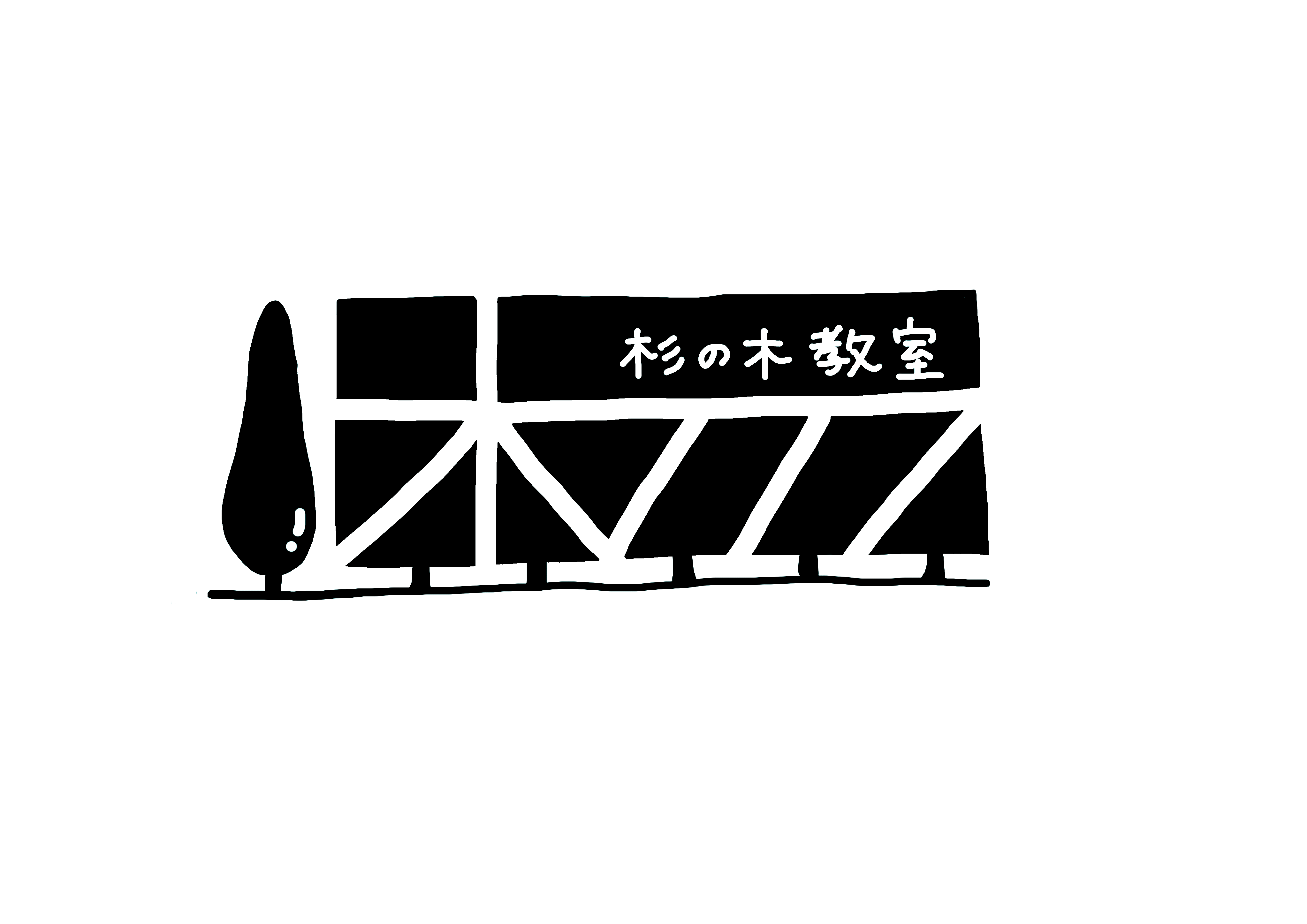
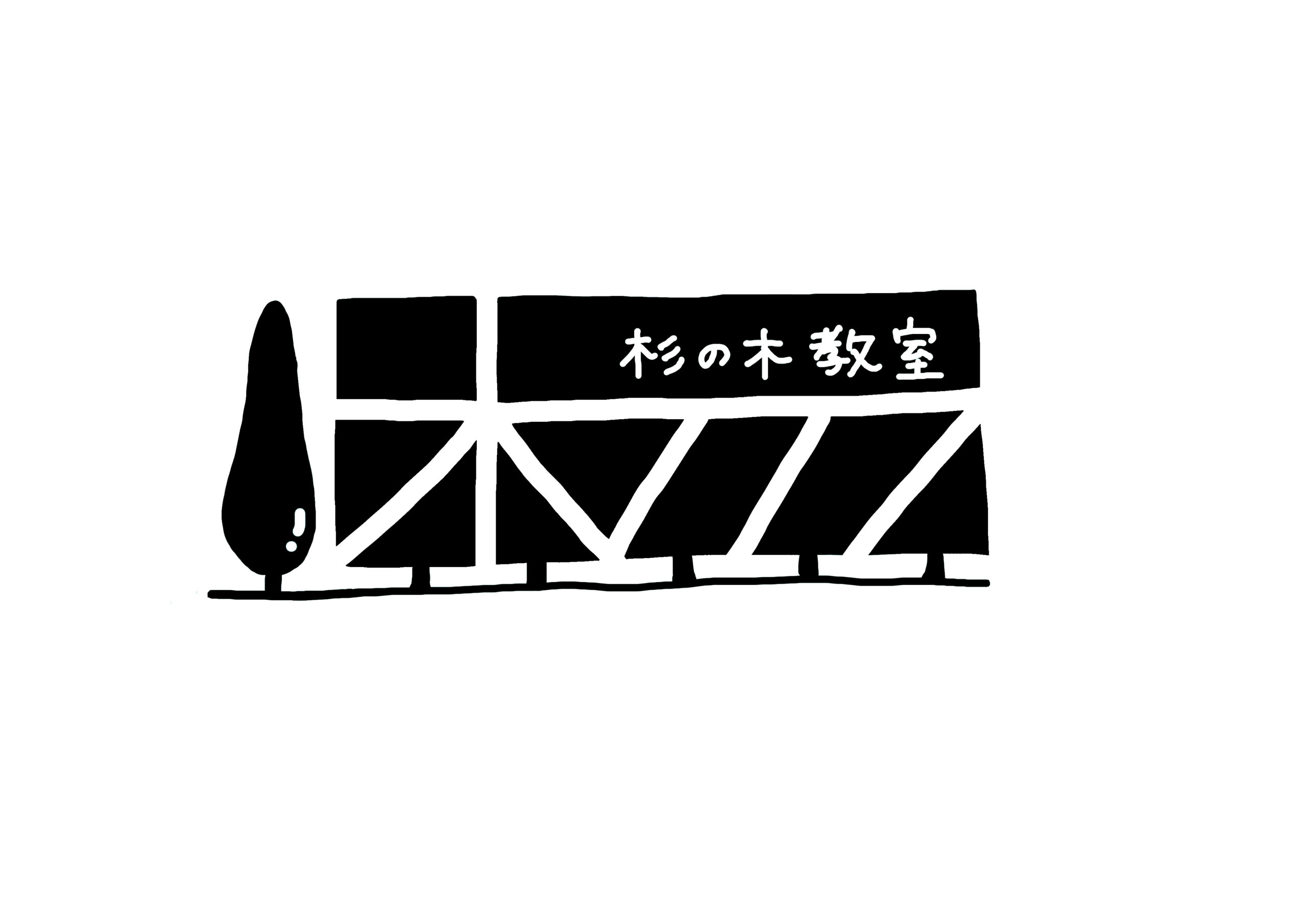
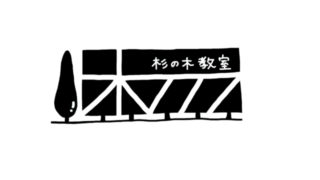

コメント